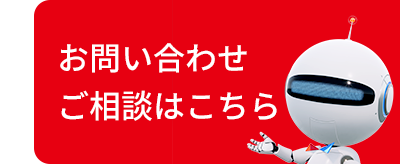日経産業新聞フォーラム スペシャリストの智 CREカンファレンス2020-2021・レポート

目次
三菱地所リアルエステートサービスが協賛する恒例イベント「日経産業新聞フォーラム スペシャリストの智 CREカンファレンス」。2021年はコロナ禍での感染症対策ということもあり、オンラインイベントの形で開催されました。コロナ禍で厳しい経営環境が続く日本ですが、そこでも勝ち残る企業があります。その条件とは何か。いま打つべき手は何なのか。現政権の「成長戦略会議」メンバーでもある経済学者、竹中平蔵氏に貴重な提言をいただくと共に、これからの不動産ビジネスのあり方について、経営コンサルタントの藤沢久美氏と当社代表取締役社長である湯浅哲生が語り合いました。(モデレーター:日経 CNBC キャスター瀧口友里奈氏)
PART1 生き残る企業の成長戦略今こそ、俯瞰の視点で状況を見定め、
誰よりも早く変化しよう
慶應義塾大学 名誉教授/東洋大学 教授
竹中 平蔵氏
バルコニーに駆け上がり、全体状況を捉える
──2020年は、日本企業にとってこれまで経験したことのない逆境の1年でしたが、コロナ禍に見舞われる日本経済をどのようにご覧になっていましたか。
昨年2020年の1月、私はちょうどダボス会議に参加しており、各国の指導者たちが世界経済について驚くほど楽観的な成長見通しを語るのを聞いておりました。その時点ですでに新型コロナウイルスは発生していたのですが、それがこれほどまでの影響を与えることを予想できる人はまだ誰もいなかった。人間の知見の限界をあらためて感じます。
結論から申せば2020年の世界経済は4~5%のマイナス成長になるでしょう。日本もまた2020年期4~6月のGDP成長率は年率換算でマイナス29%でしたから、通年で見てもこれが響くことは確かです。日本は企業の倒産件数こそ少ないものの、その6倍程度の数字で休廃業が増えています。政府や日銀の財政措置でなんとか首の皮一枚でつながっているという状況です。
しかしながら、こうした時期だからこそ、バルコニーに駆け上がり、高い位置からあたりを俯瞰するような視点で状況を捉えることが大切です。そうすると、これまでコロナ禍がなくとも、静かに変化していた流れが、コロナ禍によって加速化されているという事態が見えてくると思います。
例えば、コロナ禍によって、やろうと思っていてもなかなか進まなかったデジタル化が加速されました。企業が軒並み業績を落とす中で、4分の1の企業は大きな利益を出していることも見逃してはなりません。デジタル技術やグリーンビジネスに関連する企業はむしろ好調です。企業の明暗がくっきりと浮き彫りになっているのです。
──こうした時期にも生き残れる企業の条件は何でしょうか。
ダーウィンの進化論を例に挙げれば、生き残る種というのは変化する種です。例えば、飲食産業はコロナ禍で大きな打撃を受けましたが、テイクアウト・ビジネスにうまく対応したところは意外と売上が減らなかった。働き方を見直し、リモートワークを増やしたところ、学校でも遠隔授業を以前から準備していたところは、事態に柔軟に対応できたのではないでしょうか。
変化を促す強いリーダーシップと、そのリーダーを信頼して行動を起こすフォロワーシップの両方をもつ企業こそが、この時代には強いのです。リーダーとフォロワーの信頼関係をどう醸成するかは難しいところですが、やはり経営者は一時の成功体験にとらわれることなく、どんどん前に行く姿を示すことが重要です。あるアパレル企業の経営者は「成功はその日のうちに忘れてしまえ」と語っています。常に変化を見続けて、それに対応することが今ほど重要な時はありません。
さらなる規制緩和で日本企業のポテンシャルを解き放つ
──株価が持ち直し、予想以上の回復をしています。日本経済のポテンシャルをどうご覧になっていますか。
コロナ禍で消費需要は落ち込みましたが、工場などの供給サイドが機能しなくなったわけではありません。供給力がある一方で需要が減ると物価は上がらず、むしろデフレ気味になります。そうなると余ったお金は株式などの資産市場に向かうものです。それが、株価が高い水準を推移しており、不動産価格も上昇しているという現象の背景にあります。もちろん株価が高いことは結構なことですが、今後幾度か揺らぐ可能性はあるので、そこは気をつける必要があります。
日本経済のポテンシャルですが、これは大いにあると思います。日本企業はテクノロジー、マネー、人材リソースを持っています。ただ、これまではそれを有効に活かせないでいました。規制に象徴される硬直的な仕組みがあったからです。それを取り除いて、ポテンシャルを引き出すような規制改革、構造改革ができるかどうかが、これからの決め手になります。

──コロナ禍ではデジタル化の遅れも表面化してきましたね。
はい。しかし日本は、実は世界で最初にすべてのテレビのデジタル化を実現した国なのです。デジタル技術の基盤はあるのです。ただ、それが企業活動の隅々まで進まなかったのは、実は働く仕組みの問題があったからです。いまだ多くの人は時間に対して賃金が払われています。しかし、労働市場改革の一環として導入された高度プロフェッショナル制度のように、時間ではなく成果でその人の賃金を図るというように仕組みを転換していかないと、デジタル化も進みません。
何を成果とするかはもちろん議論が必要です。各企業でそれを検討してほしい。少なくともこれまでのようなメンバーシップ型からジョブ型の働き方に変えることが、デジタル化を進める上で重要なことになります。
5Gと共に進むデジタル化
格差を生まないためにもインフラ投資が課題に
──リモートワークの普及は今後どうなるでしょうか。
リモートワークだけですべてが解決するとは全く思いません。オンライン会議は便利ですが、人に小声で話すようなスモールトークがしにくい面もありますし、前から見知った人とはやりやすいが、初対面の人とはコミュニケーションがとりにくいというデメリットもあります。やはり、リモートとリアルの両方のハイブリッド型がいいですね。
もう一つ、デジタル化は新しい格差を生み出しかねないことにも注意が必要です。現政権で新たに発足予定のデジタル庁の役割の一つは、デジタル格差を生み出さない仕組みを作ることにあります。スマートネーション構想を進めるシンガポールでは、デジタル技術が不得意で困っている人をサポートするデジタルアンバサダーという制度が機能しています。日本でも地方で一人暮らしのお年寄りなどにはそういうサポートが必要でしょうね。
さらに、デジタル化は5Gという新しい通信インフラ技術と同時並行に進んでいることにも注目したい。5Gによって人とモノ、モノとモノがさらに繫がるようになります。例えば、畑の作物の成長をインターネットで監視することができるようになります。日本のインターネットは、国土の60%しかカバーしていない。そのためのインフラ投資がこれからますます重要です。
5Gの進展で遠隔医療もスムーズに行われるようになります。国家戦略特区構想をさらに強化したスーパーシティ構想もさらに進みます。できれば3月末ぐらいまでに第一次スーパーシティの候補地を決めたい。そこでは企業にも積極的にチャレンジして欲しいですね。構想を推進する主役は民間企業にあるのですから。
危機の時代にこそ高まる企業不動産の価値
アジャイル態勢で変化を受け容れる
──企業が財務体質を強化するためにこれから投資すべき分野として、不動産の価値をどうご覧になっていますか。
マネーが不動産や株などの資産に移動していると先ほど申し上げました。不動産の資産価値はこれからますます高くなると思います。ちなみに、東京圏で百年続く老舗企業はビル賃貸業など不動産業が多いのをご存知でしたか。例えば、江戸時代の頃、都心で回船問屋をやっていた会社。もう回船業はやりませんが、所有している不動産をビルに建て替え、賃貸してビジネスを続けています。たとえ業種は変化しても、やはり、いい場所に不動産を保有し、それを時代に合わせて適切に活用することは企業にとっての強み。それが企業の存続や成長を支えているのです。
投資対象の資産でいえば、有形固定資産だけでなく、もう一つ、無形資産の価値にも注目したいものです。無形資産にはデータベース、研究開発、人材・組織の3つがありますが、この無形資産に着目し、積極的に投資している企業はやはり強いし、リーダーシップとフォロワーシップの信頼関係のベースもそこから醸成されています。
──最後に、2021年の企業経営に取り組む経営者の皆様にメッセージをいただけますか。
繰り返しますが、こんな時代だからこそ、バルコニーに駆け上がり、俯瞰して物事を見る視点が大切になります。その上で、変化に臆病であってはならない。技術が急速に進歩することで、若い人からの提案がわからなくなってしまったとこぼす経営者がいますが、たとえ理解できなくても「まずはやってみよう。ただし、期限を設けて、その間に何らかの成果を出そう」と呼びかけることが大切なのではないでしょうか。アジャイル(素早い・機敏な)の姿勢で変化を受け容れるということですね。
そのためには年齢、性別、国籍などの壁を超えた組織のダイバーシティを高める必要があります。経済危機で変化が急速に進む時代は、それだけチャンスがあるということでもあり、同時に、企業間の格差が明確になる時代でもあります。ぜひコロナ禍を乗り越えて、新たな成長に向けてチャレンジしていだきたいと思います。
PART2 強い企業と言われる資産戦略コロナ禍で注目される日本の不動産
チャレンジするための重要な資源に
対談
シンクタンク・ソフィアバンク 代表 藤沢 久美氏
三菱地所リアルエステートサービス 代表取締役社長 湯浅 哲生
経営者のマインドはどう変わったのか
──コロナ禍で日本企業の経営者のマインドはどう変わりましたか。
藤沢
2020年は、一口で言えば経営者のマインドが変わらざるをえなかった一年だと思います。これまでやらなければとは思っていたがなかなか進まなかったデジタル化を、いわば強制的にでも進めなくてはいけない。リモートワークも導入するしかないという風に変わってきたと思います。
ただ、テレワーク一つをとっても、都市部と地方ではまだ差があります。都市部の企業は対応が速やかでしたが、地方ではそうでもない。企業オフィスの地方移転についても、コロナ禍を踏まえて本社を移転させたい企業はまだわずか。社員の転居志向も、いきなり田舎にというより、大都市からそう遠くないところでというのが実態だと思います。
湯浅 デジタル化、リモートワークへの対応が都市と地方の企業で差があることは私も同感です。もともと格差があったところに一気に課題を突きつけられたわけですが、地方の企業には構造的にハンデがあるのは認めざるを得ません。
──日本と比べ、世界の経営者のマインドの切り替えはどうだったのでしょうか。
藤沢 世界といっても広いですが、少なくとも欧米先進国では、コロナ禍のあるなしに関わらず、デジタル革命への取り組みはすでに進んでいました。他にも気候変動、SDGs、ステークホルダー型経営など新しいコンセプトを立ち上げて、そこへ突き進んでいく姿勢はこれまでも鮮明だったと思います。ただ、誰もコロナウイルスの蔓延による都市ロックダウンまでは想定していなかったと思います。それでも世界の経営者はDX(デジタル・トランスフォーメーション)をこれからの経営の中軸に据えるという意識は強く、それは一貫していますね。
湯浅 日本はその意味での危機対応は少し弱かったですね。旗が振られればそれについていくスピードは速いのですが、自ら旗を振るというのは、日本企業は苦手な面があります。
藤沢 とはいえ、現政権でデジタル庁の発足が予定されており、気候変動についても「2050年温室ガス排出実質ゼロ」という大きな目標を掲げましたから、これからは変わっていくと思います。やはり有事の時代のリーダーは、誰よりも心配性であるべきで、危機感を先取りして、変わるための準備をしておくことが重要になります。
湯浅 先行きを心配するのがトップの仕事ですからね。これは自戒を込めて言うのですが、まずはトップが発信する。失敗を恐れずに具体的な行動を起こすことが大切。その姿を見せることで、社員も危機を乗り越えようと一丸になれるのだと思います。

自由度の高いオフィスが企業文化を創造する
──コロナ禍でも東京の不動産への投資が世界的に注目されています。
湯浅 JLLによる2020年上半期の都市別商業用不動産投資額ランキングでは、東京が150億ドルで1位という結果になりました。コロナ禍とはいえ、欧米に比べれば日本の状況は比較的安定しているという見方もあり、あらためて東京という都市ひいては日本という国の国柄、安定感、将来性などのポテンシャルが認識されたということではないでしょうか。こうした投資家からの評価は日本経済の回復にとっても追い風になると思います。
藤沢 このランキングではニューヨークが2番手に付けていますが、その背景にはアメリカの中でも現時点ではニューヨークが最も感染対策が行われおり、アメリカの他の地域に比べて相対的に安全であると見なされている向きもあると思いますね。
──いずれにしても企業はコロナ禍のもとでビジネスを進めるために、オフィス戦略の練り直しを余儀なくされています。日本のオフィスはどう変わりますか。
湯浅 昨年来、私どもも顧客企業に何度かアンケートを実施し、その課題やお悩みを伺ってきました。オフィス戦略という点では、リモートワークを中心とした、サテライトオフィス、シェアオフィス、在宅勤務などを具体的な選択肢として選びながら、各企業はオフィス戦略について試行錯誤しているというのが実情だろうと思います。一つひとつその有効性を試しながら、どのような戦略の組合せが自社に合っているかを探っている状況です。
藤沢 オフィスの定義自体が多様化してきましたね。オフィスは単に仕事をするために集まる場所ではなく、企業文化を創り上げる場であるという考え方も定着しつつあります。
湯浅 その意味で、これからのオフィスはより変化に対応しやすいように自由度を高める必要があります。場所が重要であるだけでなく、機能も重要になってくるのです。オフィスを分散化させる一方で本社機能はブランド価値の高い都心に置いたままというのも、これは人材採用などで優位に働く企業ブランドを維持するということであり、それはそれで重要な判断だろうと思います。
藤沢 オフィスは企業戦略の重要な一環であり、ひいては経営者の顔を映し出す鏡でもありますからね。オフィスの変化を見ながら、その背景にある経営者の決断を感じることはよくあります。
不動産を企業ブランド向上のために活用する
──企業にとって資産価値の考え方にも影響はあるのでしょうか。
湯浅 もう一つコロナ禍がもたらした影響ということでは、あらためて企業の資産価値の見直しが進んだということが挙げられると思います。とりわけ、本業を支えるための不動産投資、その活用法があらためて重視されています。
藤沢 例えば、DXへのチャレンジも必ず成功するとは限らない。失敗して業績が一時マイナスになるというリスクもあります。そこで最低限の収入確保を考えたとき、不動産の役割は重要になりますね。いわば企業が新しいチャレンジをする上での資源となるのが、不動産といえます。
湯浅
不動産は単に目先の収益を上げるだけのものではありません。世界的なコロナ禍はあらためて、世界規模でのESG投資や環境投資への意識の高まりをもたらしていますが、こうした社会課題に取り組む際に、不動産を地域との関係性も含めた企業ブランド向上のツールとして活用するという視点が生まれているのも、新しい現象だと思います。。企業にとって自社の不動産その活用法を時代に即して見直すことでまた新たな価値が生まれます。
私たちも、いま地方の経済を支えるため、地元の金融機関などと協業して、不動産活用を提言することが大切であり、これは当社のような不動産仲介業の重要な使命だとあらためて感じています。
──2021年、これからも有事という事態がしばらく続きます。有事の際の経営が重視すべきポイントは何だと思いますか。
藤沢 課題はたくさんあるのですが、あえてワンポイントだけ指摘するとすれば、社内のダイバーシティだけでなく、社外との交流も含めて企業カバナンスを変える。組織における意思決定のプロセスを、誰にでもわかるようにより透明性の高いものに変えることが重要です。
湯浅 DXも技術を導入しただけでは変わらない。それを活かすも殺すも組織の力です。多様な商品・サービスを提供するためにも、組織の体質や体制を変えていくことがこれからの鍵になると思います。


Profile プロフィール
慶應義塾大学 名誉教授/東洋大学 教授
竹中 平蔵
博士(経済学)。一橋大学卒業。
ハーバード大学客員准教授、慶應義塾大学総合政策学部教授などを経て2001年、小泉内閣の経済財政政策担当大臣、金融担当大臣、総務大臣などを歴任。現在、公益社団法人日本経済研究センター研究顧問、アカデミーヒルズ理事長、(株)パソナグループ取締役会長、オリックス(株)社外取締役、SBIホールディングス(株)社外取締役、世界経済フォーラム(ダボス会議)理事などを兼職。

Profile プロフィール
シンクタンク・ソフィアバンク 代表
藤沢 久美
国内外の投資運用会社勤務を経て、1996年に日本初の投資信託評価会社を起業。1999年同社を売却後、2000年にシンクタンク・ソフィアバンクの設立に参画。現在代表。2007年ダボス会議を主宰する世界経済フォーラムより「ヤング・グローバル・リーダー」に選出。政府各省の審議委員や日本証券業協会、Jリーグ等の公益理事といった公職に加え、静岡銀行や豊田通商など上場企業の社外取締役なども兼務。

Profile プロフィール
三菱地所リアルエステートサービス 代表取締役社長
湯浅 哲生
1959年生まれ。1983年三菱地所(株)入社、2008年まで三菱地所ビルマネジメント(株)常務取締役を務めたのち、2009年より三菱地所にてリーシング営業部担当部長、ビル管理企画部長、ビル営業部長を歴任。2014年より常務執行役員としてビル営業、街ブランド推進、xTECH営業等を担当。2019年4月より三菱地所リアルエステートサービス(株)代表取締役社長を務める。三菱地所㈱グループ執行役員、三菱地所パークス(株)代表取締役会長兼務。