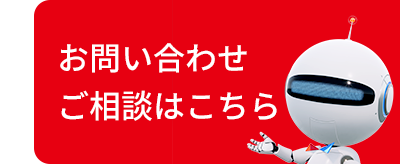コロナ禍は企業に何をもたらすか。
事業転換を模索し筋肉質に生まれ変わる

目次
新型コロナウイルスの感染拡大は日本経済に深刻な影響を与えています。中でも経済を下支えする企業にとってその影響はどのようなものであったか。苦境を脱するためにいまできることは何か。そこでは不動産戦略はどのような意義があるのか。税理士、経営コンサルタントとして長年、中小企業の経営者と伴走してきた土橋道章氏に、感染拡大からの半年間を振り返っていただきました。
「影響は1年以上続く」と3月初めで見切った経営者も
──土橋さんは税理士、経営コンサルタントとして長年にわたって中小企業の経営に関する相談に乗ってこられました。この半年間にわたるコロナ禍が企業に与えた影響とはどのようなものだったと言えますか。
私どもは全国のお客様から相談をいただいていますが、その多くが中小企業で、業種・業態は様々です。私自身、評論家ではないので実務家としてコメントさせて頂きますと、今年の2月時点では、コロナ禍の影響を感じている企業はほとんどありませんでした。インバウンド客を対象にビジネスを展開していた企業は、かなり早い段階から危機感を感じていたようですが、影響は一時的だと見る向きが多かったように思います。
ところが3月に入り、著名な芸能人などの感染や死亡がニュースで伝わると、様相が一変します。企業と言うよりは国民の意識が、新型コロナウイルスというのは怖しい病気だという認識に変わったように感じます。
先にあげたインバウンド需要を対象にビジネスをしている菓子製造会社の経営者に3月初め頃お話を伺った際には、「1年以上、ビジネスにならない」との判断のもとにいくつかの店舗を閉鎖したり事業整理をするという決断をされていました。数カ月ではなく、1年あるいはそれ以上という長期的なスパンで影響を感じていたようです。その後、東京オリンピックの延期が決まりましたが、インバウンド需要が当面消失してしまう事態を先読みされていました。
4月7日に7つの都道府県に緊急事態宣言が発令されてからの動きは、みなさんご存知の通りです。私どものお客様の中でも、特に影響があったのはアパレル業、飲食業、観光業です。特に飲食業や観光業は前年同月比で売上が10%もいかない。そもそも店が空けられない。緊急事態宣言の中、商品やサービスを提供するチャネルが対面に限られていたところは壊滅的な打撃を受けたといってよいと思います。
さらに緊急事態宣言下にはない地方の企業でも、従業員の家族が出社を心配する声にも配慮して事業を縮小するか迷われた経営者もいらっしゃいました。
──従業員のご家族の声にも配慮すると、純粋な経営判断だけでは済まなくなりますね。現場の経営者の苦悩がよくわかります。
これまでも働き方に関しては若手社員が飲み会に参加しないとか、育児に積極的に関与するなど、働き方の意識に関して世代格差はありました。今回、コロナ禍の状況では、テレビなどの媒体を通じて、家庭に毎日毎日、情報が届けられました。従業員の方も独身の方もいれば、親の介護や子育て中の方もいて、置かれている環境が違う中で、ご家族の声への対処について経営者も苦悩してらっしゃいました。何が正解か、答えが分からない中で経営判断をされていました。
医療関係のお客さまも大勢いらっしゃいますが、ほとんどが規模の小さい診療所やクリニック。地域医療を支えるドクターであり、同時に小規模事業の経営者です。もちろん徹底したウイルス対策を講じざるを得ないのですが、そのための設備投資や感染者が出た場合の対処のことを考えると、中小の事業主にとってこれは大きな負担にもなります。感染拡大が深刻になり始めた時点ではそういった不安を抱えながら、医療従事者の方たちは文字通り孤軍奮闘で頑張っている状況でした。
──その時点では、中小企業にとって経営資金の手立てはどんなものがあったのでしょうか。
緊急事態宣言は国としても初めてのことでしたが、幸い政策金融公庫や信用保証協会などが早めのアナウンスをして、公的な制度融資を機能させていました。株価も含め対応は早かった。しかし、手続き面で言えば最初のころは窓口で申し込んでから実際にお金が届くまでに2カ月待ちというところもありました。公庫や協会の担当者のデスクには申請書類が積み上がり、処理しきれないというような状態だったと聞いています。
業界で言うと独立行政法人福祉医療機構の対応は、医療機関向けということもあり、融資判断や手続きの簡便性から迅速で利用しやすかったですね。

運転資金は確保しているが事業や売上が戻ってこない
──5月、6月はいったん状況が落ち着いたように見えましたが、7月に入ると再び感染者が増えてきて、8月上旬にはピークを迎えます。いわゆる“第2波”の到来ですが、この頃の中小企業の経営はどんな感じだったのでしょうか。
公的な給付金や助成金だけでなく、保証協会付きの金融機関融資も多かったこともあり、手元には十分な資金がある企業が多い印象です。コロナ前にきちんと利益を出していた会社は、十分すぎる資金調達を行えている、または行える状況にあると思います。ただ、コロナ前から赤字であった会社やそもそも長期的な事業継続をどうするか考えていた事業者は、今回のコロナを理由に廃業を選ぶケースを私も見ています。
企業が、資金調達をできたとして、問題は今後の事業や売上が読めないこと。調達した資金の投下先がわからない。また、単月収支が黒字であればいいですが、そうでない場合、このままでは手元の資金もいずれ底をついてしまいます。もともと借入金ですから、返済が不能になるという事態も見ておかなければなりません。
金融機関は貸付先企業の状態をきちんと指標化して融資の判断をしています。例えば債務償還年数ですね。通常は7年とか10年とかのスパンで見ている。この間に返済能力があるかどうかが融資の基準になります。ところが、いまは信用保証協会が100%債務保証をしてくれているので、銀行も安心して貸し出せているわけです。ただ、現状、出口が分からないという意味で、企業は早期の財務改善を図っていく必要があります。余談ですが、金融機関の与信システムというのはよくできていて、分かりやすい話、住宅ローンの審査が通りやすい業種や属性は、今回のコロナ禍でも、短期的には安定度合いは高かったと思います。
資金はあるが売上がついてこないという事態に、経営者たちもいろいろ策を練らなければなりません。最近、私どもに寄せられる相談で多いのは、売上の大幅な増加は見込めない中で、事業のスケールを見直したい、業務フローや管理部門の効率化を図りたい、中長期的な財務戦略を考えたい、といった筋肉質な経営体制への移行です。また、コロナ禍で影響を受けている企業は、なんとか雇用調整金や銀行融資で収支をつないでいる間に、損益分岐点の引下げと新しい商品・サービス・領域へのチャレンジをし、持続性を高めていこうとしています。
労務面については、ただでさえ難しい中小企業の人材確保が輪をかけて難しくなりました。4月以降は、中長期的に現状のコロナ環境が続くのではという認識が広がり、夏以降は、企業と従業員の関係が変わってしまった。経営者からも人員や組織の見直しに関する相談は増えました。
売上の面でいうと、コロナ禍の状況では積極的な販売活動をしても大幅な売上増は見込めないと割切り、粗利率の高い商品に絞ったり、受注フローの変更、提供時間の制限、あるいはこれまでの営業活動や広告宣伝を停止や変更するなど、コロナ禍を利用した実証実験にチャレンジする経営者もいます。この先は、こうした実践結果をもとに、ここで得られた新しいノウハウを企業の営業戦略に落とし込んでいく時期になるだろうと思います。
中小企業同士の新たなM&Aが進む可能性も
──コロナ禍の影響で逆に売上が伸びたという業種・業態もあるようですね。
ケース別にいくつかあると思います。
1つ目は、コロナ需要増加に伴うもの。わかりやすい話、ニーズが増えたものとして消毒液やマスクの製造業、ビル除染事業、配送事業などがあります。
2つ目は、働き方の変化によるもの。リモートワークにより人の動くエリアや時間が変わったことによる消費増です。郊外にある喫茶・飲食店や、DIYショップやクリニックなどがそれです。昼間、勤務先に通勤していた人が自宅周辺にいることによって、自宅周りの経済圏が活性化しました。
3つ目は、時期ずれによるもの。4月、5月で新規が止まっていたものが動き出した結果、前年比で売上増加しているものです。
4つ目は、政策によるもの。GoToを筆頭に政策的な資金供給によるものです。サプライチェーン補助金など設備投資による大型の補助金制度もありました。
中小企業の経営者の皆様はマクロの動きと自社がビジネスをするミクロの動きをキチンと理解されている。中長期的なマクロの視点と短期的なミクロの視点をいずれも理解しながら動いています。
コロナ禍が企業活動に与える影響でもう一つ着目したいのは、企業同士の合従連衡や新たな集約化が一気に加速するかもしれないということです。中小企業では高度成長期に創業した企業がいま事業承継のタイミングを迎えていますが、3年かけてやろうとしていたことを加速してやる必要が出てきたと実感されました。例えば私自身、4月~5月には遺言のお手伝いをする機会が増えました。コロナ感染した場合、隔離され最悪家族とも会えないまま、2週間で亡くなってしまう。そんな報道を見て、自分自身のことに置き換えて対応を考えられた。会社のこと、家族のこと、自身の人生のこと、コロナ前とは違ったリアルな視点でのご相談が増えました。
今後も事業の継続・統廃合や、M&Aの動きがさらに加速度的に進んでいくものと考えます。
──どんな方法を使っても危機を乗り越えようとする、ある意味、企業の本能に近いものがありますね。
この数十年の歴史でみても、リーマンショックや大震災がある度に、それを乗り越えた企業はより筋肉質になって復活を遂げてきました。そういう企業はその後の外部環境の回復段階で大きく飛躍する準備をしています。ただ、この冬の“第3波”がどの程度のものかわからないし、実体経済の回復状況なども見通せないため、来年春までは大きな投資は様子見、とされている経営者の方が多いです。
モノに稼がせる不動産戦略
アセットの組換えで本業をカバー
──ところで、こうした経営危機に際して、中小企業は不動産という資産をどう考えればよいのでしょう。
事業で稼いだ利益をどこに投資するかはそれぞれの企業の戦略によりますが、対象として多いのはやはり不動産や設備ですね。これまで人が稼いでいたところを、今度はモノや仕組みで稼ぐようにしたいというのは誰もが考えること。不動産が本業の会社は別ですが、それ以外の一般の会社にとって不動産を持つことは、本業以外で稼ぐ仕組みをつくるということに他なりません。これは、昔から変わらない企業経営の手法の一つだと思います。
今回も、私どものお客さまの中には、コロナ禍の影響で不動産価格が下落したらそこに投資したいという経営者は少なくありません。ただ、実際には思うほどには不動産価格が下がっていないので、様子を見ているというのが現状だと思います。
もう一つ不動産について言えるのは、それは企業の信用を補完するものであるということです。例えば、東京・丸の内に本社を構えているといわれれば、それだけで人はその企業に一定の安心感を得るでしょう。特に信用をベースにビジネスを行っている企業の場合はそれが言えます。
むろん最近は、リモートワークの進展で大きなオフィスは要らないという意見もありますが、それはあくまでも勤務場所としての不動産の話。たとえリモートワークが進んでも、本社はブランド価値の高いところに置いたままにした方が、企業価値が高まるというのが実際のところだと思います。現実に、対面で行うセミナーやイベントなどが可能になれば、都心の一等地でやったほうが人も集まりやすい傾向があります。
──不動産と言っても、どのような不動産に投資するかはさまざまな選択肢がありますね。
不動産投資は確かに世相を反映するものでもあります。バブルの頃は多くの会社が、社宅や別荘地、ゴルフ会員権などを保有していました。今となれば、それらは不良資産になっているものもあるかもしれませんが、当時は福利厚生や営業活動の面からも最適な事業投資対象だったのです。だからこそ、投資にあたっては世の中のトレンドに敏感であったほうがいいと思います。
言葉を換えれば、アセットの組み替えを定期的にやったほうがいいということです。一般の会社にとって不動産は損益計算書(P/L)ではなく、貸借対照表(B/S)に表示される資産です。余った現預金を不動産に変えるだけで、B/Sは改善し、それが株価にも影響することがありうる。その意味で不動産はB/S戦略の要にあるもので、早め早めに動かしていくことが重要になります。もちろん、そこは不動産専門のコンサルタントやソリューションを提供する信頼できる企業と相談することも重要です。
しかも上手に不動産を活用すれば、賃貸収入など本業をカバーする定期的な収益をそこから得ることも可能になります。本業と不動産の双方をうまくバランスを取りながら投資戦略を組みたてることが大切だと思います。
──不動産投資にもトレンドがあるというお話でしたが、コロナ禍以降に顕著になると思われる変化はありますか。
不動産を利用する側からすると、保有から賃借というトレンドの変化があって、これはコロナ禍以降にますます強まるでしょう。誰から物件を借りても、質が同じであれば借り手の側はすぐに安いほうに乗り換え、そこに価値を感じられなくなったら別のものに移行してしまいます。
貸し手の側にとっては厳しい時代です。だからこそ、貸し手は不動産というコンテンツや周辺地域をたえず魅力のあるものに整備しておかないといけないわけです。単にハコを貸すのではなく、その中にあるコンテンツや周辺環境も含めて求められるものを提供する必要がある。そして、借り手のニーズに応じてコンテンツをたえず見直す、そしてそれを魅力的に発信するということが、これからますます求められてくると思います。

経営者と従業員の関係にも変化が訪れている
──不動産に関してだけではなく、あらゆる面で関係性の変化が見られるように思いますが。
確かに、会社と従業員の関係も変化が進んでいます。リモートワークが当たり前になることで、労務的な意味での場所と時間への制約が薄れ、評価にあたっては、結果や成果への比重が高くなってきました。つまり、給与や評価体系が、時間給的なものから成果主義的なものにシフトするわけです。これに加えて、これまでIT系など一部の業種に限られていた副業制度の相談が、他の中小企業でも増えてきています。
そうなってくると正社員、パート社員、派遣社員、業務委託社員などの境目がなくなってきます。会社にとって最大の固定費である人件費の変動費化が進む。変動費的に稼げる社員と、時間給的な感覚で仕事をする社員の二極化が進んでくると思います。欧米ほどではないにしても、ジョブ・ディスクリプションを厳密に行ってそれに対する寄与の度合いで評価するように、日本企業もならざるをえません。
このような中で、従業員の教育をどのようにしていくか、かつて会社は新卒を一括採用して教育を施して一人前に育てていた。しかし、今はそれができません。特に今年のように入社式も新人研修も対面で行うことが難しいとなると、若手社員はどこで仕事を覚えたらいいのか。
やはり若手といえども、自分で学習してスキルを磨いていくしかないのです。これはリモートワークを前提として仕事をしている人にも言えることです。会社から与えられる研修メニューを待っているだけでは、自分のスキルは向上しない、自分の力で自分を高めていかなければならないのです。
こういった意識と現場の変化が急速に進んでいることを、コロナ禍であらためて肌身で感じます。
とはいえ、それでも企業は人を通じてビジネスをしているのですから、経営者は考え方や環境の異なる社員をつなぎ止める目標や会社の向かう方向をより明確にしなければならないと思います。そのためにこそ経営者は社員に対してたえずメッセージを発信する必要があるわけです。特にオーナー経営者が多い中小企業ではそれが大切です。社長の言うことがたとえ昨日と今日で変わっても、状況はたえず変化しているのですから、メッセージの内容が変わっても気にする必要はありません。それでもトップが発信しつづけることが、社員のモチベーションを高め、組織を強くする上で絶対に必要だと思います。

Profile プロフィール
辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社
代表取締役社長
土橋 道章
1981年山梨県生まれ。税理士。青山学院大学経営学部経営学科卒業後、個人会計事務所を経て2009年より辻・本郷税理士法人入所。法人及び法人オーナーの会計・税務を中心に中小企業から上場企業まで関与。組織再編実行支援、連結納税導入支援、各種支援機構案件を含む事業再生、ハンズオンを実施。入所中、2016年明治大学グローバルビジネス研究科にてMBA取得。2017年より辻・本郷ビジネスコンサルティングに参画し、事業承継、M&Aを中心に業務従事し、2019年9月より同社代表取締役。その他、複数の顧問先役員に就任し、同世代の会社後継者の事業承継を実行支援。現在、4児の父。