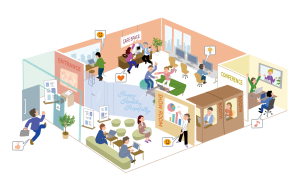これからの成長戦略に向けた企業の体質改善

目次
高度経済成長、バブルとその崩壊、失われた10年、IT産業の成長、リーマン・ショックなど、経済の浮き沈みを繰り返しながら、日本企業はそれに対応すべく体質改善を進めてきました。しかし今後も労働人口減少に伴う人材確保やAI、ロボットの活用、SDGsの推進など、取り組まなければならない課題が山積みです。経済構造や企業環境の変化を見越して、いま企業はどのような戦略を重視すべきなのか。事業構造改革や経営管理のプロフェッショナルである、アットストリームの大工舎宏氏に聞きました。
顧客ニーズを深掘りするサービスや
マネジメントにこそ人材投資を向けるべき
──今後予想される経済構造や企業環境の変化を見越して、いま企業はどのような戦略を重視すべきなのか。また、それに伴う人材投資をどう進めたらよいのか。本日はそのあたりを伺いたいと考えています。
私は総合コンサルティングファームのアーサーアンダーセンで10年にわたり、企業会計や経営管理などの分野のコンサルティングでキャリアを積み、2001年のアットストリーム設立後は、さらにクライアント企業の事業構造変革や組織変革の支援にも力を入れるようになりました。企業が今後あるべき姿を目指す中長期戦略の中に、KPI(重要業績評価指標)などの経営管理指標をどのように設定・活用していくかなど、マネジメントの仕組みづくりのお手伝いもしています。ですから今回は、経営管理の観点から企業戦略のお話をさせていただければと思います。
最近、「AIが発達すると人間が行う仕事がなくなってしまう」といったようなことが言われていますが、たしかに単純なオペレーション業務や定型の作業はAIやロボットに置き換わっていくことでしょう。こうした事態は、製造業などに限らず、システム開発や会計管理などの仕事でも発生すると考えられます。
しかし、お客様のニーズを把握し適切な提案をしていくような、そこに人が介在する仕事はそう簡単にはなくなりません。同じサービスでも定型的ではなく、相手の状況に臨機応変に対応したサービスは、あくまでも人が主体です。ビジネスの中で人間がそこに介在してサービスを改善していく状況は、決してなくなるものではありません。
このような時代に企業は、他社と何で差をつけるべきなのか。もちろん目の前のオペレーションにしっかりと取り組むのは当然ですが、その上で、個別ニーズへの対応や、気持ちのよいサービス、顧客体験といった、より高い付加価値をつけることが求められます。
人材投資という観点でいえば、これからはオペレーション作業よりもサービスやマネジメントにこそ人材投資を向けるべきでしょう。「決まったことをたくさんやる」ということではなく、その人やその会社でなければできない製品やサービスを生み出し、そのプロセスをしっかりと管理していく。こうしたマネジメントスキルを高めなければ、他社との違いを出していけない時代になっているのです。
──たしかに単純なデータ入力作業はロボットで置き換えることができると思います。しかし、そのデータをどう分析するのか、そこからお客様にどんな提案をしていくのか。それはやはり人間の仕事ですね。
その通りです。例えば、大手の金融機関は、FinTechなどの新技術の導入を急ぐ一方で、人材への投資も強めています。単純に取引量を増やすのではなく、お客様の事業を深く知り、経営陣とのコミュニケーションを通して経営課題を共有することで、いわば事業パートナーとして深くお客様の懐に入ることができる。そういった営業職の育成に注力するようになりました。これはAIではできない、人間同士のコミュニケーションです。相手も営業担当が懐に入ってくれば、「こういう人だったら、こういう話をしようか」という気持ちになります。今後企業が勝つための要素は、そこに残されているのです。

自社ならではの差別化要素を
明確にした企業戦略が、会社の競争力を高める
──不動産業界でも、製造業の設備投資で新規の工場や倉庫の用地を探してほしい、といったお客様からのニーズは多くあります。かつては、単に広くて安い物件があれば、という話が多かったのですが、最近は量から質への変換というか、立地要件の中に従業員の働きやすさや、周辺環境との調和といった要素も含まれるようになりました。設備投資のニーズがより高度になっていることを実感することができますが、これも事業会社の中に、ある種の意識変化が生まれているからだと思います。
設備や不動産の選び方にしても、企業は効率性だけを追い求めるのではなく、従業員にとっての利便性、働きやすさ、快適さなどの要素も重視すべきだといった考え方へと変化しています。こうした考えは、必ずしも財務面では最適化とは言えないかもしれません。しかし、いくら財務面で最適な倉庫を確保したとしても、そこで働く従業員が確保できなければ意味がないわけですから、良い職場環境をつくり、良い人材を確保するという考え方は、企業経営全体から見れば最適化につながります。
しかしこれらの課題を、当面確保すべき収益目標との間でどのようにバランスを取っていくか。近年は、これが経営者にとっての難しい仕事になっています。
──企業はそうした意識変化を、どのように数字で把握しているのでしょうか。これまでは企業評価の指標としてROA(総資産利益率)やROE(自己資本利益率)が一般的でしたが、提案営業強化のための人材育成に関わる費用対効果などは、なかなか数字には表れないものです。
提案営業の強化とそれに伴う人材育成などの取り組みをどのように評価するか。これは投資家、経営者の双方にとっての課題です。投資家からすれば、人材育成に対するお金の面での費用対効果がいつ出るのかという将来性が見えていないと、新しい事業への投資機会をも失ってしまうことがあります。
企業では、優秀な提案型人材が増えればお客様との距離が近くなり、企業価値や競争力が高まります。ですから経営者はまず、そうしたビジョンや中長期戦略を立案することが必要です。そして、そのビジョンや事業戦略を達成するためにいまこれだけの投資をする、これが他社と自社を差別化することになる——といったことをストーリーとして明示し「見える化」しなければなりません。企業の戦略マップを踏まえた上で、成功に導くための要因を投資家にしっかりと示すことが重要なのです。企業の戦略とそれを達成するためのストーリーが目に見えないままでは、投資家は適切な投資判断が出来かねます。
企業戦略は差別化戦略でもありますから、中期経営計画書を見たときに、同じ業種のA社とB社の違いが見えなければ、戦略とは呼べません。企業はそこに自社ならではのこだわりや、差別化要素を明確にしなければならないのです。
では、その差別化要素を可視化するためにはどうすればよいのでしょうか。
私がマネジメントの仕組みやKPIに落とし込むときには、自社の差別化要素が強化されたときに、社内外にどういうことが増えるのか。あるいはどういうことがなくなるのか。具体的な変化は何かを、クライアントと一緒に考えるようにしています。
しかし、ビジネスの教科書の中にその答えはありません。もし答えがあれば、それはすぐに真似されてしまい、結果的にその企業らしさではなくなってしまうからです。
例えば、提案営業の強化を進める時には、単純な提案機会増や受注増がKPIではありません。提案機会獲得件数の中でも、こちらからお客様の潜在的なニーズを発見して提案した機会の数や、提案営業にふさわしい内容で獲得できた新規案件の数を見るべきです。その会社のオリジナル製品がどれだけ売れたのかも重要です。そういった自社ならではのものを増やすことが、結果的にその会社の差別化要素を増やすことになり、会社の競争力を高めることになるのです。
──量から質への転換の時代に、大工舎さんの専門でもあるKPIマネジメントでも、指標の設定の仕方に変化が見られますか。
量よりも質、そして他社との差別化が求められる時代となり、マネジメント指標も多様化しています。最近では単なる財務目標だけでなく、企業ビジョンや社会的責任を意識し、SDGsやESGといった要素をKPIに設定する企業が増えています。例えば中小企業庁が全国の中堅・中小企業の中から経済的・社会的に優れた企業を表彰する「グッドカンパニー」をKPIにする企業もあります。地域に貢献し、従業員にとっても働きやすい会社だと社会から認められれば、採用にも有利に働きますから、人材採用難の時代には重要な取り組みだと思います。
地域の特色を明確にして
インバウンド・ニーズを呼び寄せる
──最近は、大都市経済と地域経済の構造の違いもよく指摘されるようになりました。単一のビジネスモデルが成立しにくい時代なのかもしれません。地域経済において企業はどう戦えばよいか。単純に規模を追うだけではない別の価値観もあるのではないか、そんなことを考えます。
例えば、ITやサービスのグローバル企業では、GAFAに代表される企業とどう戦うかが関心の的になっています。ビジネスモデルやテクノロジーで勝負して、グローバルスタンダードを構築し、勝者が市場を総取りするいわばゼロサムの競争です。しかし、何も全てのビジネスでこうしたゼロサム発想が必要なわけではありません。
地域経済においても、それぞれの地域でパイの取り合いは生じています。むろん、そこにも勝者と敗者は存在して、お客様のニーズをしっかりと捉えて自社の製品やサービスの改善を重ね、そこでお客様を掴むことが出来るかどうかが、勝敗の分かれ目になります。
地域ビジネスで重要なポイントは、「地域を一つのまとまりとして考え、地域の特色を明確にしてインバウンド客を呼び寄せること」です。ここで言うインバウンドは必ずしも外国人観光客だけを意味しているのではなく、例えば、福岡県の企業が福岡県にいながらにして全国のビジネスニーズに応えるという意味合いも含んでいます。
また、他の地域からニーズを集める一方で、「豊かな人との触れあいがあって、高齢者も安心して暮らせるなど、その地域にしかないような世界を自己完結的に実現すること」も地域が潤い、ローカル企業が成長する上で重要です。
今はワンクリックでどこにいてもほとんどのモノが買えるようになりましたが、人々の生活はモノだけで成り立っているわけではありません。やはり、地域の人間関係が豊かでないと生活の満足感は得られないものです。
こうした街づくりを担うのは行政かもしれないし、地域の老舗企業かもしれません。官民一体のスキームの中にローカル企業が関わり、地域の特色をつくっていくことも十分考えられます。地域経済で企業が勝つための成長戦略には、その地域ならではの独自性やコミュニティのあり方を考えるという視点が大切です。

不動産専門サービス企業も、
地域のハブになることで力を発揮できる
──地域経済を活性化させるという意味では、お金の流れを担う、地域の金融機関が果たす役割も重要ですね。
地方銀行も変わりつつあります。これまでのようにお客様を回って預金を集め、融資するというビジネスモデルでは収益が成り立たなくなってきました。そこで先ほど挙げた金融機関の例と同様に事業構造を転換し、企業のビジネスパートナーとして、その会社の困っていることをまるごと解決する。いわば、課題共有型のビジネスへの転換を強める金融機関が増えています。
もちろん、なかには金融機関だけで解決できない課題もあるでしょう。例えば、資金需要の話を聞きに行ったら、物流拠点増設や幹部人材育成の相談を受けるなど。これらは本来、金融機関の仕事ではないのですが、不動産企業や人材育成コンサルティングと提携することで課題を解決することが可能です。つまり地方の金融機関が、ローカル企業のニーズに応えるための“ハブ”になるわけです。
その前提には、先にもお話したように、単なる御用聞き営業ではなく、経営者が困っている真の課題を聞き出すスキルが一人ひとりの営業担当に求められます。だからこそ、そのような人材投資を進めていく必要があるのです。
──「地域のハブになる」というお話は必ずしも金融機関だけでなく、一般の事業会社、例えば不動産企業でもできることです。不動産を一つの企業と相対で仲介・売買するだけでなく、狭い土地であれば他の地主さんにも話をして土地を広げ、それを開発して、高度な活用を促すといった提案ができます。当社も不動産ニーズからご相談を承り、ジョイントビジネスやM&Aなど、高度な経営課題克服のお手伝いもさせていただいています。
地域のハブとしての役割を果たせるのは不動産企業や金融機関だけではありません。地元企業が地域のために旗振り役になってその役割を果たすこともできます。大切なことは、ハブ機能を自社事業のコアに取り入れ、継続的に企画・実行し続けることです。その継続的な取り組みが、いまあらゆる企業、更には行政にも求められています。なぜなら、その地域のネットワークを活かしたハブ機能こそが、魅力的な街づくりやローカル企業の新たな成長戦略へとつながっていくからです。

Profile プロフィール
株式会社アットストリーム 代表取締役
大工舎 宏 (だいくや ひろし)
1991年アーサーアンダーセン入社後、1995年より経営コンサルティング業務に従事。 2001年に株式会社アットストリームを共同設立。現在、同社代表取締役。公認会計士。主な専門分野は、事業構造改革の企画・実行支援、KPIマネジメントなど各種経営管理制度の設計・導入支援。著書:「事業計画を実現するKPIマネジメントの実務」他、多数。