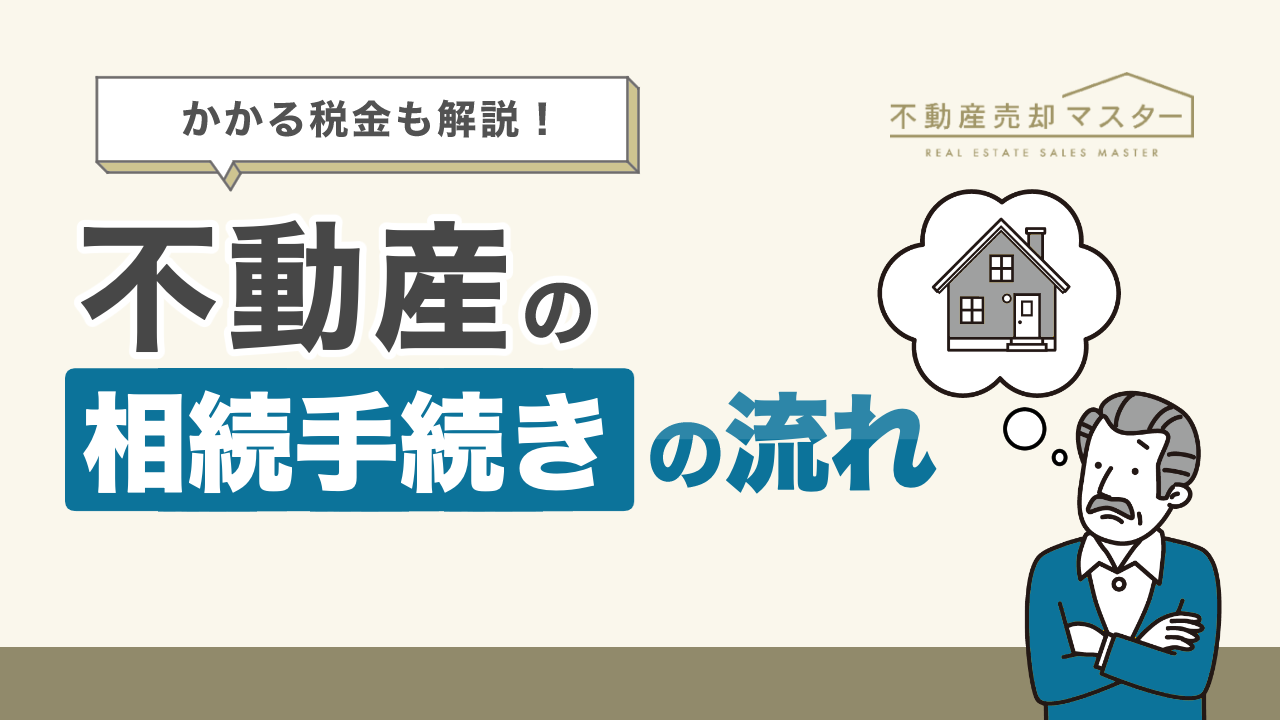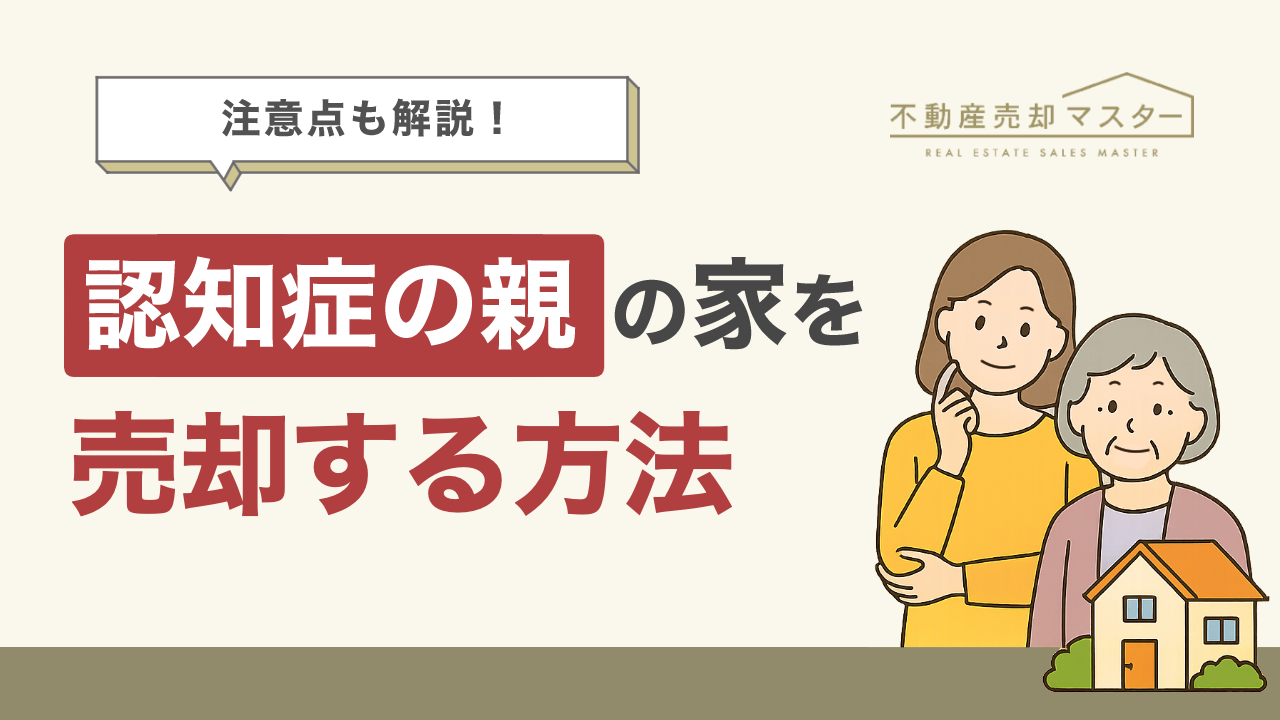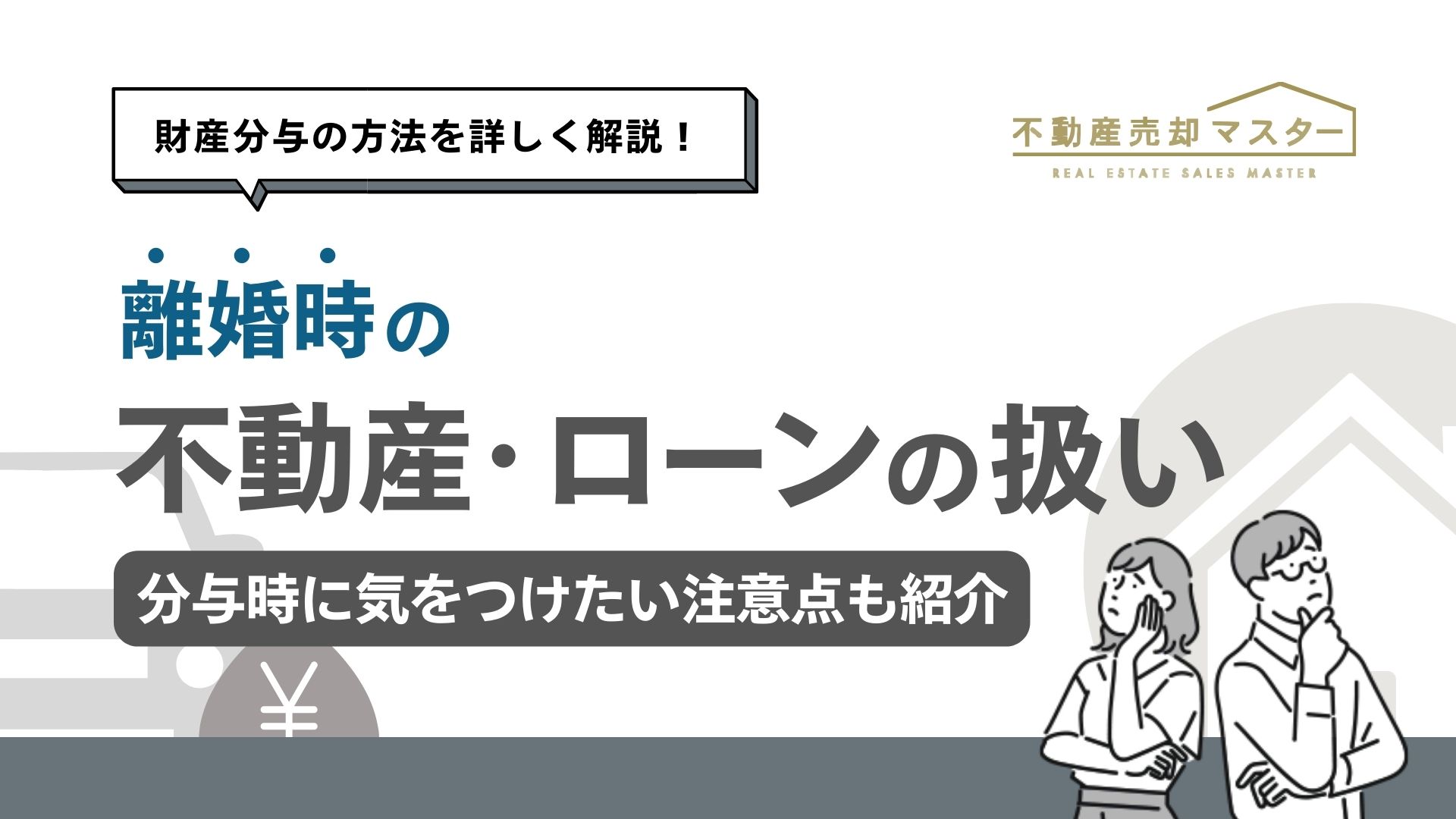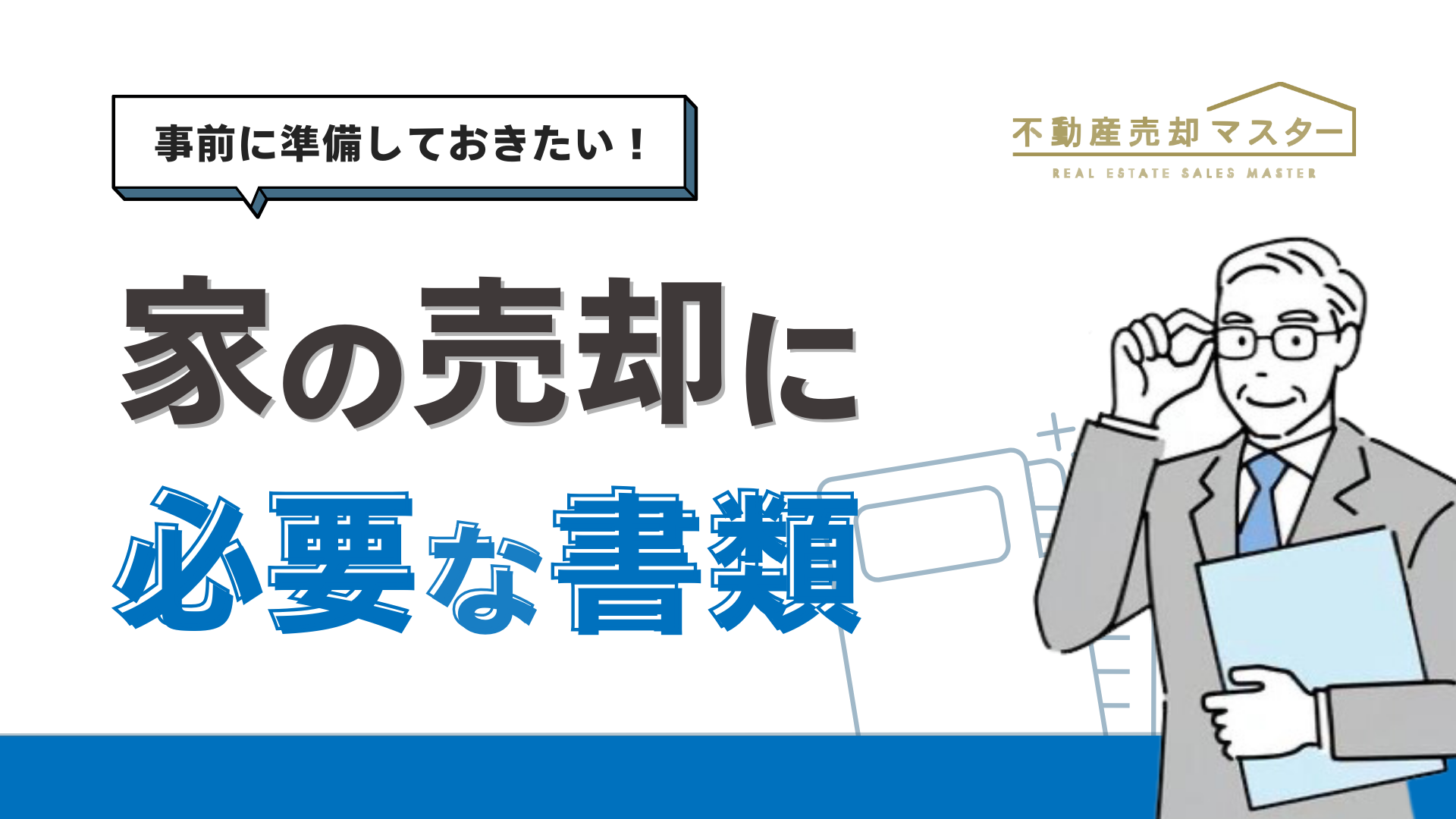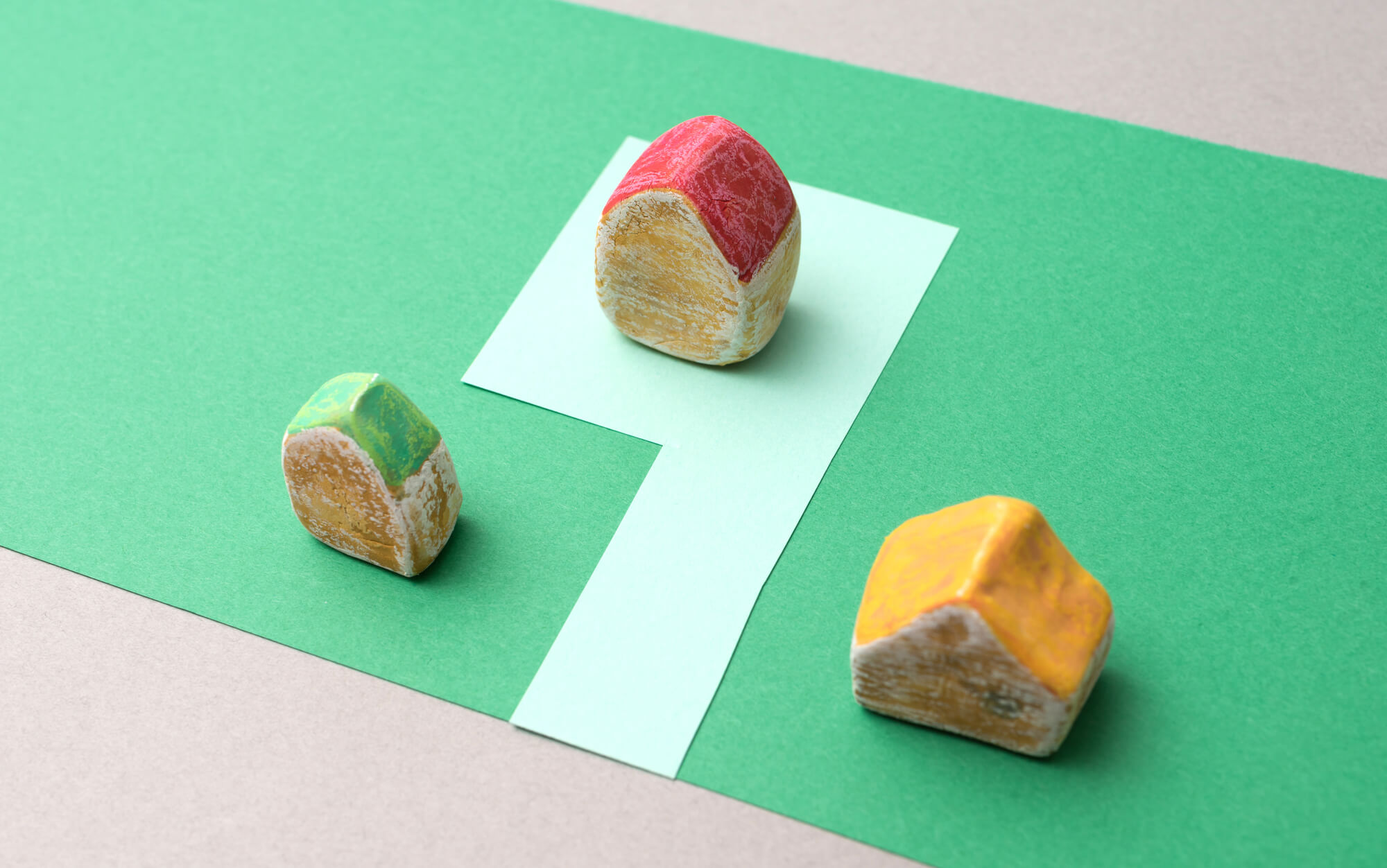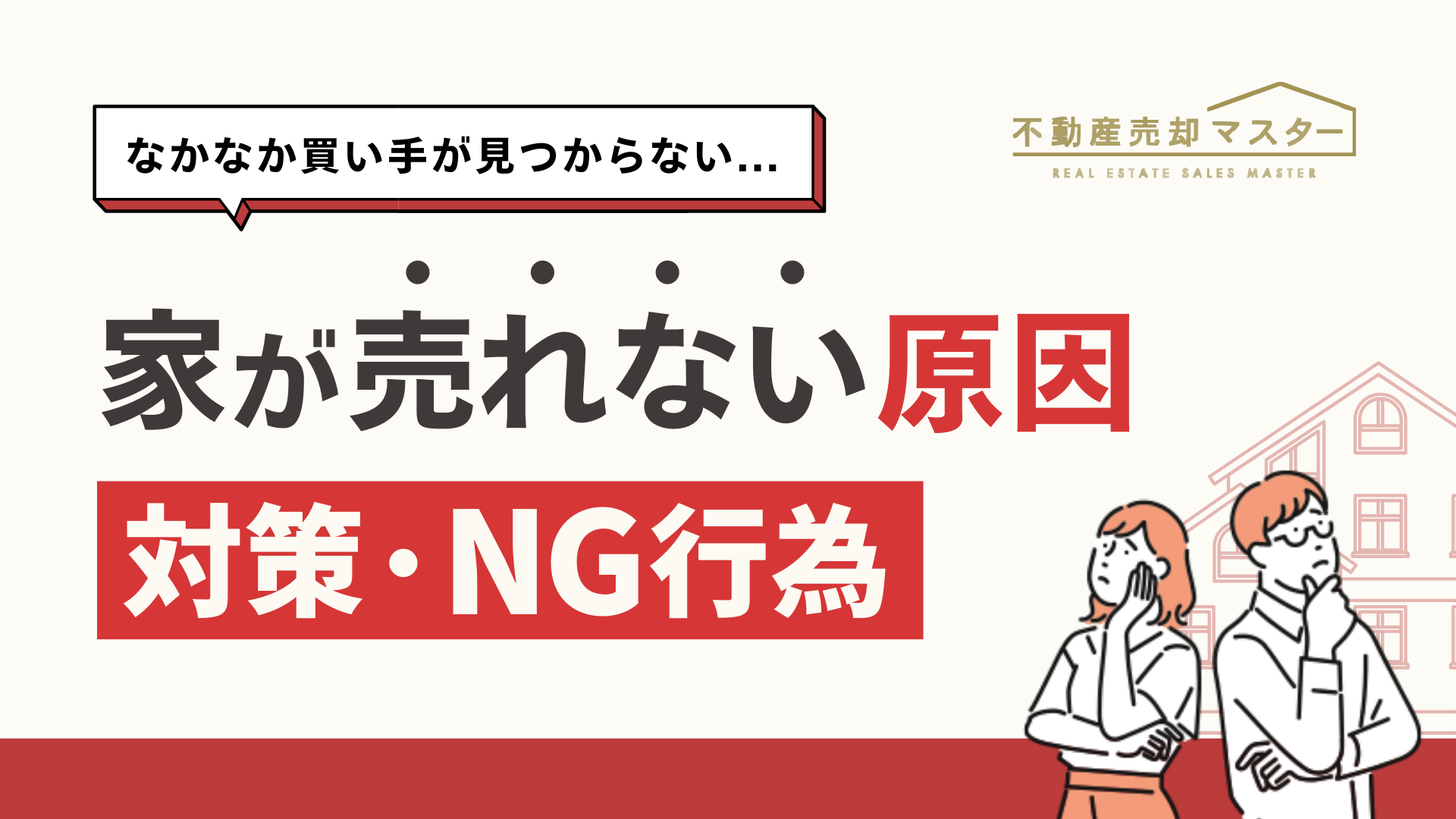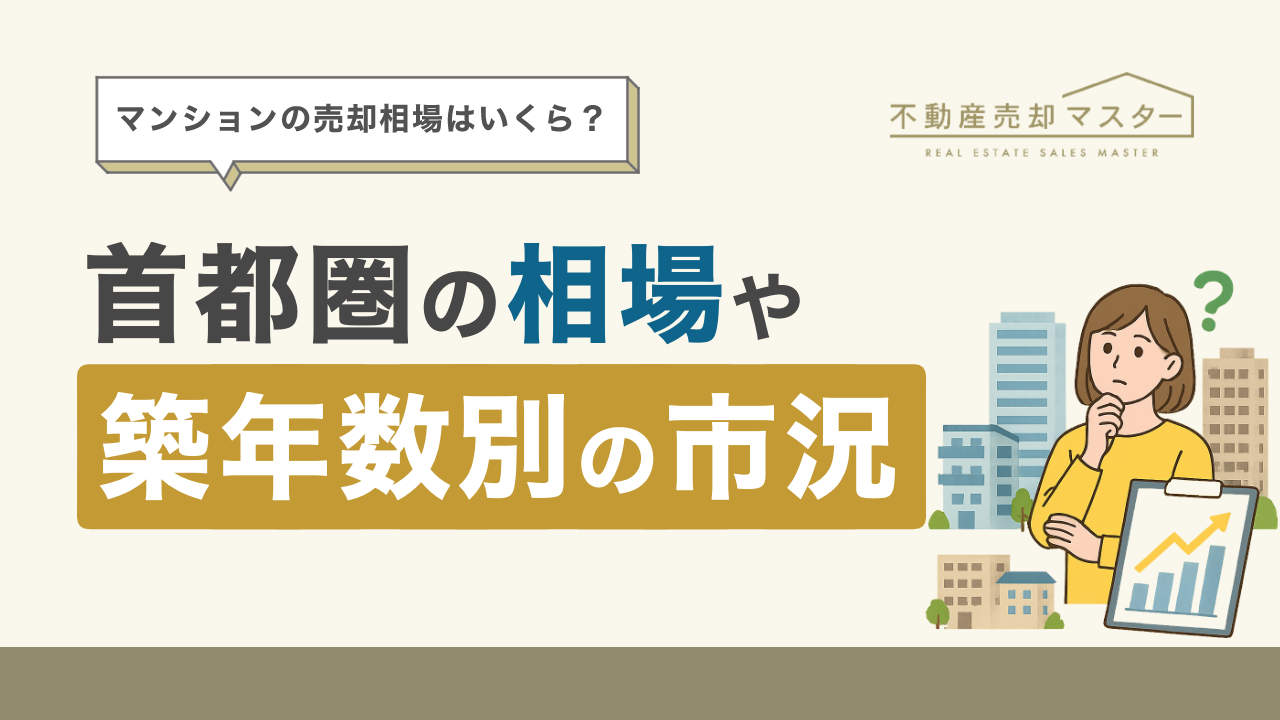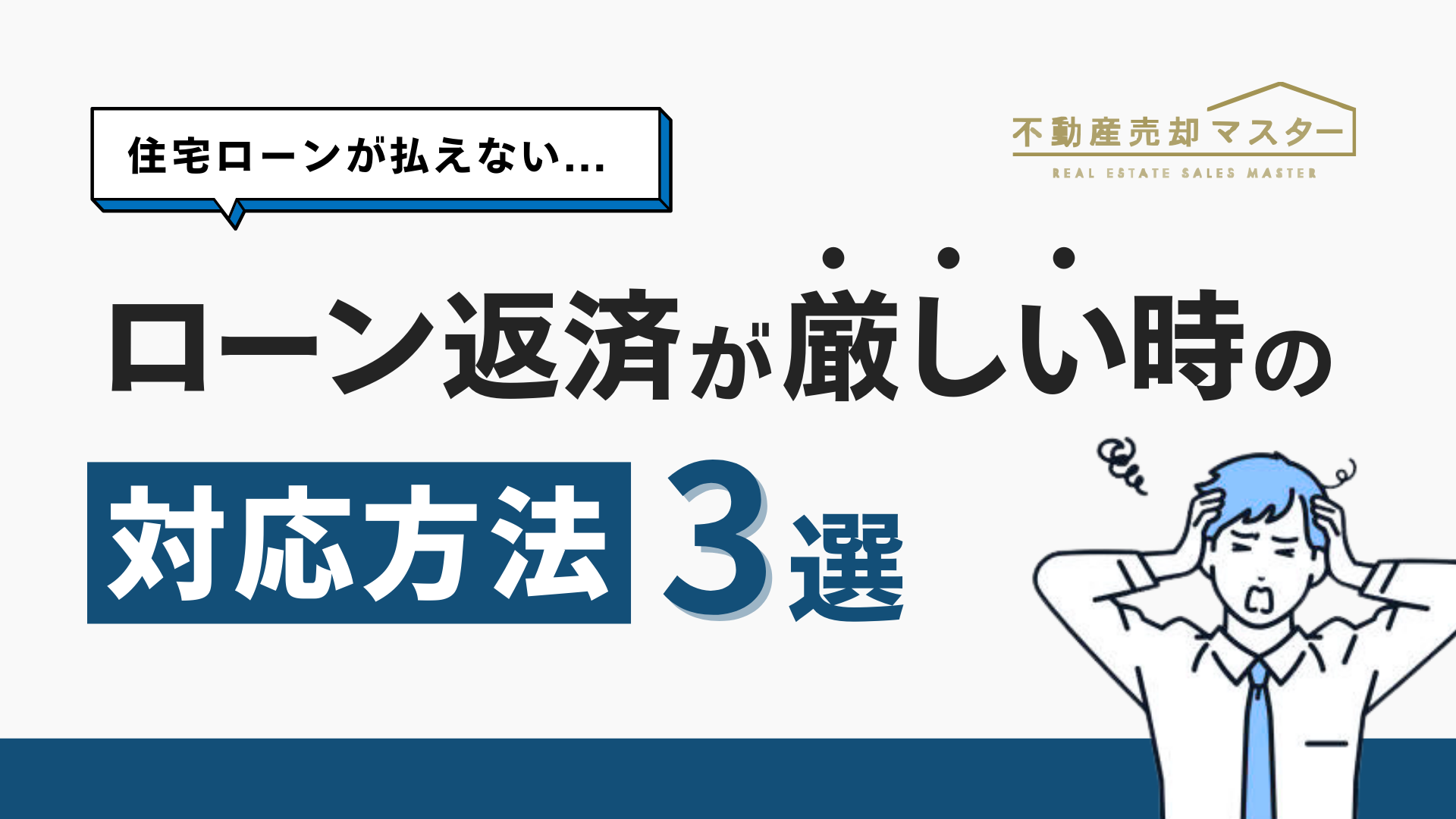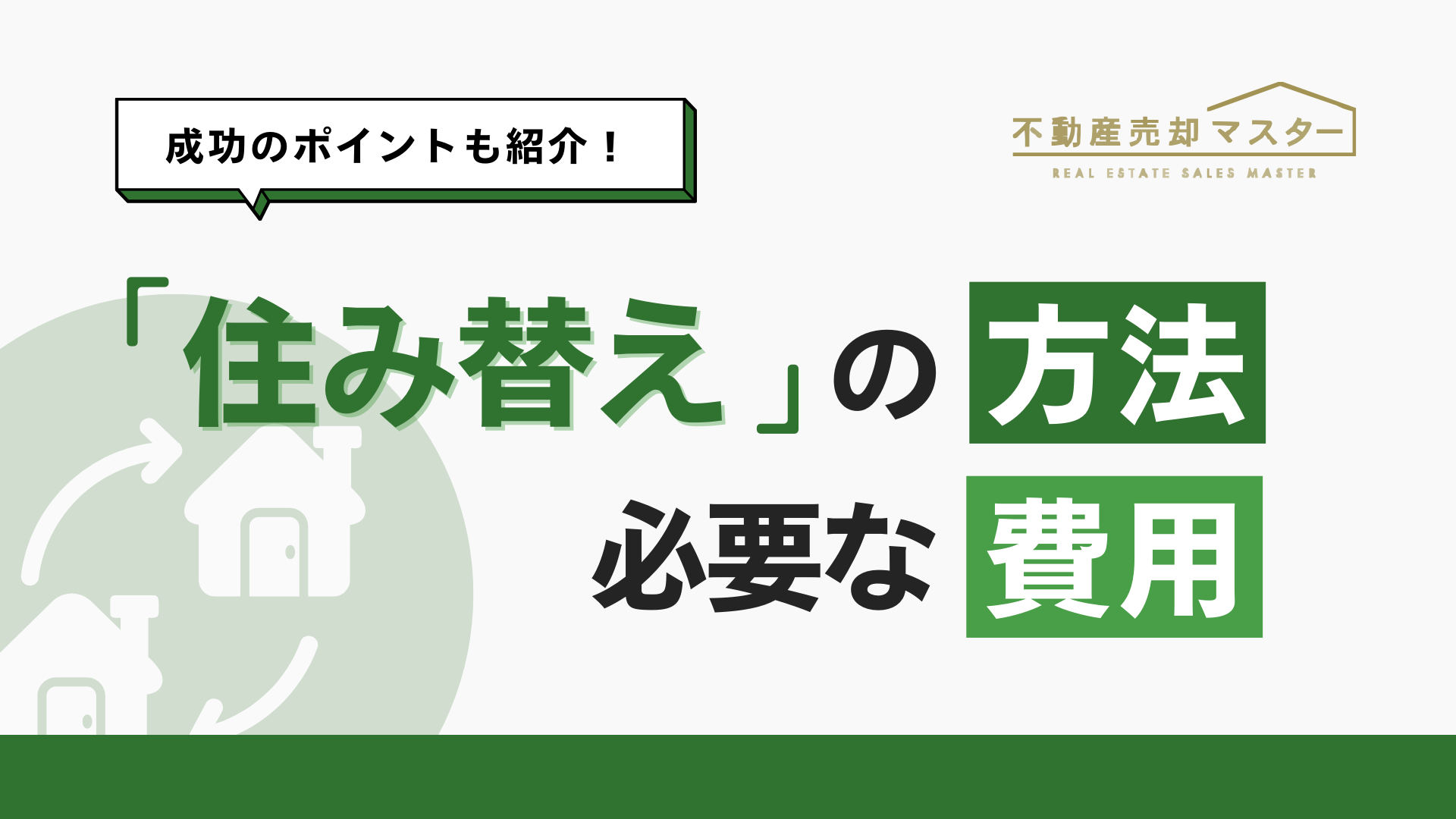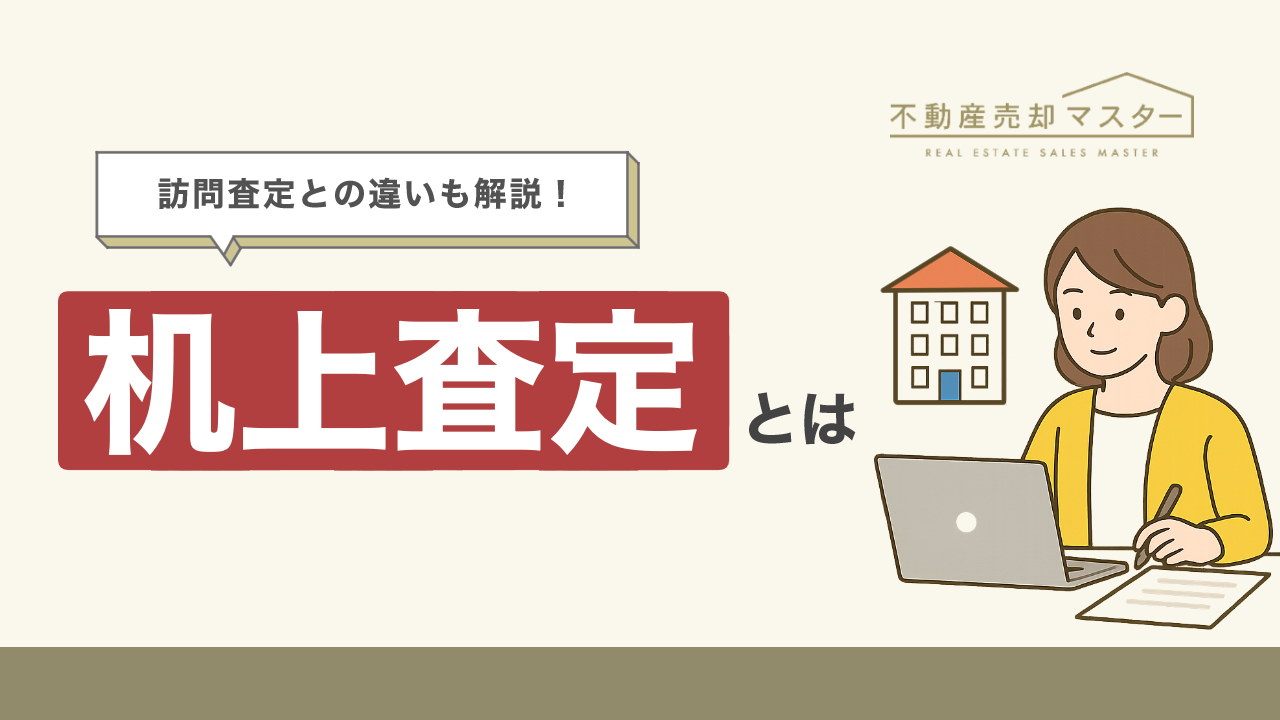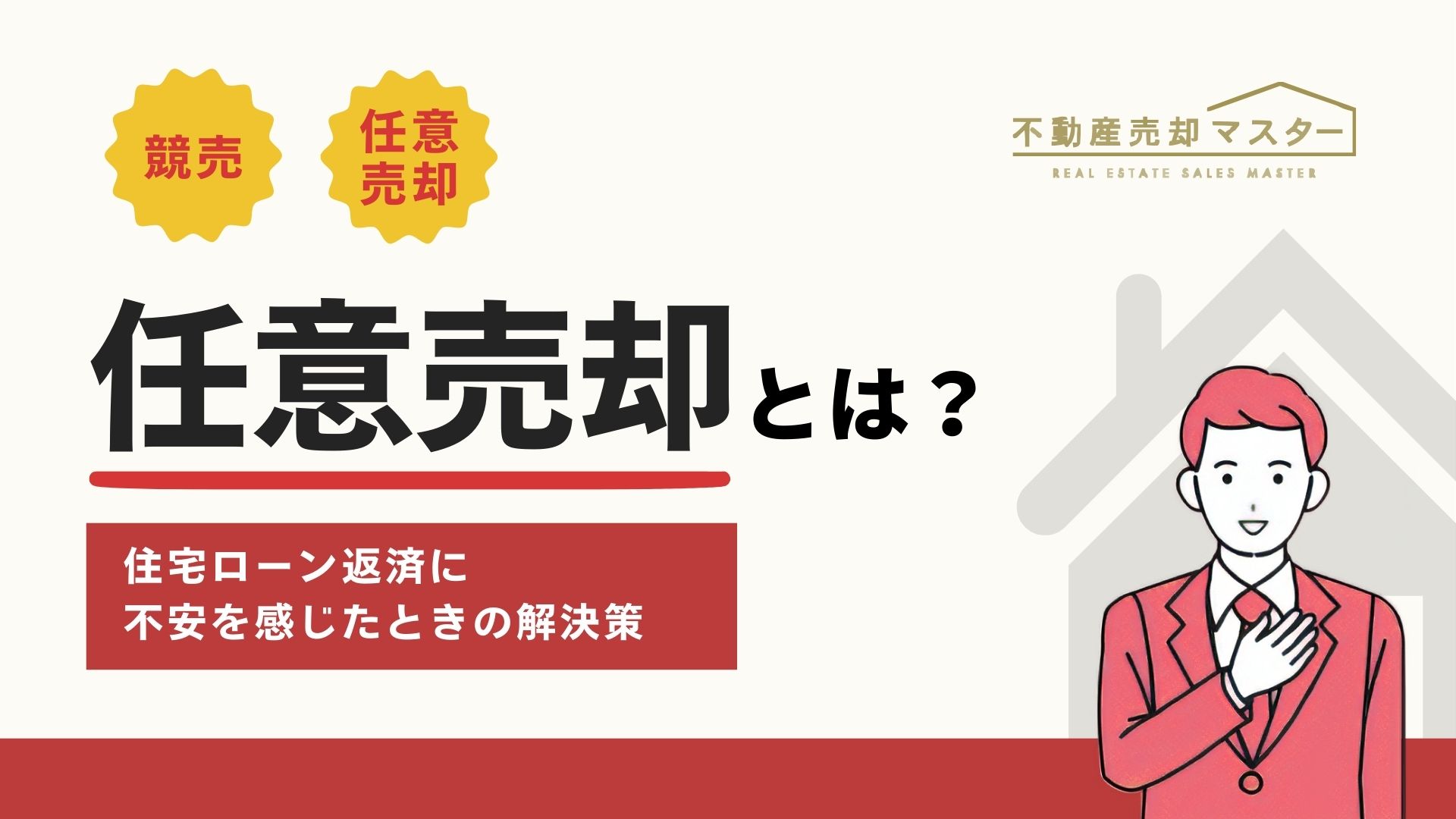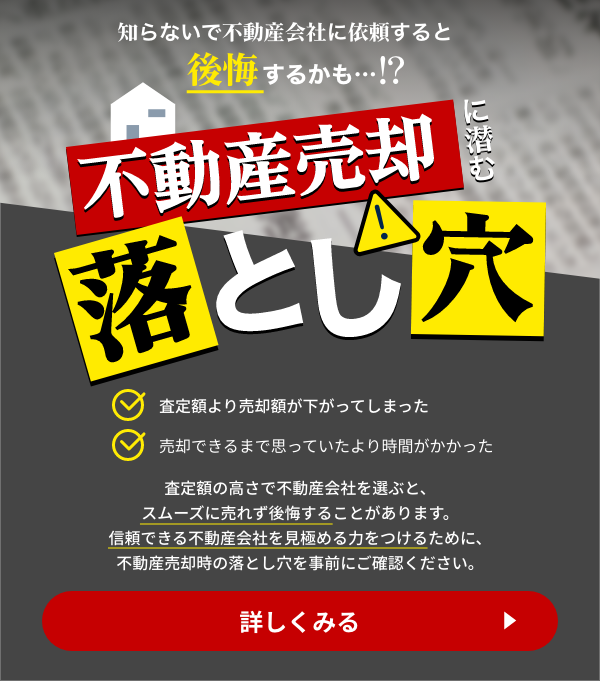土地の相続が発生したときには、遺言書の有無を確認する、遺産分割協議を開く、相続登記をおこなうなどさまざまな手続きが必要です。とくに相続税が発生する場合には、相続の開始から10カ月以内に申告・納付をおこなわなければならず、相続人や土地を含むすべての相続遺産の確定を迅速に進めなければなりません。
そこで今回は、土地を相続した際の手続きの一連の流れや必要な書類や費用、相続税の計算方法などを解説します。土地相続での相続税対策に利用できる特例や、土地の相続登記が必要なのかなどもご紹介します。
家を売りたくなったらタクシエ
三菱地所リアルエステートサービスが
あなたのエリアで実績の多い不動産会社をご紹介!
チャットで完結OK!
しつこい営業電話はありません!
土地を相続した際の手続きの流れ
まずは、土地を相続したときにどのような手続きが必要なのか、流れを確認しておきましょう。土地相続の手続きは、以下のステップを踏むのが一般的です。
それぞれどのようなことをおこなうのか、順番に確認しましょう。
STEP1:遺言書の有無を確認する
最初に、被相続人(亡くなった方)が遺言書を残しているかどうかを確認します。
遺言書が存在する場合、その内容に従うことが重要です。しかし、遺言書がないと思って手続きを進めてしまうと、後で遺言書が見つかった場合、手続きを最初からやり直すことになります。そのため、被相続人の自宅や公証役場で公正証書遺言が残されていないかを確認することが大切です。公正証書遺言は、公証人が立会いのもとに作成するため、遺言書の信頼性が高く、遺言による紛争を防止するためにも推奨されています。
STEP2:法定相続人と土地を含む相続遺産を確定する
遺言書を探すと同時に、法定相続人の確定も行いましょう。相続人が配偶者と子だけの場合はシンプルですが、配偶者のみで被相続人の子や親兄弟がすでに亡くなっている場合などは、甥姪にまで相続範囲が広がります。
また思わぬ親族関係があとから発覚すると、相続手続きをやり直すなどのトラブルになりかねないため、被相続人の戸籍謄本を出生までさかのぼり、慎重に法定相続人を確定しましょう。
同時に、土地を含めた相続遺産の調査・確定も行います。遺産は土地・建物などの不動産や預貯金といったプラスの資産だけでなく、借入金などマイナスの資産も洗い出します。
マイナスの資産が多い場合、相続放棄を検討する相続人が現れることがあります。相続放棄の期限は相続を知った時から3カ月とされているため、遺産の確定作業は早めに進めましょう。
STEP3:相続税がかかるか確認する
相続財産総額から基礎控除分や負債を差し引いて、相続税が発生するかどうかを調べましょう。相続税は相続が発生してから10カ月が期限となるため、早めに確認することが重要です。
土地に関しては、相続税路線価を基に評価する「路線価方式」や、路線価がないエリアでは固定資産税評価額を基に評価する「倍率方式」で評価額を算出します。
土地の査定を受け時価を確認しておく
土地については、相続税評価額とあわせ、不動産会社の査定を受けて時価を確認しておくことが重要です。
相続税評価額は時価よりも低いのが一般的なので、実際にどう分配するかを考えるときには時価で評価しないと、後々トラブルになる恐れがあるためです。例えば土地を相続した人があとになって高額で売却した場合「高く売れると知っていたら自分が土地を相続すればよかった」と言いだす相続人があらわれる可能性が考えられます。
土地は個別性が高いため、査定を受ける際には、誰もが納得できる明確な根拠を示せるよう、エリアの土地相場に詳しい仲介担当者に依頼することが重要です。仲介担当者の実績を確認したい場合は、担当者と直接マッチングできる紹介サービスを利用することがおすすめです。
例えば 三菱地所グループが運営するTAQSIE(タクシエ)なら、物件情報を登録すると、そのエリアで実績が豊富なエージェントが自動でマッチングされるので便利です。プロフィールや実績などを確認してから相談相手を選べるので、ぜひ利用をご検討ください。
STEP4:遺産分割協議で土地の分配方法を話し合う
相続人が複数いる場合には、遺産を誰が、どのように相続するのかを決めるために「遺産分割協議」をおこないます。とくに土地は、現金のように簡単に分け合うことができません。相続人同士で話し合い、ほかの遺産も含めてどのように分配するかを決めましょう。
土地については、次の4つの分配方法が考えられます。
それぞれどのような分け方か、順番に解説します。
現物分割
「現物分割」は、土地や家など相続割合の通りに分けるのは簡単ではない遺産があるときに、相続人同士で話し合って誰がどの遺産を相続するのかを決める方法です。具体的には、「家は母」「土地は長男」「現金は長女」など、遺産を現物のまま分け合います。
なお広い土地であれば、土地を分筆して相続人それぞれの土地として登記する方法もあります。ただし分筆して面積が小さくなることにより、価値が下がるケースもあるので注意が必要です。分筆による現物分割を考える場合には、不動産会社に相談することをおすすめします。
換価分割
「換価分割」は、土地を売却して得られた代金を遺産として分配する方法で、相続財産の大半が土地であるようなケースや、今後土地を利用する予定がないケースで有効です。現金化してから分け合うので公平に分配できますが、売却の手間と時間がかかります。
また相続した土地の売却は、相続人全員の共有状態となっているため、全員が合意しないとおこなえません。1人でも反対者がいると売却はできないので、まずは合意形成に取り組みましょう。
相続した土地を売却する流れについては、こちらの記事をご覧ください。
相続した土地売却の実践マニュアル|流れや税金の目安、節税対策まで
代償分割
「代償分割」は、土地を1人が相続し、ほかの相続人に相続割合に応じた代償金を支払う方法です。土地を分筆したり売却したりする手間と時間が不要になりますが、土地を相続した人に代償金を支払うだけの資力が求められます。
また土地の評価でトラブルになる可能性もあります。土地を相続した人は評価額が低いほうが支払う代償金が少なくてすみますが、受け取る側は評価額が高いほうがより多くの代償金を受け取れるためです。代償分割では、誰もが納得感を得られる評価方法を決めることが重要になるでしょう。
共有分割
「共有分割」は、複数の相続人が土地を共有する形で分け合う方法で、相続人全員の名前で相続登記をおこないます。土地をどう分けるかが決まらないときに「とりあえず」で選ばれることが多い方法です。
しかし、共有分割は、将来土地を売りたくなったときに全員の同意が必要になるため、問題を先送りしているだけになりがちです。共有者が亡くなり、相続が発生するたびに名義人が増え続けるので、権利関係がどんどん複雑になってしまいます。そのため共有分割は、基本的には避けるのが無難です。
STEP5:遺産分割協議書を作成する
遺産分割協議で土地を含む遺産をどのように分け合うかが決まったら、取り決めた内容を記載した「遺産分割協議書」を作成します。遺産分割協議書には相続人全員が署名し、実印を押印します。
STEP6:相続登記をおこなう
土地の相続人が確定したら、法務局で被相続人から新しい相続人へ相続登記をおこない名義を変更します。相続登記に必要な書類やかかる費用は、土地の相続登記に必要な書類と費用をご覧ください。
なお換価分割で売却することに決まった場合も、相続登記が必要です。土地は名義人しか売却できず、被相続人から買主へと直接名義を変更することはできないためです。
相続人が多い場合は、代表者を決めて相続登記すると売却手続きがスムーズですが、相続人全員の名前で登記してもかまいません。遺産分割協議の際に話し合って決めましょう。
STEP7:相続税の申告・納付
土地を含む遺産の相続で相続税が発生する場合には、相続発生後10カ月以内に申告・納付をおこなう必要があります。相続税が高額で、土地の売却で得られる資金を充当する必要がある場合は、限られた時間しかないため早めに売却手続きを進めることが重要です。
土地の相続登記に必要な書類と費用
ここでは、土地の相続登記をする際に必要な書類とかかる費用、取得先などをご紹介します。
土地の相続登記に必要な書類
土地の相続登記には、以下のような書類が必要です。
| 書類名 |
内容 |
取得先 |
| 相続登記の申請書類 |
相続登記を申請するために法務局に提出する書類 |
法務局 |
| 被相続人の戸籍謄本および除籍謄本 |
出生から死亡までの連続したもの |
被相続人の本籍地の市町村役場 |
| 被相続人の本籍地が記載された住民票除票または戸籍の附票 |
戸籍に記載された被相続人と登記名義人が同じ人物であることを証明するための書類 |
被相続人の本籍地の市町村役場 |
| 相続人の戸籍謄抄本 |
相続人全員の現在の戸籍謄本または抄本 |
各相続人の本籍地の市町村役場 |
| 相続関係説明図 |
相続人の関係を示した図 |
ー |
| 土地を相続する人の住民票 |
土地を相続する人の現在の住所を証明するための書類 |
相続人が居住する市町村役場 |
| 遺産分割協議書 |
遺産分割協議で取り決めた内容を記し、相続人全員が署名・実印で捺印したもの |
ー |
| 相続人全員の印鑑証明書 |
遺産分割協議書に押印した印影が実印であることを証明するための書類 |
相続人が居住する市町村役場 |
| 代理人権限情報(委任状) |
司法書士などに申請を依頼する場合のみ必要 |
ー |
| 固定資産税納税通知書 |
登録免許税を計算するために必要 |
ー |
土地の相続登記にかかる費用
相続登記にかかる主な費用は、以下の2つです。
| 登録免許税 |
固定資産税評価額×0.4%
不動産の持分の価額が100万円以下では免税(対象期間:令和7年3月31日まで) |
| 司法書士報酬 |
相続登記を司法書士に依頼する場合にかかる費用
相場は5〜15万円 |
登録免許税は、相続登記をおこなう際に、申請書に収入印紙を貼付して納税します。相続登記は司法書士に依頼せず、自分でおこなうことも可能です。その場合、司法書士報酬は不要になります。
土地の相続で発生する相続税の計算方法
相続税は、土地だけではなく相続遺産全体にかかるため、土地を含めた遺産総額をもとに以下の手順で算出します。
①課税遺産総額を算出する
遺産総額から基礎控除分(3000万円+600万円×相続人の人数)と負債、葬式代金などを控除して、課税遺産総額を算出します。
②法定相続割合に応じた相続税総額を算出する
①で算出した課税遺産総額に、法定相続分をかけて各相続人が相続する課税遺産額を出し、さらに課税遺産額に応じた税率をかけあわせて相続税総額を算出します。
<法定相続割合の主な例>
| 配偶者の有無 |
相続人 |
法定相続分 |
| 配偶者がいる |
子がいる場合 |
配偶者 |
2分の1 |
| 子 |
2分の1(人数で分ける) |
| 子がいない場合 |
配偶者 |
3分の2 |
| 父母 |
3分の1(人数で分ける) |
| 子も父母もいない場合 |
配偶者 |
4分の3 |
| 兄弟姉妹 |
4分の1(人数で分ける) |
| 配偶者がいない |
子がいる場合 |
子 |
1分の1(人数で分ける) |
<相続税の速算表>
| 法定相続分に応ずる取得金額 |
税率 |
控除額 |
| 1,000万円以下 |
10% |
– |
| 1,000万円超〜3,000万円以下 |
15% |
50万円 |
| 3,000万円超〜5,000万円以下 |
20% |
200万円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 |
30% |
700万円 |
| 1億円円超〜2億円以下 |
40% |
1,700万円 |
③実際に遺産を取得した割合に応じて相続税額を按分する
②で算出した相続税総額に、各相続人が実際に遺産を取得した割合を乗じて按分します。
④控除額を差し引き、実際に納税する税額を算出する
③で算出した相続税額から控除額を差し引いた金額が、実際に納税する相続税額です。
相続税の出し方について詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
不動産相続税の基礎知識|計算方法と節税のコツ、関連費用を解説
土地相続で使える相続税の特例
土地を相続したときに、相続税を節税するために使える特例をご紹介します。
小規模宅地の特例
「小規模宅地の特例」は、一定の要件を満たしたときに、土地の相続税評価額が最大で80%減額できる制度です。
| 土地の種類 |
内容 |
上限面積 |
減額割合 |
| 特定居住用宅地 |
被相続人などが居住用にしていた宅地 |
330㎡ |
80% |
| 特定事業用宅地 |
被相続人などが事業用にしていた宅地(貸付事業をのぞく) |
400㎡ |
80% |
| 特定同族会社事業用宅地 |
特定同族会社の事業用にしていた宅地(貸付事業をのぞく) |
400㎡ |
80% |
| 貸付事業用宅地 |
被相続人などが貸し付け事業用(不動産貸し付け)にしていた宅地 |
200㎡ |
50% |
それぞれ適用される要件がありますが、ここでは特定居住用宅地を相続する場合の要件を確認しましょう。
【被相続人が暮らしていた宅地】
①配偶者
とくに要件はありません。
②被相続人と同居していた親族
相続税の申告期限まで住み続け、かつ所有していること
③被相続人と同居していない親族(家なき子)
・①②がいないこと
・相続開始時に日本で納税義務があり、日本国籍があること
・相続開始前3年以内に、自分や配偶者、3親等以内の親族などが所有する家に住んだことがないこと
・相続開始時から相続税の申告期限までその宅地を所有していること
【被相続人と生計を同じにしていた親族が暮らしていた宅地】
①配偶者
とくに要件はありません。
②被相続人と同居していた親族
相続開始前から相続税の申告期限まで住み続け、かつ所有していること
小規模宅地の特例について詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
土地相続税の基礎知識「税金はいくらかかる?」|計算方法と使える控除を解説
配偶者控除
「配偶者控除」は、配偶者の相続分について利用できる控除です。配偶者に按分された相続税のうち、
・1億6,000万円まで
・配偶者の法定相続分を超えない範囲
の金額が大きいほうを上限として、相続税が非課税となります。
土地の相続登記をしないとどうなる?
現在、相続登記は義務ではなく、実施しなくても罰則はないです。しかし、相続登記が行われないことにより、相続人が増え、土地の権利関係が複雑になり、社会問題化しています。特に、土地の所有者がわからないと、災害時に復旧や復興が難しくなることが問題です。
相続人としても、相続登記されていないといざ売却しようと思ってもできず、相続人が多くなればなるほど手続きは煩雑になってしまいます。このため2024年(令和6年)4月1日から、相続登記が義務化されることになりました。これは制度開始前に相続が発生しているケースも対象になるとされています。
相続が発生してから3年以内に登記しない場合、正当な理由がなければ、10万円以下の罰金が科される可能性があります。土地を相続した際には、問題が起こる前に、早めに相続登記を行いましょう。
まとめ
土地を相続するときには、相続税評価額を出すのとあわせ、不動産会社に査定を依頼して時価を知ることが大切です。相続税の評価額は時価よりも低くなるケースが多いため、相続税評価額にもとづき遺産の分配方法を決めてしまうと、後々トラブルになる可能性があるためです。
相続した土地の査定を受ける際には、対象となるエリアの不動産市況や開発予定などに詳しい仲介担当者に依頼すると、土地をどのように相続すればよいのか相談に乗ってもらえるのでおすすめです。土地相続は、そのまま相続する以外にも、分筆して分け合う、売却して現金化するなどさまざまな方法があります。エリアのニーズも考慮して、どのように土地を相続し、活用すればよいかを提案してもらうとよいでしょう。
なお相続が得意な担当者を選ぶときには、仲介担当者と直接マッチングされる紹介サービスを利用することをおすすめします。三菱地所グループが運営するタクシエでは、物件があるエリアで実績の豊富な担当者と自動マッチングされるので便利です。仲介担当者のプロフィールや実績を確認し、相続案件に強い担当者を見つけて相談できるので、ぜひ利用をご検討ください。