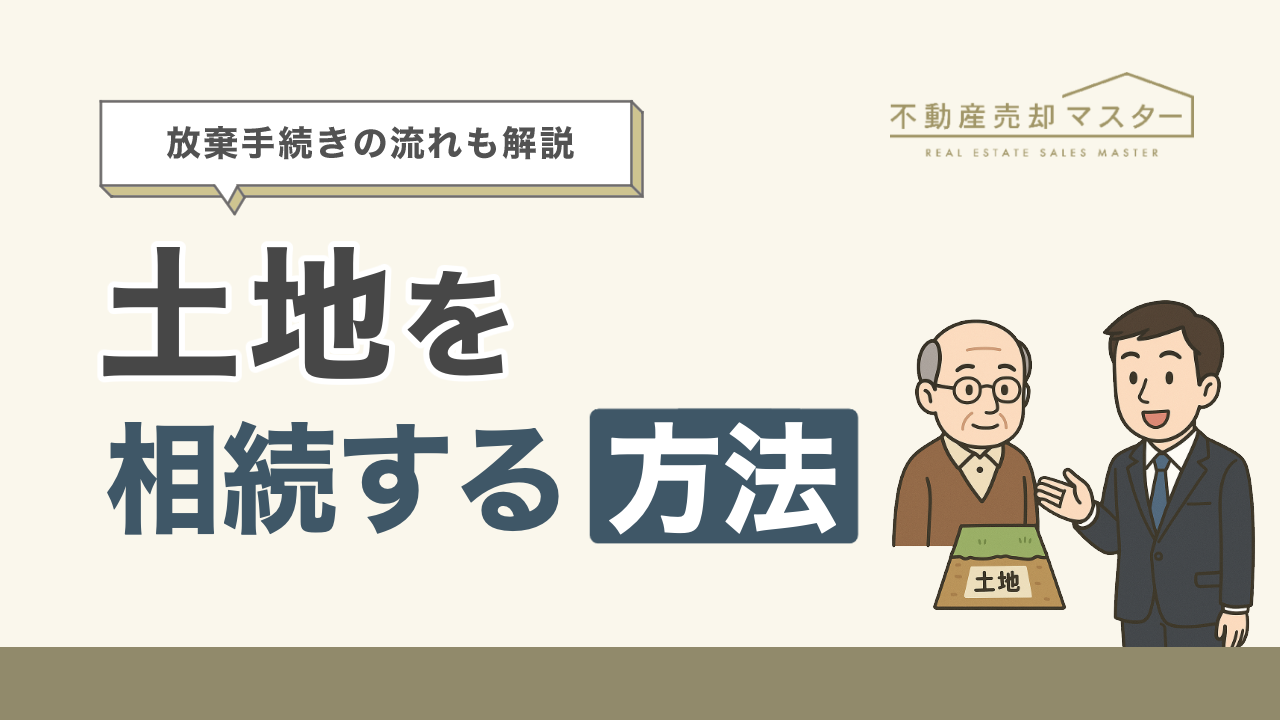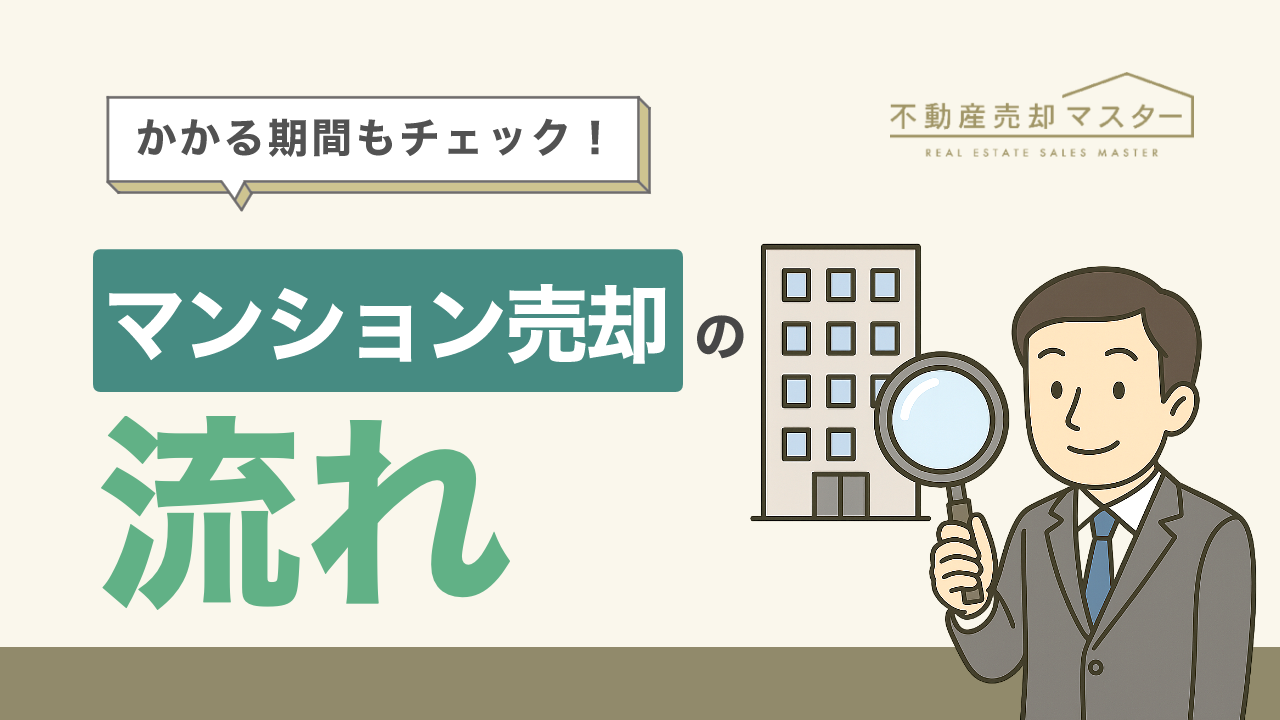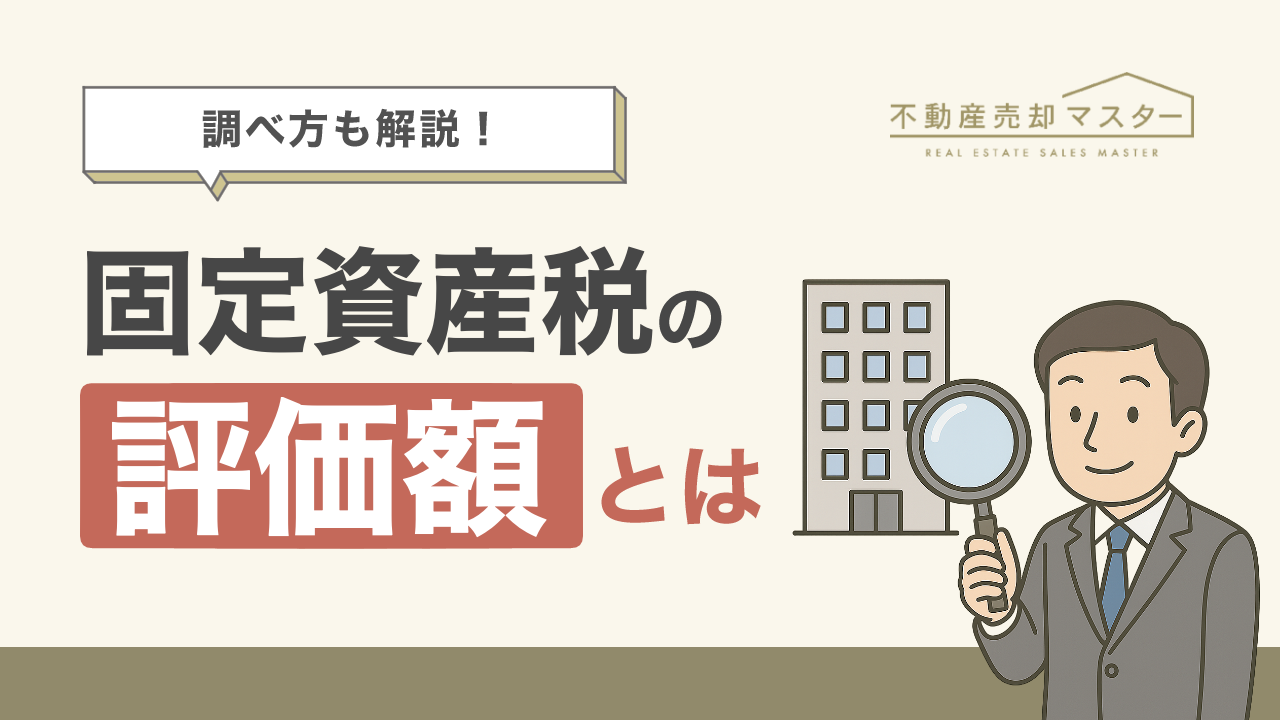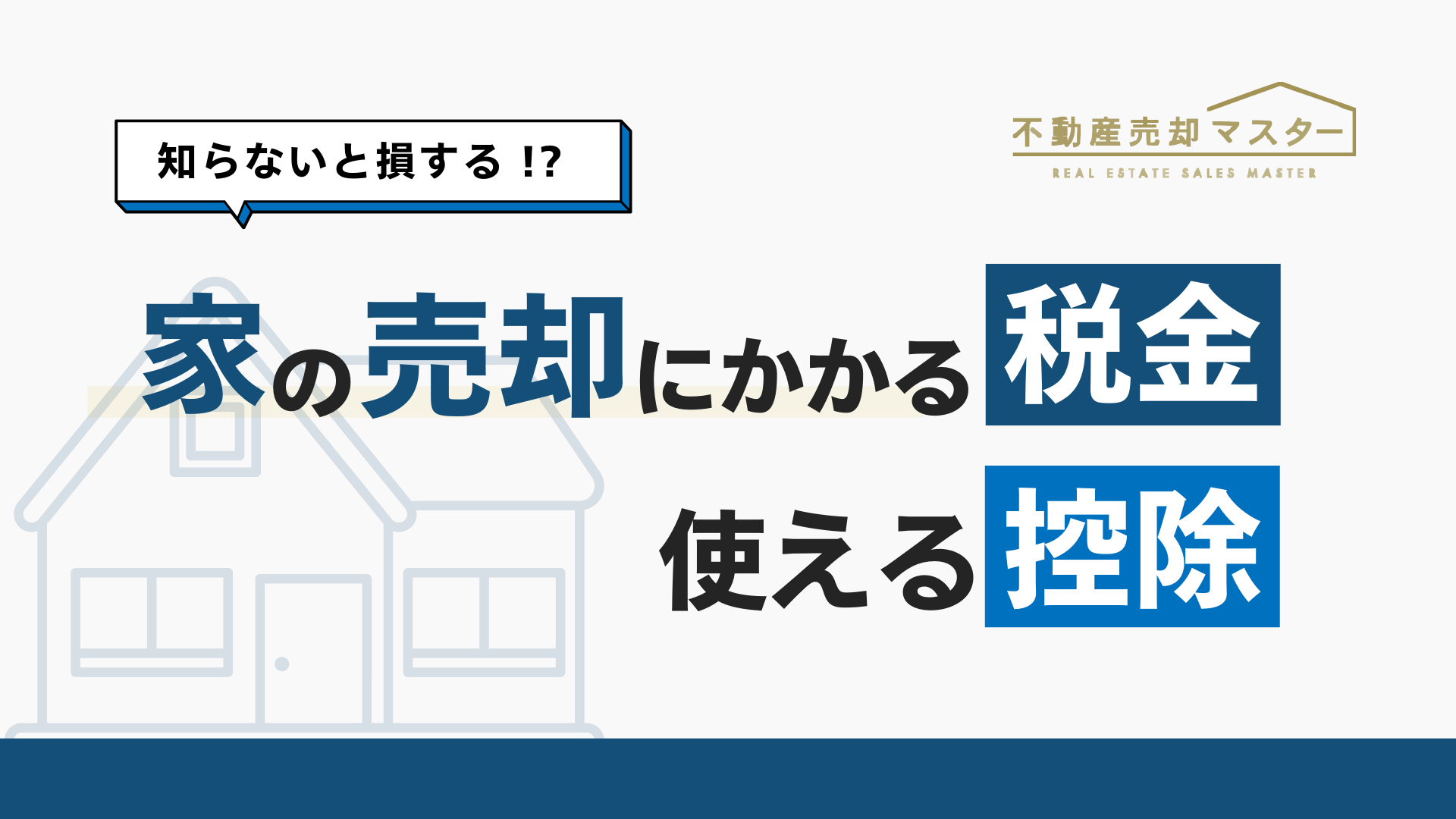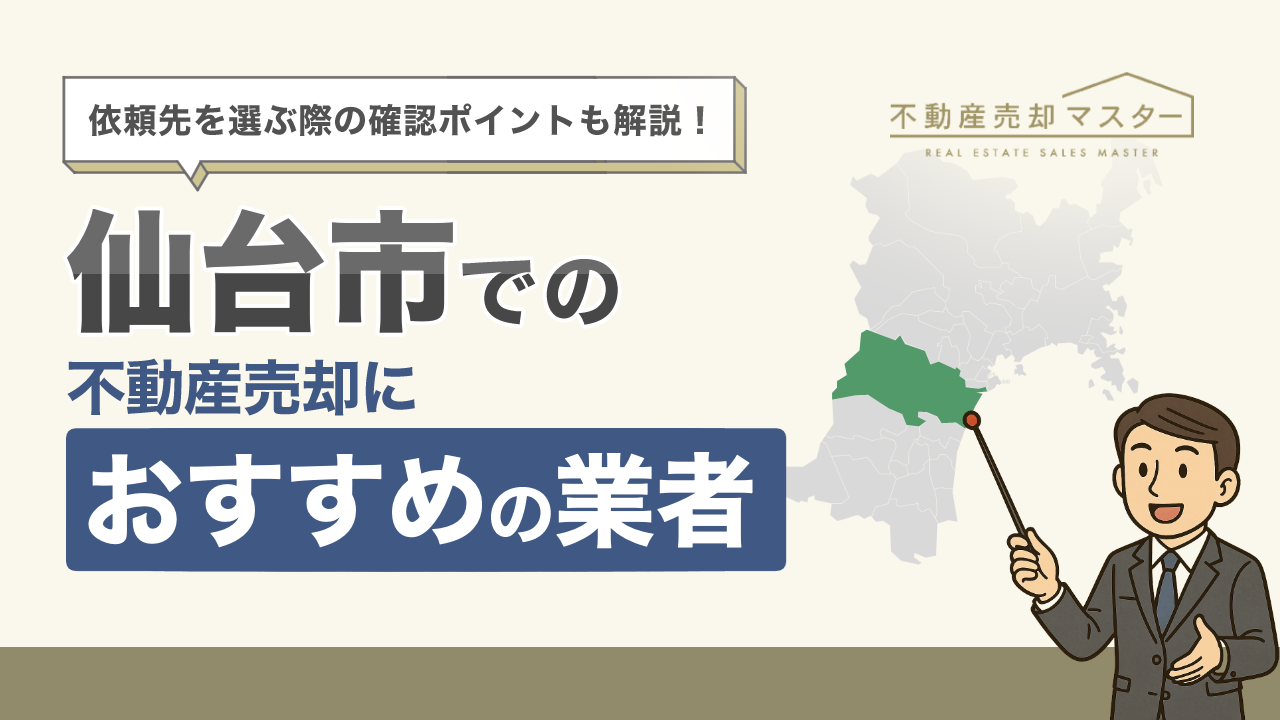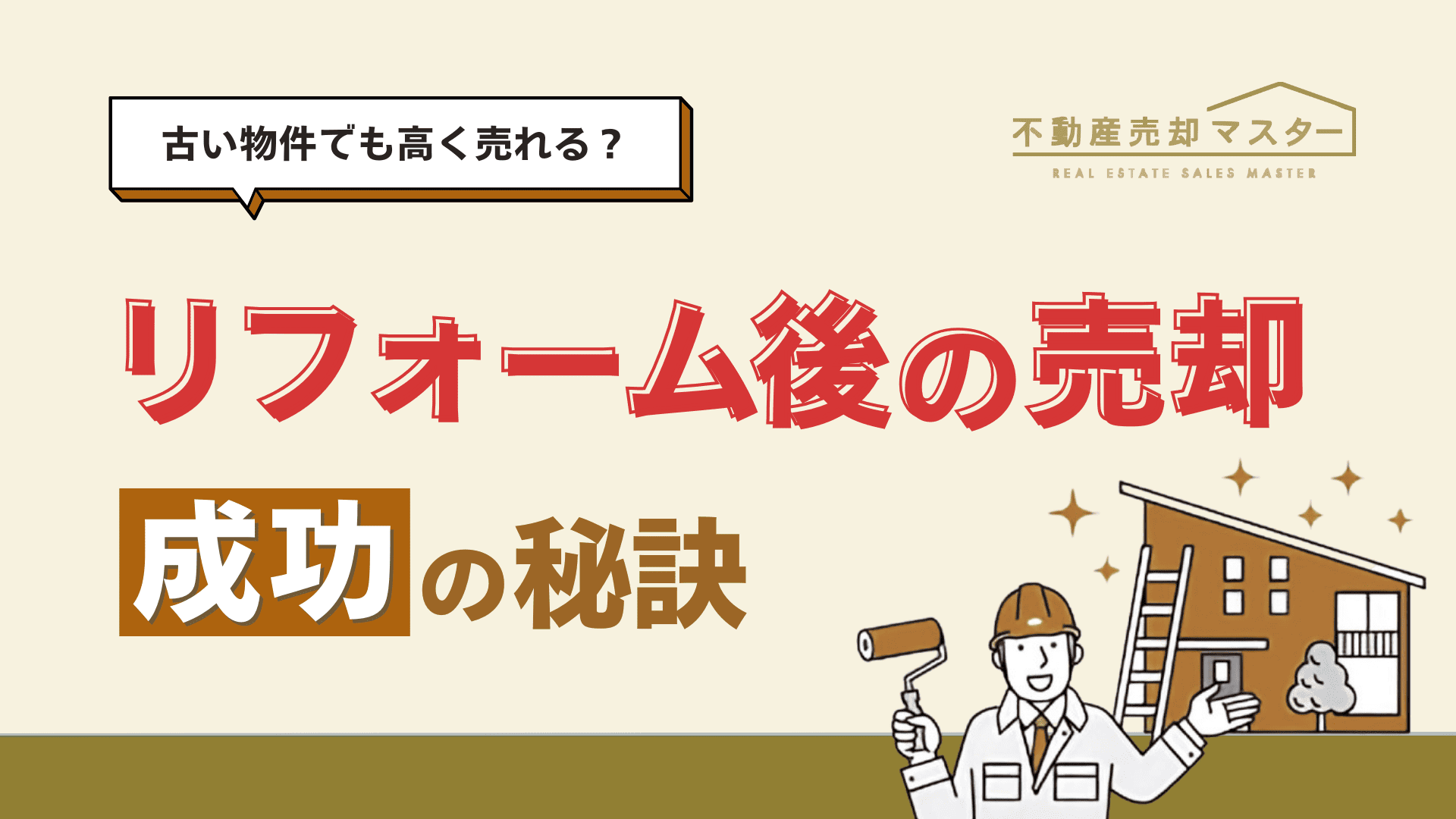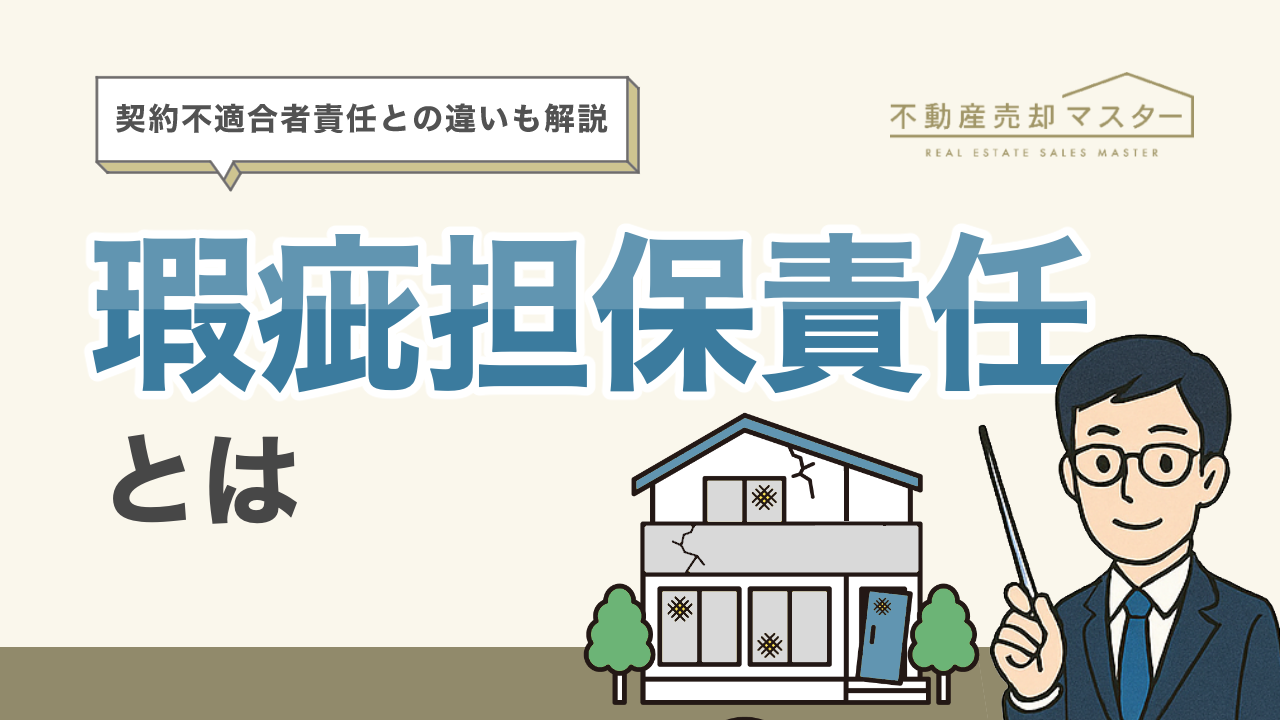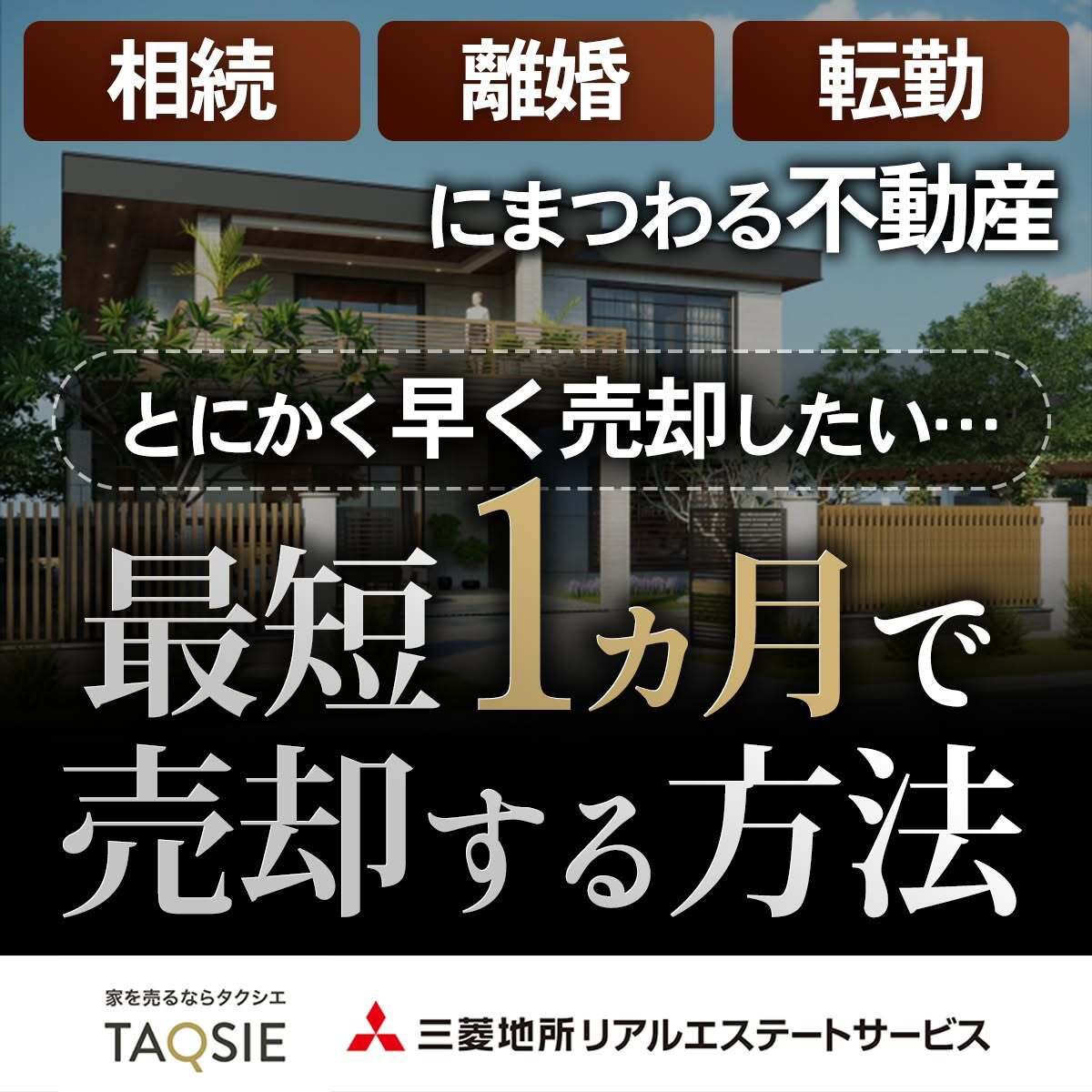成年被後見人(成年後見制度を利用してサポートを受ける方)の不動産を売却するにあたって、手続きの流れがわからず悩んでいる方もいるでしょう。
成年後見人が不動産売却を行う場合、不動産の種類によっては家庭裁判所の許可が必要になります。売却活動をスムーズに進めるためにも、手続きの流れを正確に理解しておくことが重要です。
本記事では、不動産売却を成年後見人が行う方法を解説します。
- この記事を読むと分かること
-
- 成年後見人が不動産売却をする際に裁判所の許可が必要なケース
- 成年後見人が不動産売却をする際の流れ
- 成年後見人が不動産売却をする際の必要書類
家を売りたくなったらタクシエ
三菱地所リアルエステートサービスが
あなたのエリアで実績の多い不動産会社をご紹介!
チャットで完結OK!
しつこい営業電話はありません!
成年後見人による居住用の不動産売却には家庭裁判所の許可が必要
 成年後見人が、成年被後見人の居住用不動産を売却する際は、家庭裁判所の許可が必要です。被後見人の生活基盤を守るために、成年後見人に家庭裁判所の許可を得ることが義務付けられています(※1)。家庭裁判所の許可を得ずに成年後見人が売却した場合、売買契約は無効になります。
成年後見人が、成年被後見人の居住用不動産を売却する際は、家庭裁判所の許可が必要です。被後見人の生活基盤を守るために、成年後見人に家庭裁判所の許可を得ることが義務付けられています(※1)。家庭裁判所の許可を得ずに成年後見人が売却した場合、売買契約は無効になります。
居住用に該当する不動産は、現に成年被後見人が住んでいる家だけではありません。過去に住んでいた不動産や、将来的に居住する予定の不動産も居住用不動産に該当する場合があります(※2)。
たとえば、成年被後見人が介護施設に入所しており、将来自宅に戻る可能性がある場合、その自宅は居住用とみなされ、売却するには裁判所の許可が必要になることがあります。居住用不動産に該当するか判断できない場合は、裁判所に確認しましょう。
(※1)「民法」(デジタル庁)
(※2)「成年後見人・保佐人・補助人ハンドブック(Q&A付き)」(東京家庭裁判所)
▼関連記事
不動産売却の方法とは?流れや必要書類、発生する税金を解説
成年後見人が不動産売却をする際の流れ【居住用の場合】

成年後見人が不動産売却をする際は、以下の流れで手続きを進めます。
- 不動産の相場を調べて査定を依頼する
- 不動産会社と媒介契約を締結し売却活動をする(仲介の場合)
- 買主と不動産の売買契約を結ぶ
- 管轄の家庭裁判所に許可の申立てを行う
- 決済をして不動産を引き渡す
- 家庭裁判所に報告する
- 確定申告をする
それぞれの手順を解説します。
1.不動産の相場を調べて査定を依頼する
成年後見人が不動産を売却する際は、まず不動産の相場を調べます。適正価格で売却しなければ家庭裁判所の許可が下りない可能性があるため、相場の把握が必要です。
成年被後見人の不動産と類似した物件の売却価格を確認すれば、おおよその相場が把握できます。過去の売却価格は、不動産流通機構が運営する「レインズ」や国税庁の「不動産情報ライブラリ」で確認しましょう。
おおよその相場を把握したら不動産会社に査定を依頼し、査定結果をもとに売り出し価格を決めます。不動産会社に依頼できる査定方法は、以下の2種類です。
査定方法 | 概要 |
|---|
簡易査定(机上査定) | 不動産会社の担当者が、物件情報や過去の取引事例などを参考に査定額を算出する方法 |
訪問査定 | 不動産会社の担当者が、実際の不動産を現地調査したうえで査定額を算出する方法 |
現地調査を行う訪問査定は、詳細な情報をもとに査定額が算出されるため、机上査定よりも査定の精度は高くなります。
家庭裁判所に売却の申立てをする際には、不動産会社が作成した査定書が必要です。そのため、成年後見人が不動産売却をする場合は、精度の高い訪問査定を依頼しましょう。
▼関連記事
不動産の売却相場の調べ方|購入価格・エリア・築年数など9つの方法
不動産売却時の見積もりの取り方は?おすすめの依頼先や注意点も解説
2.不動産会社と媒介契約を締結し売却活動をする(仲介の場合)
売却を依頼する不動産会社を決めたら媒介契約を締結し、不動産会社の担当者が売却活動を開始します。媒介契約とは、不動産売買の仲介を依頼する際に不動産会社と締結する契約です。媒介契約には、一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類があります。
媒介契約の種類 | 一般媒介契約 | 専任媒介契約 | 専属専任媒介契約 |
|---|
複数社との締結 | 可能 | 不可能 | 不可能 |
買主との直接取引 | 可能 | 可能 | 不可能 |
契約期間 | 期間制限なし | 3ヶ月以内 | 3ヶ月以内 |
売主への報告義務 | 報告義務なし | 報告義務あり (2週間に1回以上) | 報告義務あり (1週間に1回以上) |
レインズへの登録義務 | 登録義務なし | 登録義務あり (媒介契約の締結から7日以内) | 登録義務あり (媒介契約の締結から5日以内) |
参考:「媒介契約の種類」(国土交通省)
複数の不動産会社に売却を依頼したい場合は、一般媒介契約を結びましょう。広範囲で売却活動ができるため、駅に近い物件や築浅物件など需要が高く購入希望者が見つかりやすい不動産を売却する場合に向いています。
家庭裁判所への申請に不安がある場合は、成年後見人による不動産売却に詳しい不動産会社と専任媒介契約か専属専任媒介契約を結ぶのがおすすめです。
一般媒介契約よりも拘束力が強い契約のため、手厚いサポートを受けられ売却活動を積極的に行ってもらえる傾向にあります。売却する不動産の特徴や自分の状況に合わせて媒介契約を選ぶとよいでしょう。
なお、不動産会社に直接買い取ってもらう場合は買主が確定しているため、媒介契約の締結は不要です。
3.買主と不動産の売買契約を結ぶ
買主が決まったら売買契約を結びます。不動産会社を通じて送られてくる購入申込書を確認して、内容に問題なければ不動産会社の立ち合いのもと契約手続きを済ませます。
成年後見人が不動産を売却する場合は、売買契約書に停止条件を記載する必要がある点に注意しましょう。停止条件とは、特定の条件が満たされるまで契約の法的効力の発生を停止させることです。
売買契約書に「家庭裁判所の売却許可を得られたら契約を有効にする」などの条件を明記します。万が一、家庭裁判所の許可が得られなかった場合は契約が無効となるため、トラブルを避けられます。
4.管轄の家庭裁判所に許可の申立てを行う
売買契約が成立したら、成年被後見人の住所地を管轄する家庭裁判所に許可の申立てを行います。申立書に800円の収入印紙を貼付して、必要書類と一緒に提出します(※1)。申立書を提出してから審判されるまでにかかる期間は約2週間です(※2)。
買主と売買契約を結ぶ前に申立てを行うことも可能です。その場合、売買契約書の案を提出し、許可が下りた後に売買契約書の案と同じ内容で売買契約を結びます。
(※1)「居住用不動産処分の許可の申立てについて」(東京家庭裁判所)
(※2)「よくある質問 東京家庭裁判所後見センター」(裁判所)
5.決済をして不動産を引き渡す
家庭裁判所の許可が下りたら、売却代金の決済をして不動産を引き渡します。成年後見人、買主、不動産会社の担当者、司法書士が不動産会社や金融機関に集まって手続きを進めるのが一般的です。
売買代金の決済時には、必要に応じて固定資産税や修繕積立金などの清算も済ませます。所有権移転登記に必要な書類や鍵を買主に渡したら、引き渡しは完了です。受け取った売買代金は成年被後見人の財産として成年後見人が厳格に管理します。
6.家庭裁判所に報告する
不動産の売却が完了したら、家庭裁判所に報告書を提出します。成年後見人には、被後見人の財産管理状況を裁判所に報告する義務があるからです。
原則として年に1回行う定期報告のタイミングで、報告書に不動産売却の内容について記載して提出します(※)。
後見監督人(後見人の役割を監督する者)が家庭裁判所により選任されている場合は、後見監督人の指示に従って対応します。
(※)「<定期報告について>」(東京家庭裁判所)
7.確定申告をする
不動産の売却で利益が出た場合、成年被後見人であっても原則として確定申告が必要です。不動産を売却した翌年の2月中旬〜3月中旬の申告期間内に行います。
申告書の提出先は、成年被後見人の住所地を管轄する税務署です。期限内に申告を済ませなかった場合、無申告加算税や延滞税を課される可能性があるため、早めに準備をして必ず期限内に提出しましょう(※)。確定申告書の作成に不安を感じる方は、税理士に相談するとよいでしょう。
(※)「確定申告を忘れたとき」(国税庁)
▼関連記事
不動産売却による確定申告の必要書類は?特例の適用を受ける際や相続の場合も解説
不動産売却後の確定申告が不要になるケースは?譲渡所得額がいくらなら税金がかからないかも解説
成年後見人が不動産売却をする際の流れ【居住用以外の場合】
 賃貸物件などの居住用以外の不動産を成年後見人が売却する際の流れは、以下のとおりです。
賃貸物件などの居住用以外の不動産を成年後見人が売却する際の流れは、以下のとおりです。
- 不動産の相場を調べて査定を依頼する
- 不動産会社と媒介契約を締結し売却活動をする(仲介の場合)
- 買主と不動産の売買契約を結ぶ
- 決済をして不動産を引き渡す
- 家庭裁判所に報告する
- 確定申告をする
居住用以外の不動産売却においては家庭裁判所の許可は必要ないため、基本的には一般的な不動産売却の流れで手続きを進められます。
ただし、不動産を現金化して医療費や生活費に充てる必要があるなど、正当な理由がなければ不動産を売却できません。正当な理由がないにもかかわらず成年被後見人の不動産を売却すると、家庭裁判所から後見人としてふさわしくないと判断される可能性があります。
事前に売却の意向を裁判所に相談しておくとよいでしょう。
▼関連記事
不動産売却の流れは?かかる期間や必要書類も解説【図解あり】
成年後見人が不動産売却をする際の必要書類
成年後見人が不動産売却をする際には、以下の書類が必要です。
書類 | 概要 | 必要な時期 |
|---|
登記権利証または登記識別情報 | 不動産の所有者を証明する書類 | 売却依頼時 引き渡し時 |
確定測量図、境界確認書 | 土地の面積や、隣接する土地との境界線が記載された書類 | 売却依頼時 |
登記事項証明書(登記簿謄本) | 所有権や建物の構造などが記載された書類 | 売却依頼時 申立て時 |
建物の図面 | 建物の形状や敷地との位置関係がわかる図面 | 売却依頼時 |
申立書 | 家庭裁判所に不動産売却の許可の申立てをする書類 | 申立て時 |
不動産売買契約書 | 売主と買主の売買契約の内容が記載された書類 | 申立て時 |
固定資産評価証明書 | 土地や建物などの固定資産の評価額を証明する書類 | 申立て時 |
不動産会社が作成した査定書 | 不動産の査定額が記載された書類 | 申立て時 |
郵便切手(110円) | 裁判所の返信封筒に貼付する切手 | 申立て時 |
監督人の意見書(成年後見監督人がいる場合) | 監督人が売却に同意していることを証明する書類 | 申立て時 引き渡し時 |
売却許可審判書(居住用不動産の場合) | 家庭裁判所から売却の許可を得たことを証明する書類 | 引き渡し時 |
固定資産税通知書 | 固定資産税の税額が記載されている書類 | 引き渡し時 |
実印 | 成年後見人の実印 | 引き渡し時 |
成年後見人の登記事項証明書 | 成年後見人であることを証明する書類 | 引き渡し時 |
成年後見人の印鑑証明書 | 市区町村で登録している印鑑の証明書 | 引き渡し時 |
成年後見人の本人確認書類 | 免許証やマイナンバーカードなど、本人であることを証明できる書類 | 引き渡し時 |
参考:「居住用不動産処分の許可の申立てについて」(東京家庭裁判所)
マンションを売却する場合は、マンションの長期修繕計画書や管理規約なども必要です。申立て時に必要な書類は管轄の家庭裁判所によって変わる場合もあるため、事前に確認しておきましょう。
成年後見人が不動産売却の依頼先を探すならTAQSIE(タクシエ)に相談!
成年後見人が被成年後見人の居住用不動産を売却する場合は、家庭裁判所の許可を得なくてはなりません。居住用以外の不動産は一般的な不動産売却と同様の流れで売却できますが、正当な理由が必要です。
複雑な手続きに不安を感じる場合は、成年後見人による不動産売却に詳しい不動産会社に売却を依頼しましょう。専門的なアドバイスを受けられるため、スムーズに売却を進められます。
成年後見人による不動産売却の依頼先を探すなら、不動産の買取・仲介担当者とのマッチングサービス「TAQSIE(タクシエ)」をご利用ください。
80社以上の大手不動産会社の中から、成年後見人による不動産売却を丁寧にサポートできる担当者を3名(買取のスピード売却コースは最大5名)紹介いたします。担当者が買主を探してくれる「なっとく提案売却コース(仲介)」と、最短3日で買取価格を提示する「スピード売却コース(買取)」があり、仲介・買取のどちらでもスムーズな売却を目指せます。無料の会員登録で不動産売却の相談をできるので、ぜひご活用ください。
三菱地所リアルエステートサービス 新事業推進部
「不動産売却マスター」編集長
【保有資格】宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、衛生管理者、ファイナンシャルプランナー3級
2008年入社。人事部門で福利厚生制度などの企画運営、住宅賃貸部門でタワーマンション営業所長、高級賃貸マンション企画などを経て、2018年より経営企画部で主に事業開発を担当し、複数の新規事業立上げに従事。2020年度三菱マーケティング研究会ビジネスプランコンテスト最優秀賞受賞。「TAQSIE」では初期構想から推進役を担い、現在もプロジェクト全般に関わっている。
「不動産の売却に特化した情報を発信する『不動産売却マスター』編集部です。不動産の売却や買取をスムーズに進めるポイントや、税金、費用などをわかりやすく解説します」
あなたのケースにあった
ご成約者の声を見てみる
絞り込む

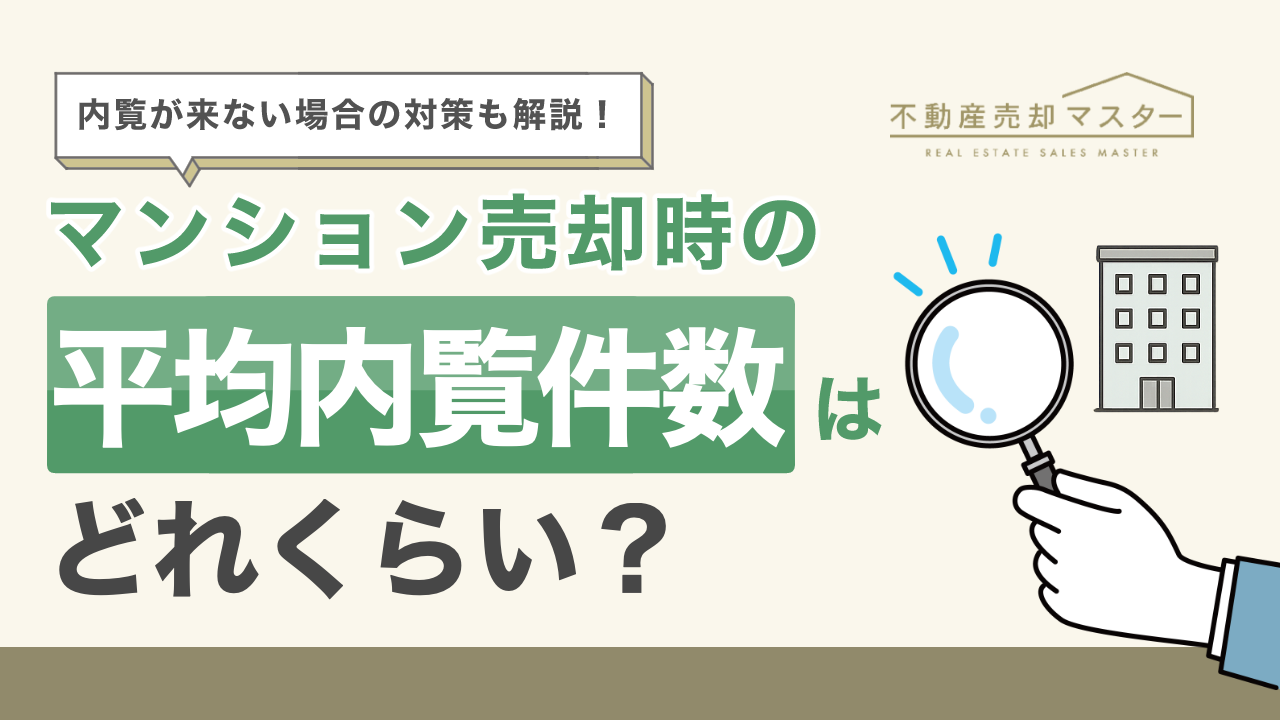
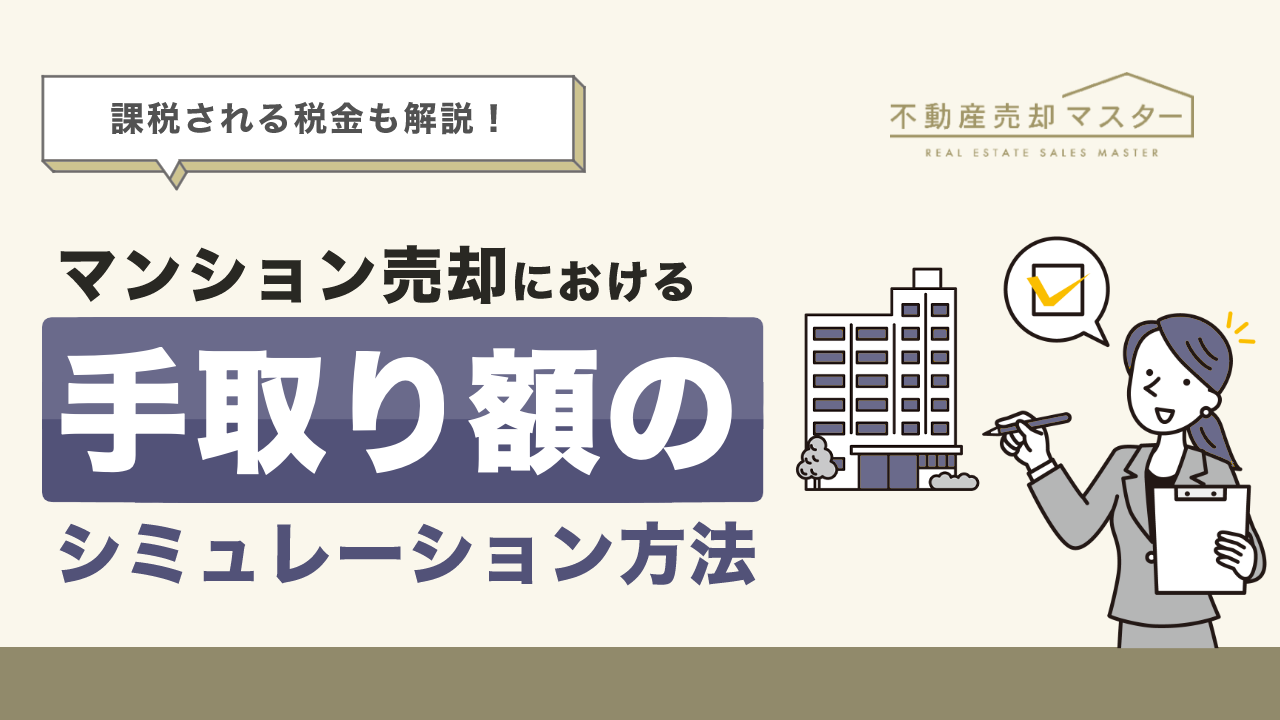









 成年後見人が、成年被後見人の居住用不動産を売却する際は、家庭裁判所の許可が必要です。被後見人の生活基盤を守るために、成年後見人に家庭裁判所の許可を得ることが義務付けられています(※1)。家庭裁判所の許可を得ずに成年後見人が売却した場合、売買契約は無効になります。
成年後見人が、成年被後見人の居住用不動産を売却する際は、家庭裁判所の許可が必要です。被後見人の生活基盤を守るために、成年後見人に家庭裁判所の許可を得ることが義務付けられています(※1)。家庭裁判所の許可を得ずに成年後見人が売却した場合、売買契約は無効になります。
 賃貸物件などの居住用以外の不動産を成年後見人が売却する際の流れは、以下のとおりです。
賃貸物件などの居住用以外の不動産を成年後見人が売却する際の流れは、以下のとおりです。