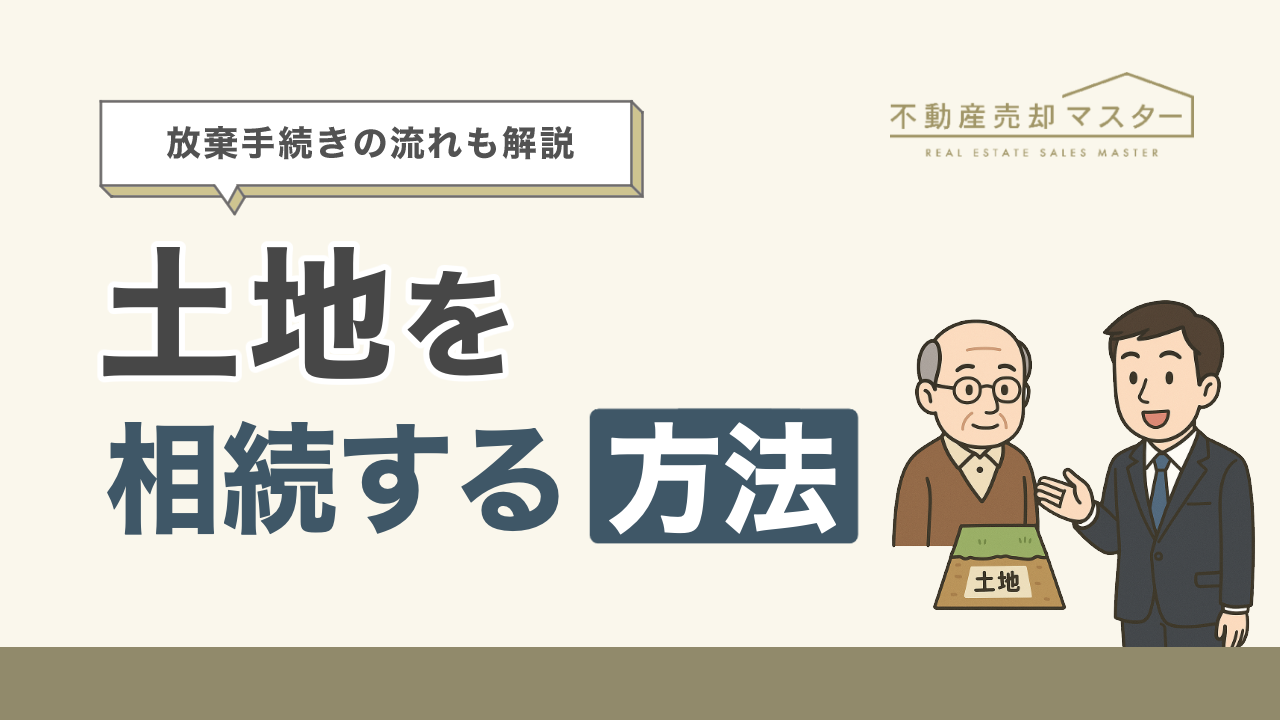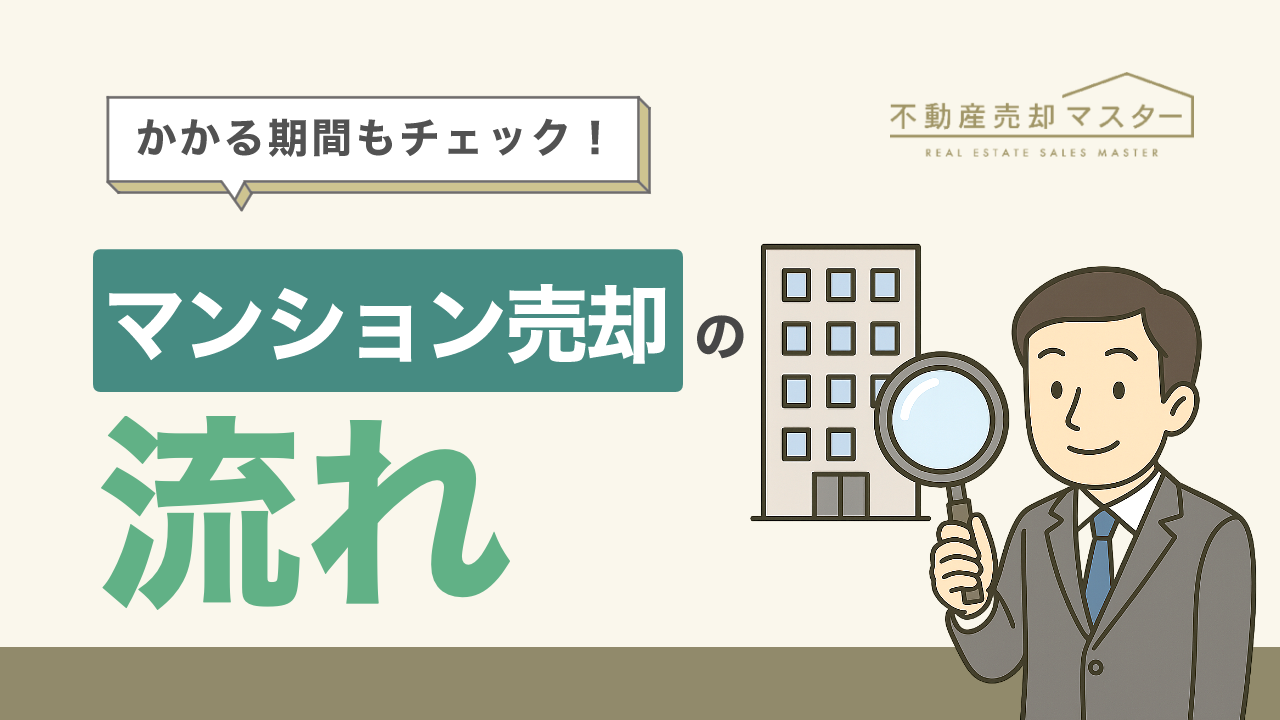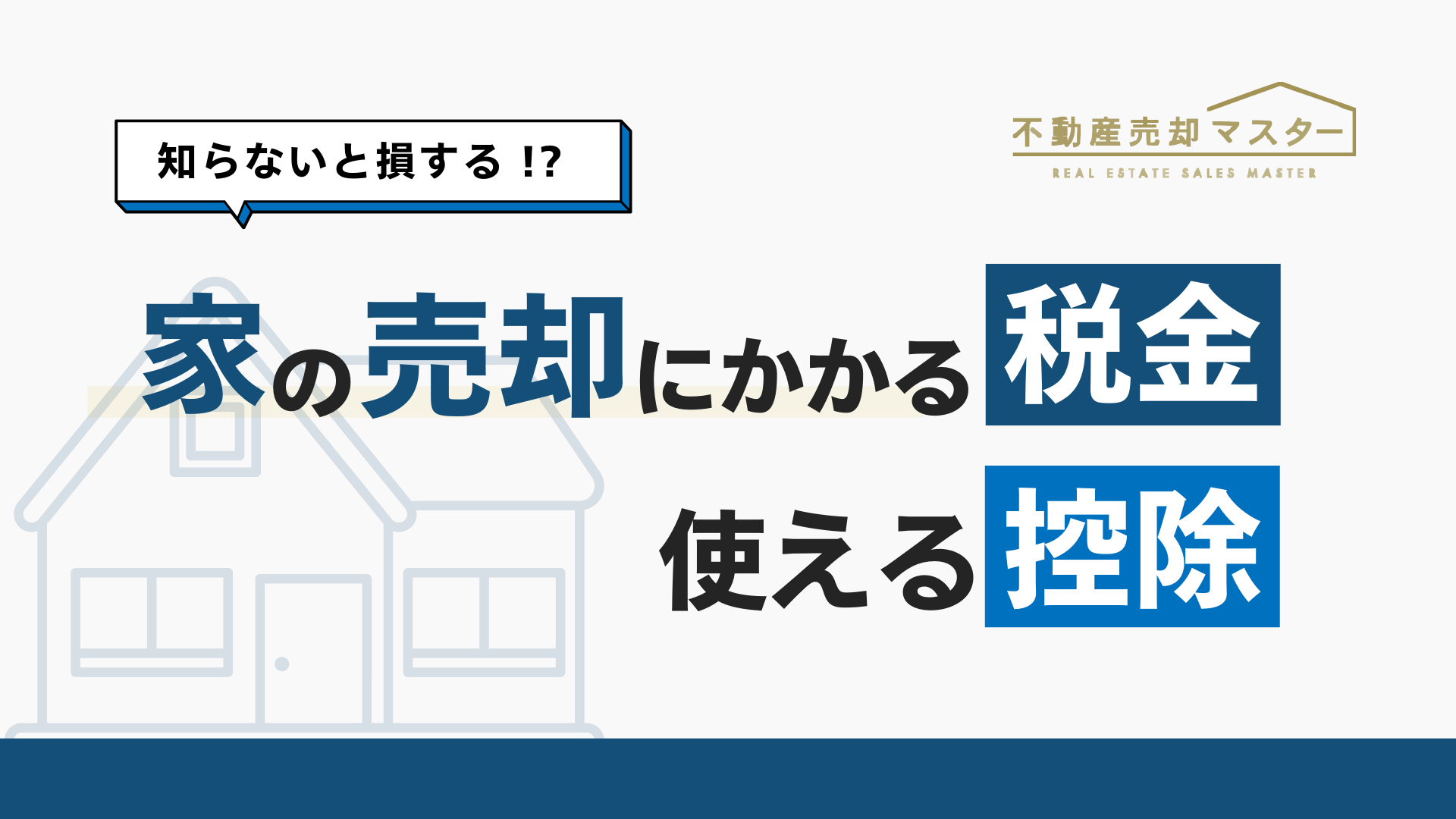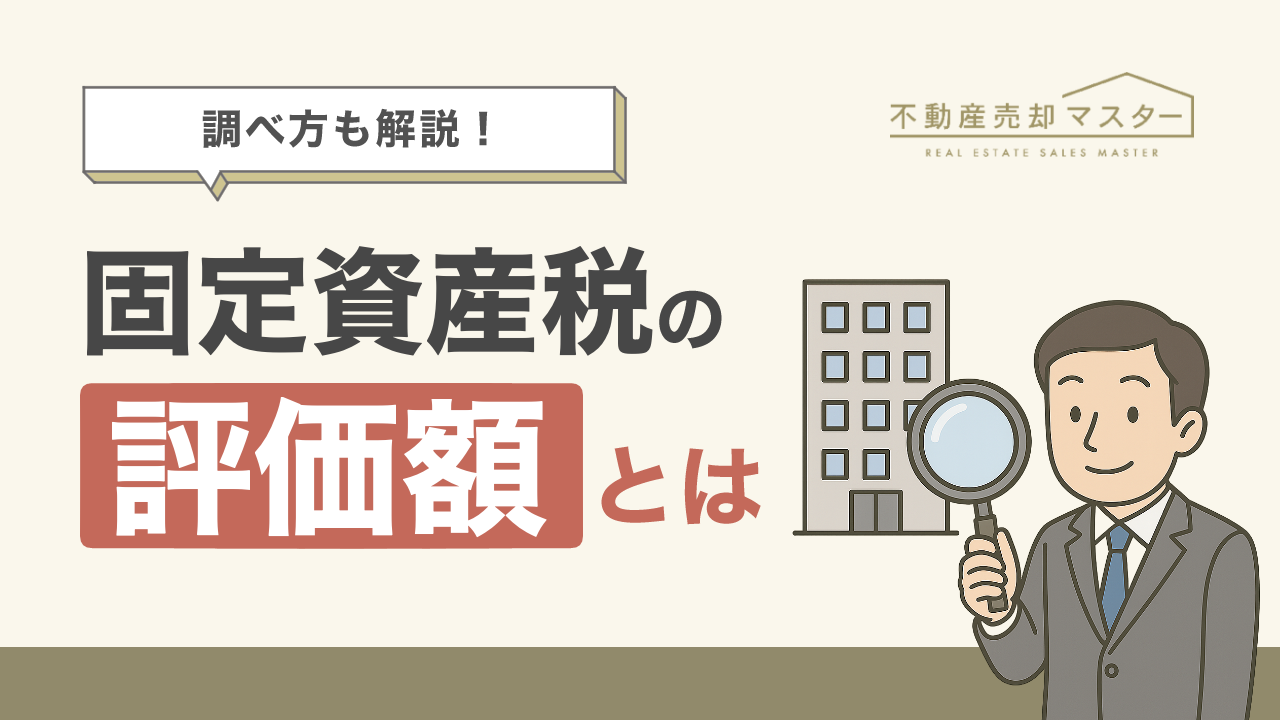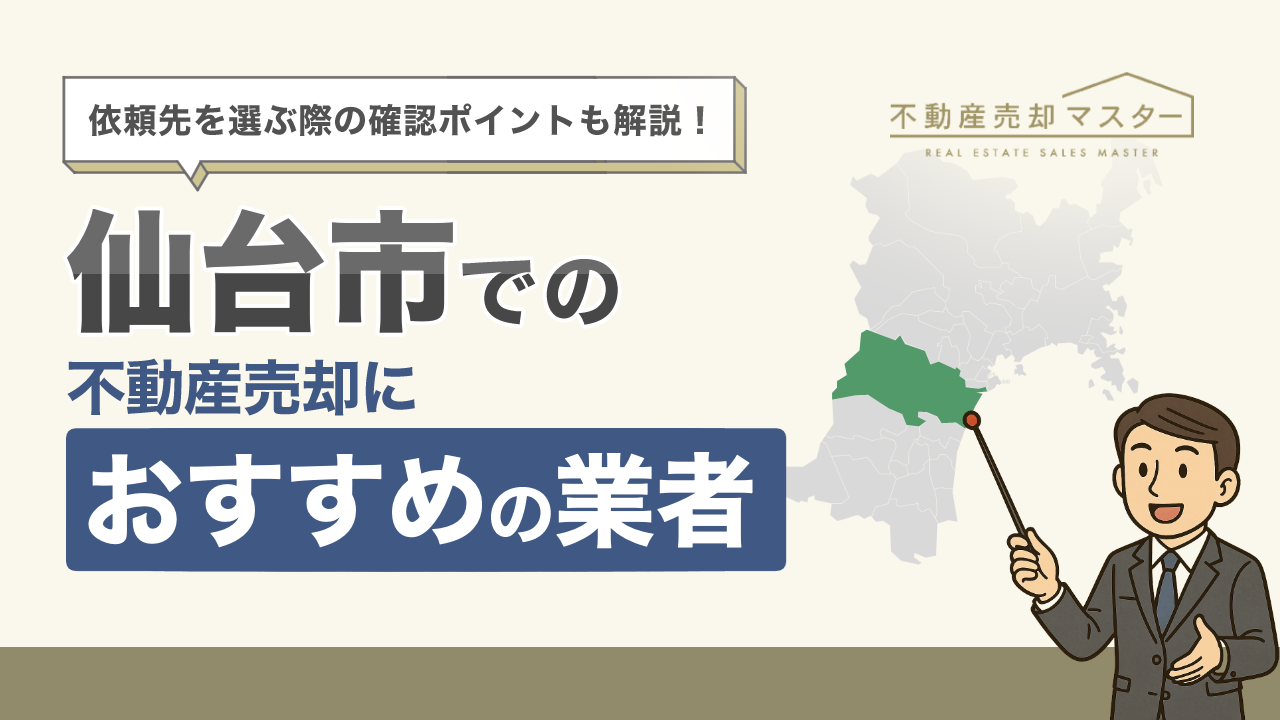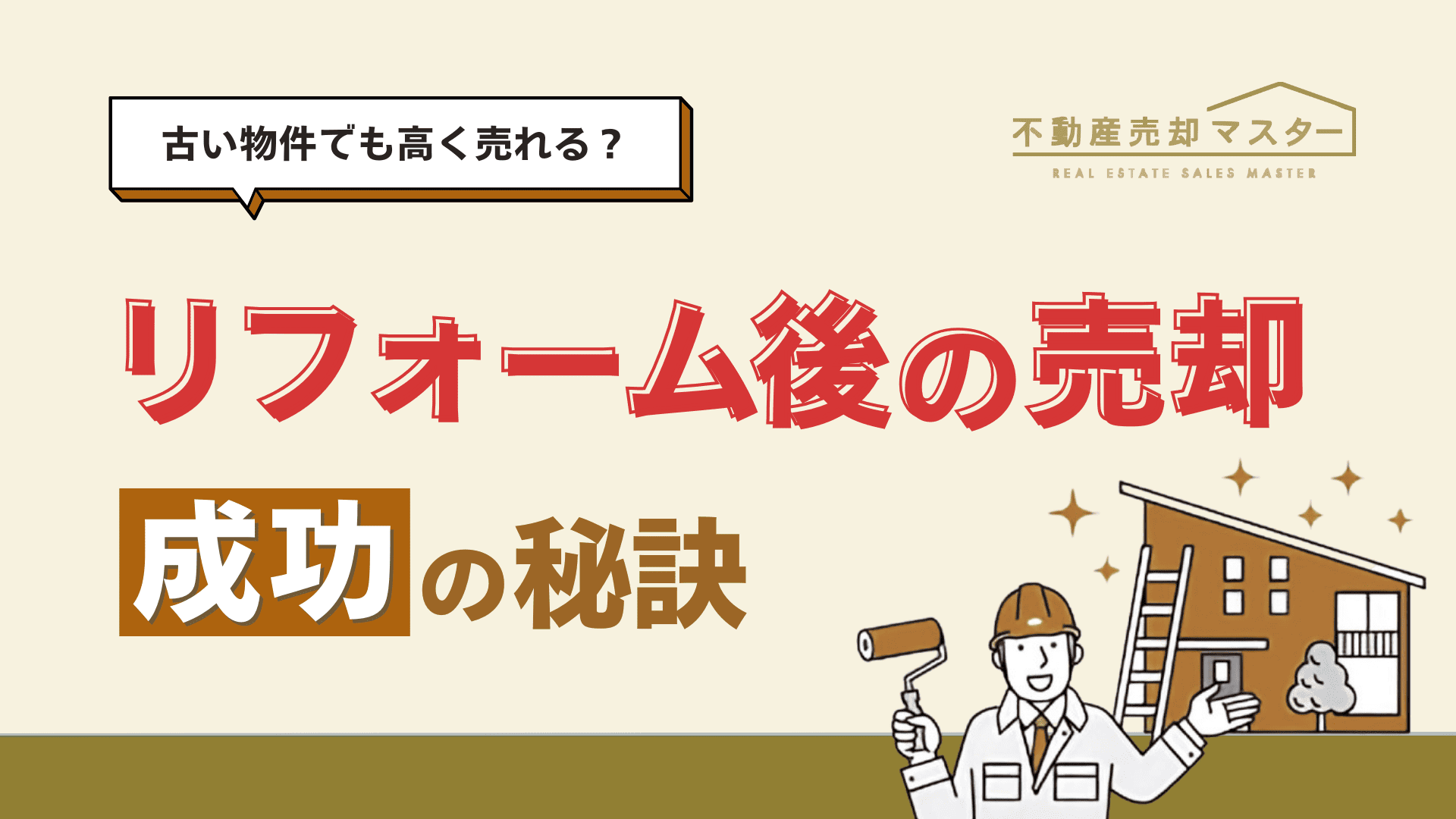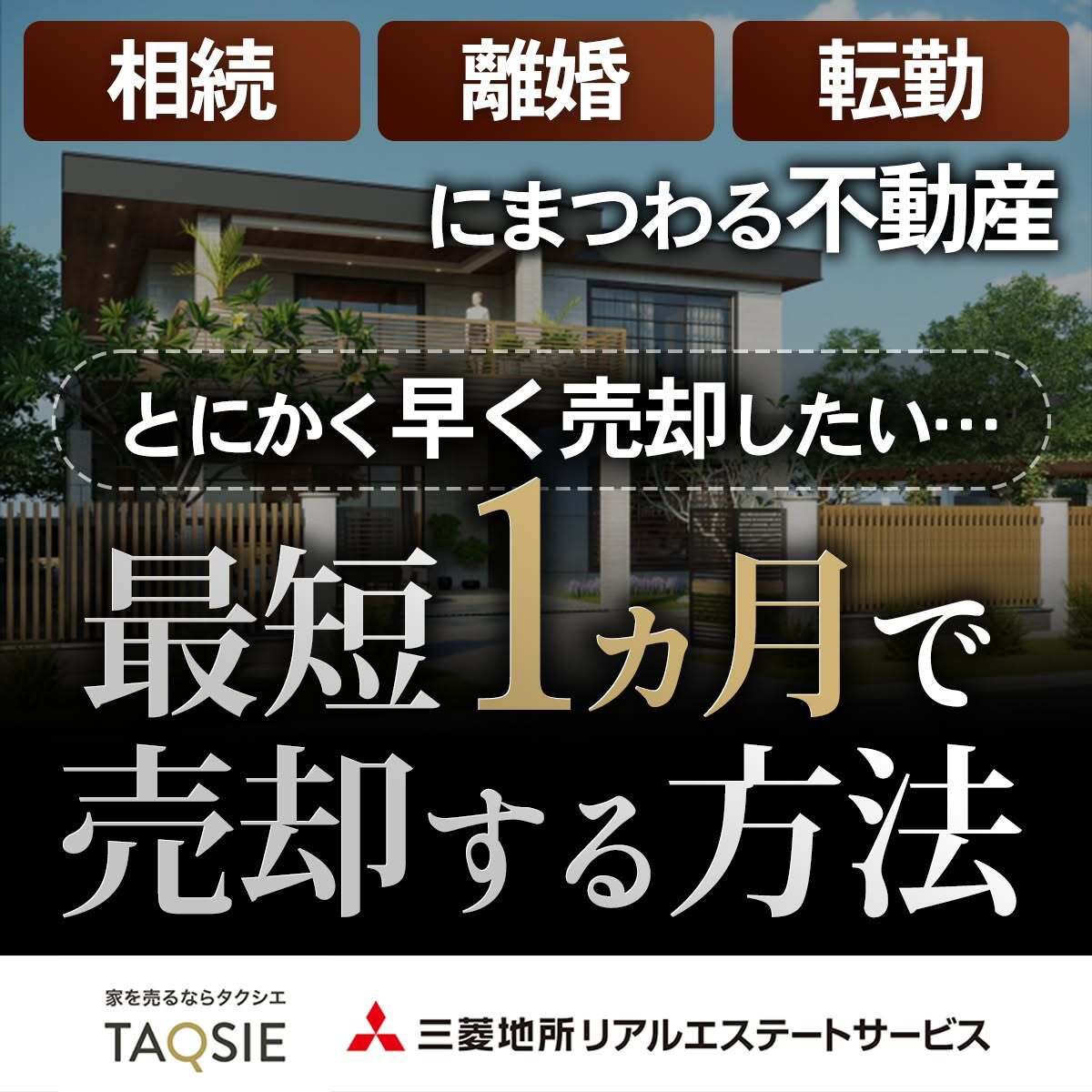不動産情報を見ていると、「平米(㎡)」「坪」「畳」など、様々な単位で広さが表示されているのを目にするでしょう。これらの単位は、それぞれ異なる特徴と使用場面があり、物件探しをする際には正確な理解が欠かせません。特に日本では、伝統的な「坪」や「畳」と、現代的な「平米(㎡)」が混在して使用されているため、単位の換算や実際の広さのイメージにお悩みの方も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、これらの計測単位の基本的な知識から計算方法、さらには世帯人数に合わせた適切な広さの選び方、公示地価、基準地価、路線価といった不動産の関連用語まで、物件探しに役立つ情報を詳しく解説していきます。
- この記事を読むと分かること
-
- 平米(㎡)・坪・畳の違いと計算方法
- 【世帯人数別】間取り決めのポイント
- 押さえておきたい土地・物件の基本用語
家を売りたくなったらタクシエ
三菱地所リアルエステートサービスが
あなたのエリアで実績の多い不動産会社をご紹介!
チャットで完結OK!
しつこい営業電話はありません!
対照表と計算方法
 不動産物件を探す際には、「平米(㎡)」「坪」「畳」など、さまざまな単位で広さが表示されているのを目にします。
不動産物件を探す際には、「平米(㎡)」「坪」「畳」など、さまざまな単位で広さが表示されているのを目にします。
それぞれの単位を正確に理解し、自身が望む広さを的確に把握するには、単位間の換算方法を知っておくことが重要です。ここでは、実用的な換算表と具体的な計算方法を説明します。
広さを表す単位の対照表
物件探しで活用できる換算表を以下にまとめました。
不動産物件を探す際には、様々な単位での表示を正確に理解し、自身の希望する広さを的確に把握することが重要です。ここでは、実用的な換算方法と具体的な計算例を詳しく解説していきます。
| 平米(㎡) |
坪 |
畳数 |
一般的な間取り |
| 20㎡ |
約6坪 |
約12畳 |
1R/1K |
| 30㎡ |
約9坪 |
約18畳 |
1K/1DK |
| 40㎡ |
約12坪 |
約24畳 |
1LDK/2DK |
| 50㎡ |
約15坪 |
約30畳 |
2DK/2LDK |
| 60㎡ |
約18坪 |
約36畳 |
2LDK |
| 70㎡ |
約21坪 |
約42畳 |
3LDK |
| 80㎡ |
約24坪 |
約48畳 |
3LDK/4LDK |
参考:坪・平米(㎡)・畳数 計算ツール
この換算表を参考にすることで、物件情報に記載された広さの単位を、なじみのある単位に素早く換算することができます。例えば、30平米(㎡)の物件であれば、約9坪、約18畳という具合に、おおよその広さをイメージすることが可能です。
平米(㎡)と坪の計算方法
平米(㎡)と坪の換算は、不動産取引では最も頻繁に必要となる計算です。基本的な換算式は以下の通りです。
平米(㎡)⇔坪の換算式
- 坪 = 平米(㎡) ÷ 3.3
- 平米(㎡) = 坪 × 3.3
実際の計算例を見てみましょう。例えば、65平米(㎡)の物件の坪数を計算する場合、65 ÷ 3.3 = 約19.7坪となります。逆に、25坪の物件の平米数(㎡)を計算する場合は、25 × 3.3 = 82.5平米(㎡)となります。物件探しをする時には、概算で「1坪≒3.3平米(㎡)」と覚えておくと便利です。
よく使われる坪⇔平米(㎡)の換算式
- 10坪 = 33平米(㎡)
- 15坪 = 49.5平米(㎡)
- 20坪 = 66平米(㎡)
- 25坪 = 82.5平米(㎡)
- 30坪 = 99平米(㎡)
特に賃貸物件では和室と洋室が混在していることも多いため、両方の換算に慣れておくと便利です。
例えば「6畳和室+8畳洋室+6畳DK」という間取りの場合、関東間で計算すると、約33平米(㎡)(約10坪)となります。
平米(㎡)と畳の計算方法
平米(㎡)と畳の換算には、地域による畳のサイズの違いを考慮する必要があります。一般的な換算の目安は以下の通りです。
平米(㎡)⇔畳の換算式
- 関東間:1畳 = 約1.65平米(㎡)
- 京間:1畳 = 約1.82平米(㎡)
例えば、10畳間の広さを平米(㎡)に換算する場合、関東間では10 × 1.65 = 16.5平米(㎡)、京間では10 × 1.82 = 18.2平米(㎡)となります。物件情報で畳数表示を見かけた際は、地域による違いを考慮しながら換算することが重要です。
よく使われる畳⇔平米(㎡)の換算式
- 4.5畳 = 約7.4平米(㎡)
- 6畳 = 約9.9平米(㎡)
- 8畳 = 約13.2平米(㎡)
- 10畳 = 約16.5平米(㎡)
- 12畳 = 約19.8平米(㎡)
世帯人数別に適した間取り・広さ

一人暮らしの場合は個人の好みによって柔軟に間取りや広さを選択すればよいですが、複数人で住む場合にはどのような間取りやどれくらいの広さがあれば十分かわかりにくいかと思います。
以下の表は、世帯人数別に最低限必要とされる広さや推奨とされる広さを示した例です。
【世帯人数別 推奨居住面積の目安】
| 世帯人数 |
最低限必要 |
推奨 |
理想的な広さ |
| 1人 |
20平米(㎡) |
25平米(㎡) |
35平米(㎡)以上 |
| 2人 |
30平米(㎡) |
40平米(㎡) |
50平米(㎡)以上 |
| 3人 |
40平米(㎡) |
55平米(㎡) |
75平米(㎡)以上 |
| 4人 |
50平米(㎡) |
70平米(㎡) |
95平米(㎡)以上 |
参考:国土交通省「住生活基本計画における居住面積水準」
1人や2人で住む場合の家の広さについては必要な広さに想像がつくケースが多いかと思いますが、特に子供を持ってから3人以上で暮らす場合にはどれくらいの広さ・間取りがあれば十分かわからないケースも多いでしょう。
そこで以下では、単身世帯以外特に多い、夫婦と子供(1人・2人)で住むケースに適した間取り・広さを紹介します。
夫婦と子供(3人暮らし)
3人家族に適した家の広さは60平米(㎡)(約18坪)程度です。子供の年齢や生活スタイルにもよりますが、2LDKまたは3LDKの間取りが基本となります。
特に子供が成長期の場合、学習スペースの確保が重要になってきます。リビングは家族の団らんの中心となるため、最低でも12畳(約20平米(㎡))以上の広さを確保することをおすすめします。
さらに、子供部屋は将来の学習机や本棚の設置を考慮すると、6畳(約10平米(㎡))以上あると理想的です。収納スペースについては、子供の成長に伴う衣類や学用品の増加も見据えて、十分な容量を確保することが大切です。
▼関連記事
家を買うベストタイミングはいつ?お得な制度や失敗しないためのポイントも解説
夫婦と子供2人(4人暮らし)
4人家族の場合は、75平米(㎡)(約23坪)以上の広さがあるとよいでしょう。理想的な広さは85平米(㎡)(約26坪)以上で、3LDKや4LDKの間取りが推奨されます。子供2人の年齢差や性別に応じて、個室の確保が重要になってきます。
家族全員が集まるリビングは、15畳(約25平米(㎡))以上の広さがあると、食事スペースと寛ぎスペースを十分に確保できます。また、子供部屋は将来の進学や成長に合わせて、学習環境の整備が可能な広さと間取りを選ぶことが重要です。
▼関連記事
家の買い替えに適したタイミングは?流れや費用、ローン残債がある場合の対処法も解説
住み替えで失敗しない2つの方法とは?流れや費用、節税、注意点を解説
押さえておきたい土地・物件の用語

不動産取引では、面積に関するさまざまな専門用語が使用されます。これらの用語を正しく理解することは、物件選びにおいて重要なポイントとなります。特に「表示面積」と「実際に使える面積」の違いは、生活する上で大きな影響を与える要素となります。
▼関連記事
不動産売却の方法とは?流れや必要書類、発生する税金を解説
不動産売却の流れは?かかる期間や必要書類も解説【図解あり】
壁芯面積と内法面積
不動産広告や重要事項説明書でよく目にする面積表示には、主に「壁芯(へきしん)面積」と「内法(うちのり)面積」の2種類があります。これらの違いを理解することで、実際の生活空間を正確に把握することができます。
壁芯面積
不動産の面積表示において、壁芯面積は建物の壁や柱の中心線を基準として計測された面積を指すとされています。建築基準法における床面積の定義では、この壁芯面積が採用されているため、不動産広告やパンフレットなどに記載される建物面積や専有面積は、一般的に壁芯面積で表示されているようです。
そのため、実際の使用可能面積よりも大きな数値となります。以上のことから、設計向けの表記と言えます。
内法面積
壁芯で面積を出す考え方とは異なり、壁の内側の線を基準にした面積を床面積とする計算方法を「内法面積(うちのりめんせき)」とよびます。
内法面積というのは、実際に目に見える範囲で考えた広さともいえます。住む人の立場に立って考えれば、目に見えていて、実際に使える部分の面積が重要です。
壁から壁までがどれくらいの距離があるのかによって、配置が可能な家具の大きさが決まるからです。そこで、物件の賃貸で部屋の広さが問題になる不動産業界では、この内法が基本となっています。
以上のことから、不動産向けの表記と言えます。
- 大型家具の配置には開閉スペースを含めた検討
- 収納家具の実効容量の確認
- 動線の確保と生活スペースの使いやすさ
家具のレイアウトを考える際は、この内法面積を基準に検討することが重要です。例えば、ベッドや食器棚などの大型家具を置く場合、カタログ上のサイズに加えて開閉スペースも考慮する必要があります。
誘導居住面積水準
現代社会における多様なライフスタイルに対応した豊かな住生活を実現するため、住宅の適切な面積水準が設定されています。この水準は、人々の生活の質を確保するための重要な指標として位置づけられているとされています。
居住面積水準については、居住地域や住宅形態に応じて二つの区分が設けられているようです。まず、都市郊外や地方部における戸建住宅を想定した「一般型誘導居住面積水準」が存在するとされています。この水準は、比較的ゆとりのある居住空間を前提として設定されています。
一方、都心部やその近郊における共同住宅向けには、「都市居住型誘導居住面積水準」が定められているとされています。この水準は、都市部特有の居住形態や生活様式を考慮して設定されているようです。
これらの水準は、地域特性や住宅形態の違いを反映しながら、それぞれの環境において望ましい居住空間を確保するための指標として機能しているでしょう。
【誘導居住面積水準】
| 世帯構成 |
一般型 |
都市居住型 |
| 単身者 |
55平米(㎡) |
40平米(㎡) |
| 2人世帯 |
75平米(㎡) |
55平米(㎡) |
| 3人世帯 |
100平米(㎡) |
75平米(㎡) |
| 4人世帯 |
125平米(㎡) |
95平米(㎡) |
引用元:国土交通省|住生活基本計画における「水準」について
一般型誘導居住面積水準
一般型誘導居住面積水準は、主に都市の郊外や地方部での推奨居住面積を示す水準です。ゆとりある居住空間の確保を目指しており、例えば4人家族の場合、125平米(㎡)(約38坪)が目安とされています。この広さがあれば、各個室の十分な確保に加えて、家族共用スペースも余裕を持って設けることができます。
地方部では戸建住宅も選択肢として考えられるため、庭や駐車場なども含めた総合的な空間計画が可能です。例えば、35坪の建物に10坪の庭と2台分の駐車スペースを確保するといった計画も、地方部では現実的な選択肢となります。
都市居住型誘導居住面積水準
都市居住型は、都市部での現実的な居住面積を示す基準です。土地の制約や価格の問題から、一般型よりもコンパクトな基準となっており、4人家族の場合で95平米(㎡)(約29坪)が目安とされています。都市部の物件選びでは、この基準を参考にしながら、予算と相談して最適な広さを検討することになります。
都市部の物件では、限られた面積を効率的に活用する工夫が重要です。例えば、リビングと個室の間仕切りを可動式にしたり、収納を上手く配置したりすることで、実際の広さ以上の空間の使い方が可能になります。
最低居住面積水準
最低居住面積水準は、健康で文化的な住生活を送る上で必要不可欠な最低限の広さを定めた基準です。単身者で25平米(㎡)、4人家族で50平米(㎡)が最低ラインとされていますが、これはあくまでも最低限の基準であり、快適な生活のためにはできるだけ誘導居住面積水準に近づけることが推奨されます。
【最低居住面積水準の基準値】
| 世帯構成 |
最低居住面積 |
| 単身者 |
25平米(㎡) |
| 2人世帯 |
30平米(㎡) |
| 3人世帯 |
40平米(㎡) |
| 4人世帯 |
50平米(㎡) |
参考:徳島県庁「誘導居住面積水準、最低居住面積水準とは何ですか。」
地価に関する用語
不動産の価値を判断する際に重要となる地価情報には、主に「公示地価」「基準地価」「路線価」の3種類があります。これらの指標は、それぞれ異なる目的と特徴を持っており、物件の適正価格を判断する際の重要な参考情報となります。
▼関連記事
不動産の売却相場の調べ方|購入価格・エリア・築年数など9つの方法
公示地価
公示地価とは、適正な地価の形成に役立てるために国が公表しているものです。
土地の価格形成には、立地や形状だけでなく、取引当事者の様々な事情が影響を与える可能性があるとされています。しかしながら、市場原理のみに委ねた場合、地価の急激な変動が経済に悪影響を及ぼしたり、公共事業の円滑な実施を妨げる可能性があるのです。
このような背景から、地価公示法が制定され、都市部とその周辺地域における標準的な土地の価格を公示する制度が確立されたとされています。この制度では、一般的な取引価格の指標提供や、公共事業における適正な補償金算定などを目的としています。
標準地の選定はその地域における平均的な特性を持つ土地が対象とされ、更地としての価格が算出されるとされています。実際の都市部には更地が少ないものの、仮想的な更地価格として評価が行われているようです。
土地鑑定委員会が選定した標準地については、複数の土地鑑定士による鑑定評価が実施され、その結果をもとに価格が決定されているとされています。近年では鑑定評価書も公開されるようになり、地価の変動率や市場特性、将来予測などの詳細な情報も確認できるようになってきているようです。これらの情報は、土地購入を検討する際の重要な判断材料となる可能性があるでしょう。
基準地価
基準地価とは、各都道府県が主体となって実施する土地の標準価格の評価
夏季に評価が行われ、初秋頃に公表される仕組みとなっています。
評価対象となる基準地は全国各地に設定されており、その評価方法については公示地価とほぼ同様の手法が採用されているとされています。ただし、基準地価の特徴として都市計画区域外の土地も評価対象に含まれる点や、不動産鑑定士の必要人数が公示地価と異なる点が挙げられます。
また、一部の地点では公示地価と基準地価の両方が評価されているケースもあるとされています。このため、年初に公表される公示地価と、半年後に発表される基準地価を比較することで、より短期的な地価動向を把握できる可能性があるでしょう。
このように基準地価は公示地価と並んで、地価の変動を把握するための重要な指標として機能しています。
路線価
路線価は、相続税や贈与税などの税額算定の基準となる土地価格とされています。納税者と税務署双方の手続きを円滑にするため、土地が接している道路ごとに設定された価格が公表されています。
この路線価には、主に二種類の区分があるとされています。国税庁が公表する相続税路線価は、相続税や贈与税の算定基準として用いられることがほとんどです。一方、地方自治体が固定資産税の算出に使用する固定資産税路線価も存在します。
一般的に路線価という場合は、国税庁が定める相続税路線価を指すことが多いとされています。これらの路線価は、いずれも公示地価と連動して設定されているようですが、その評価水準については、それぞれ公示地価より低めに設定される傾向にあるとされています。
このように路線価は税務上の実務を円滑にする重要な指標として機能しており、公平な課税の実現に貢献しているのです。
具体的な評価方法や基準については、専門家への相談を推奨します。
【地価指標の比較】
| 指標 |
発表時期 |
主な用途 |
特徴 |
| 公示地価 |
3月 |
一般取引の指標 |
実勢価格の目安 |
| 基準地価 |
9月 |
地域動向の把握 |
都道府県による詳細調査 |
| 路線価 |
7月 |
税務評価の基準 |
相続税算出に使用 |
不動産の売却はTAQSIE(タクシエ)がおすすめ
いかがでしたでしょうか?
今回は、平米(㎡)や坪、畳の単位について説明しながら、世帯人数ごとの間取りの考え方についてご紹介させて頂きました。ぜひ本記事を参考に、ご自分にぴったりな間取りを見つけみてください。
また、これから物件を購入する方で、「今、住んでいる家を売却したい」とご検討している方も中にはいるのではないでしょうか?
TAQSIE(タクシエ)は、厳選された不動産売却のプロを紹介するマッチングサービスとなっております。
一人ひとりが、宅地建物取引士の資格はもちろん豊富な実績がある精鋭たちです。
不動産売却についてのお悩みの方は、登録は無料なので、お気軽にご利用ください。
あなたのケースにあった
ご成約者の声を見てみる
絞り込む

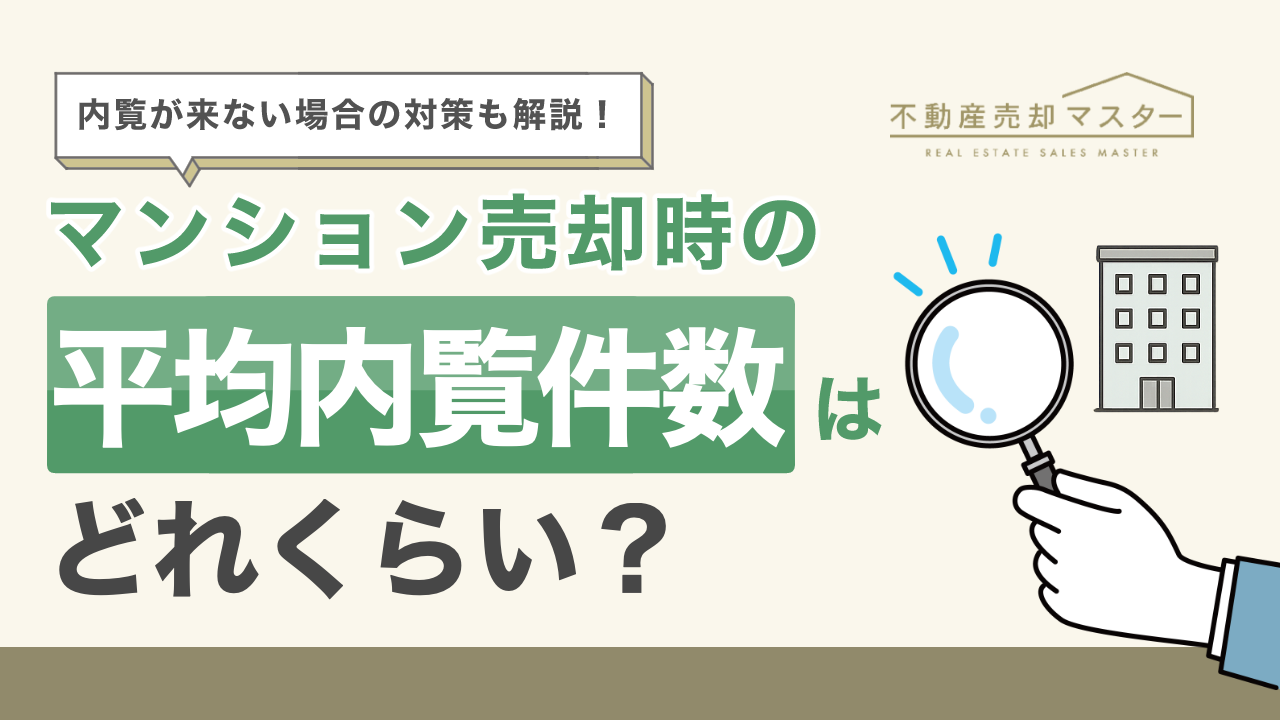
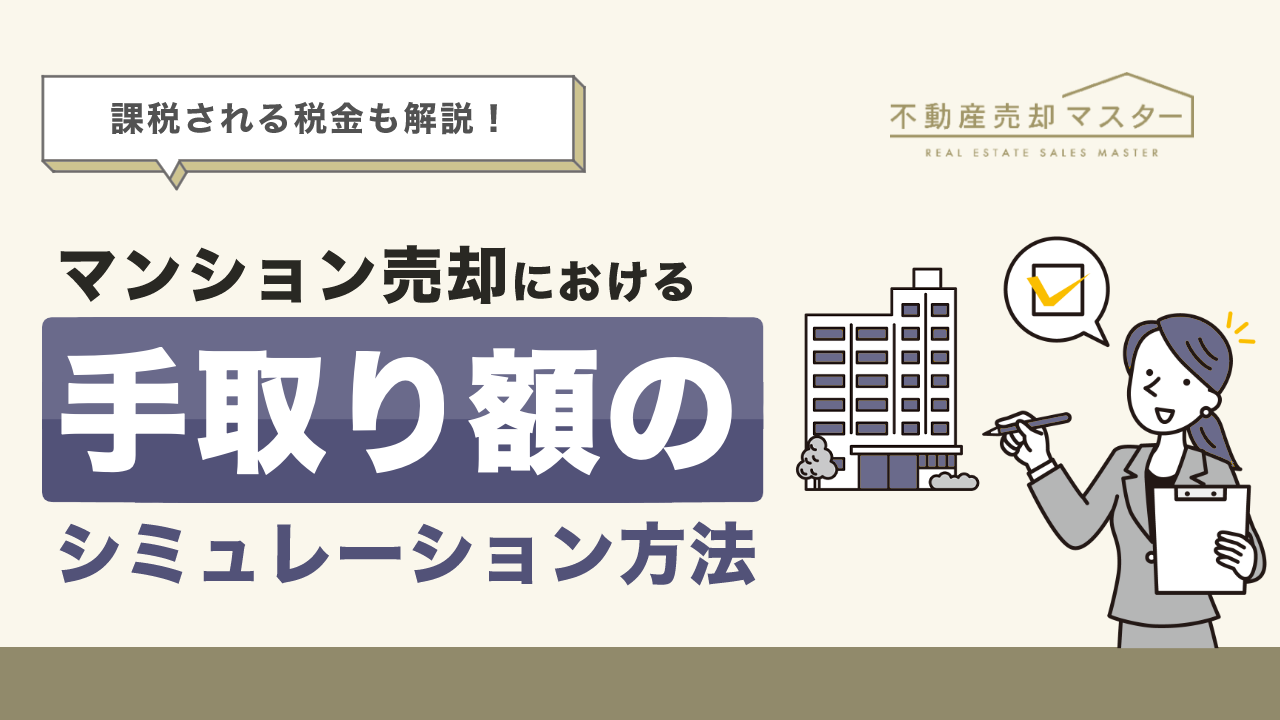


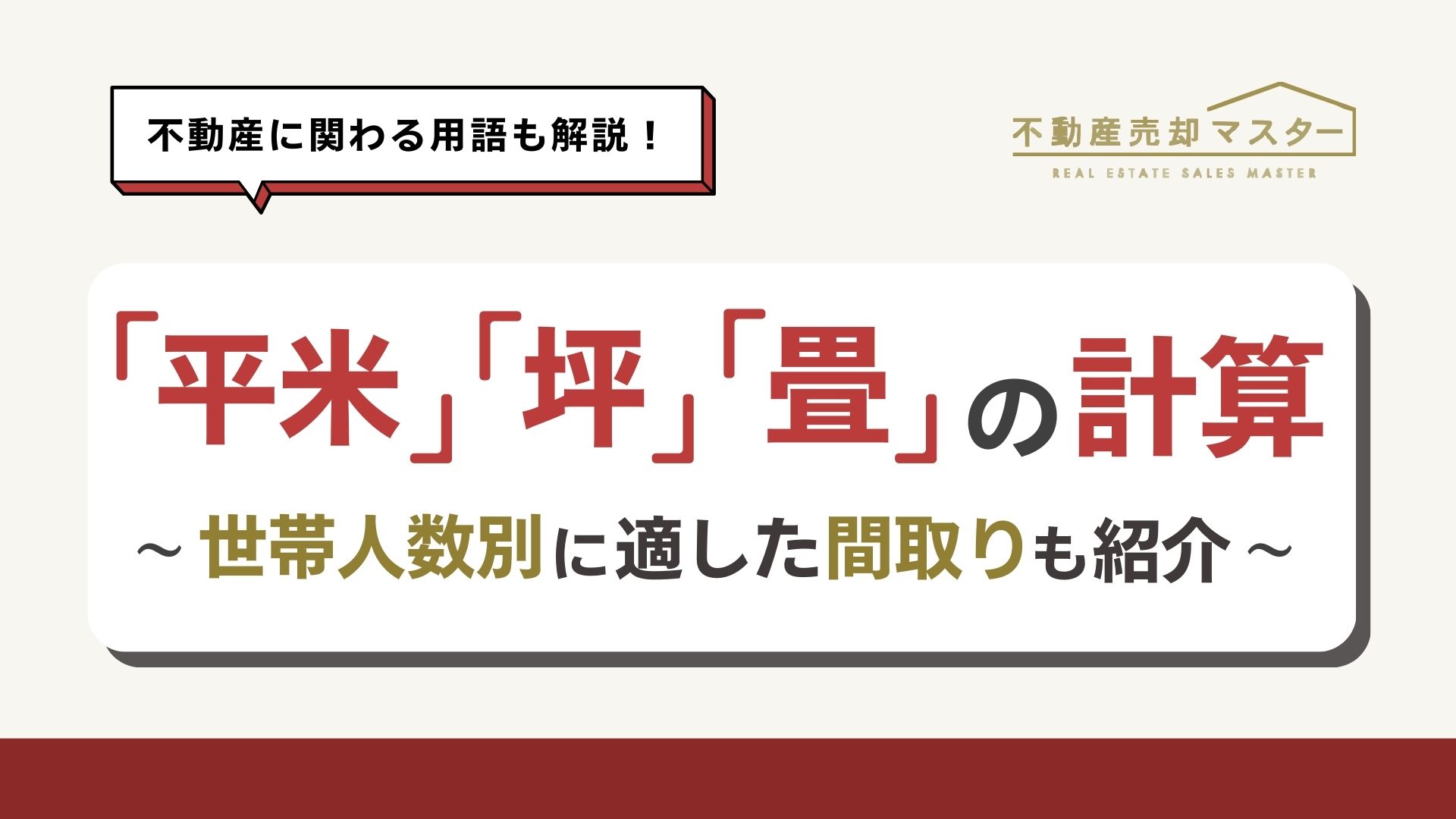






 不動産物件を探す際には、「平米(㎡)」「坪」「畳」など、さまざまな単位で広さが表示されているのを目にします。
不動産物件を探す際には、「平米(㎡)」「坪」「畳」など、さまざまな単位で広さが表示されているのを目にします。