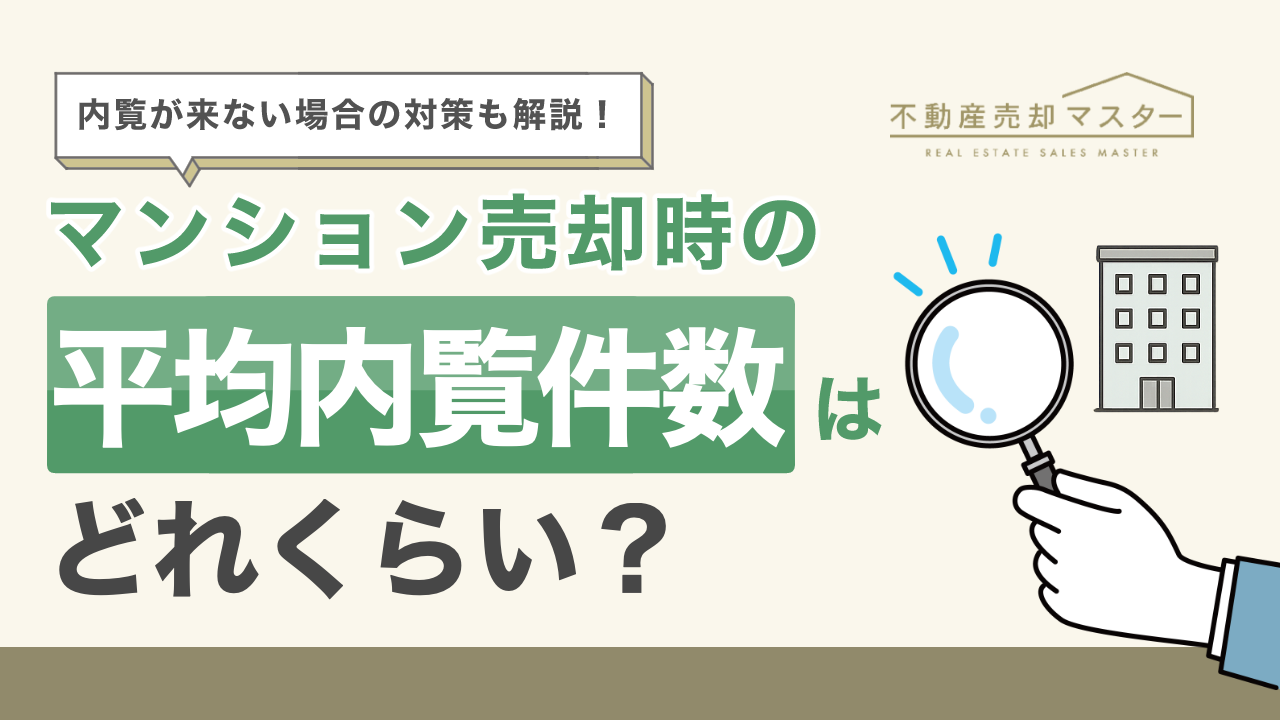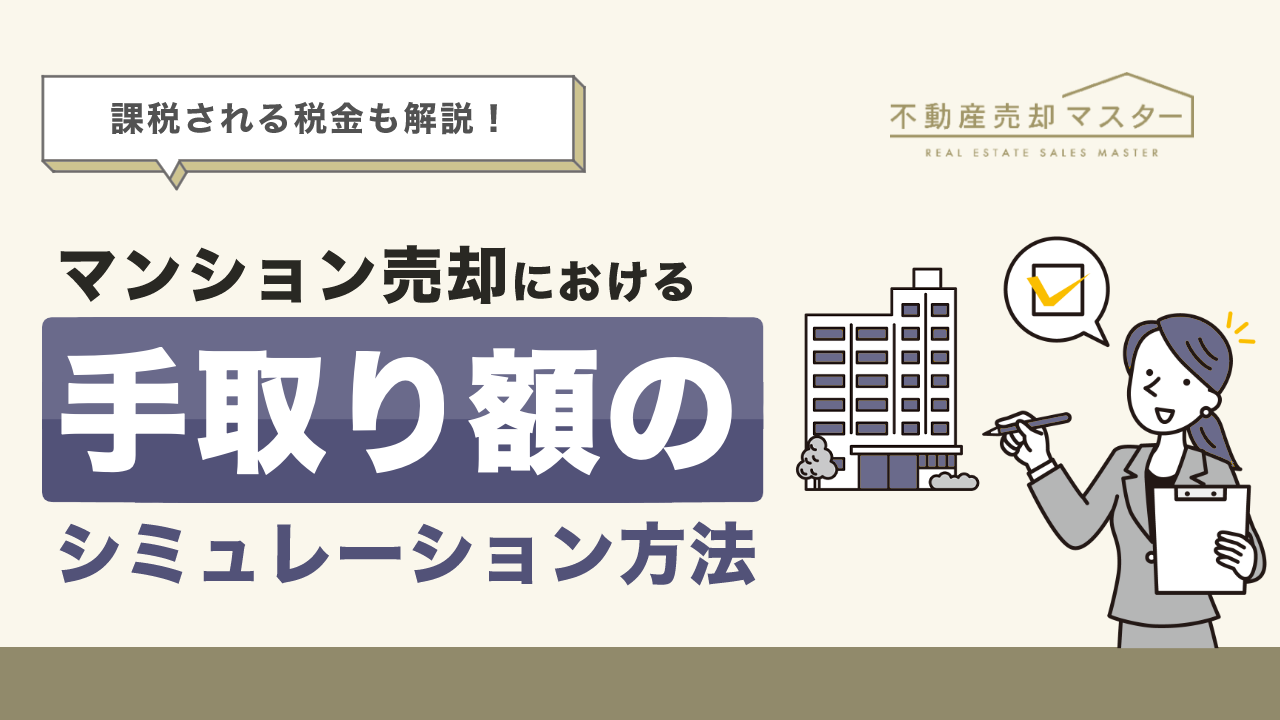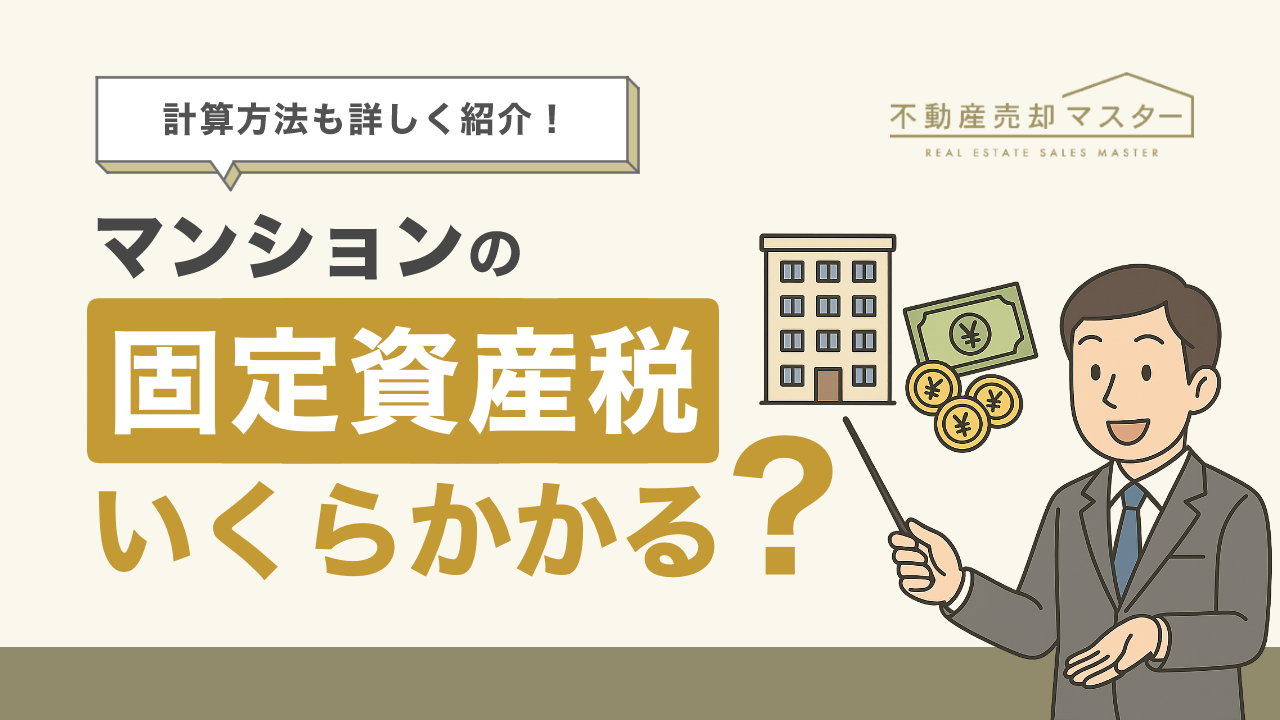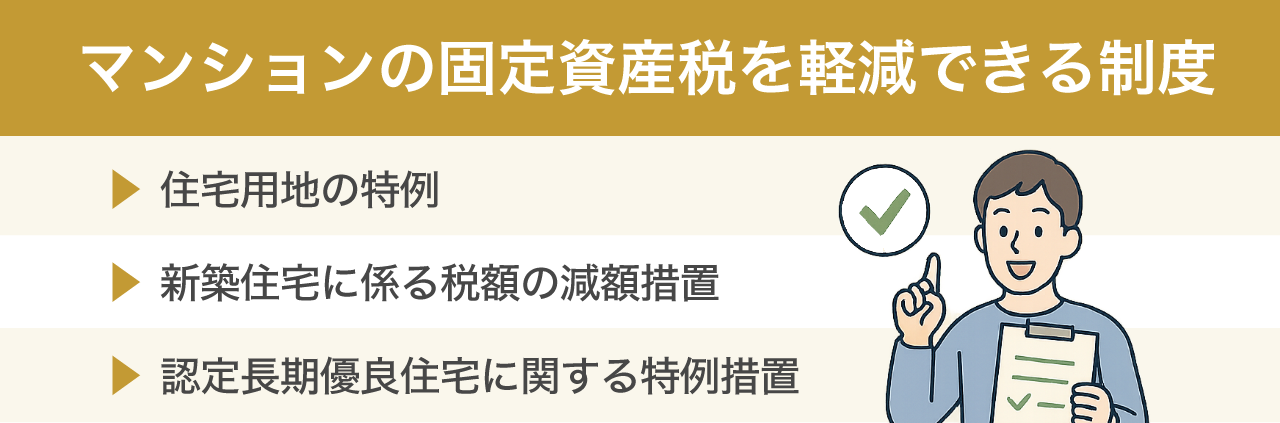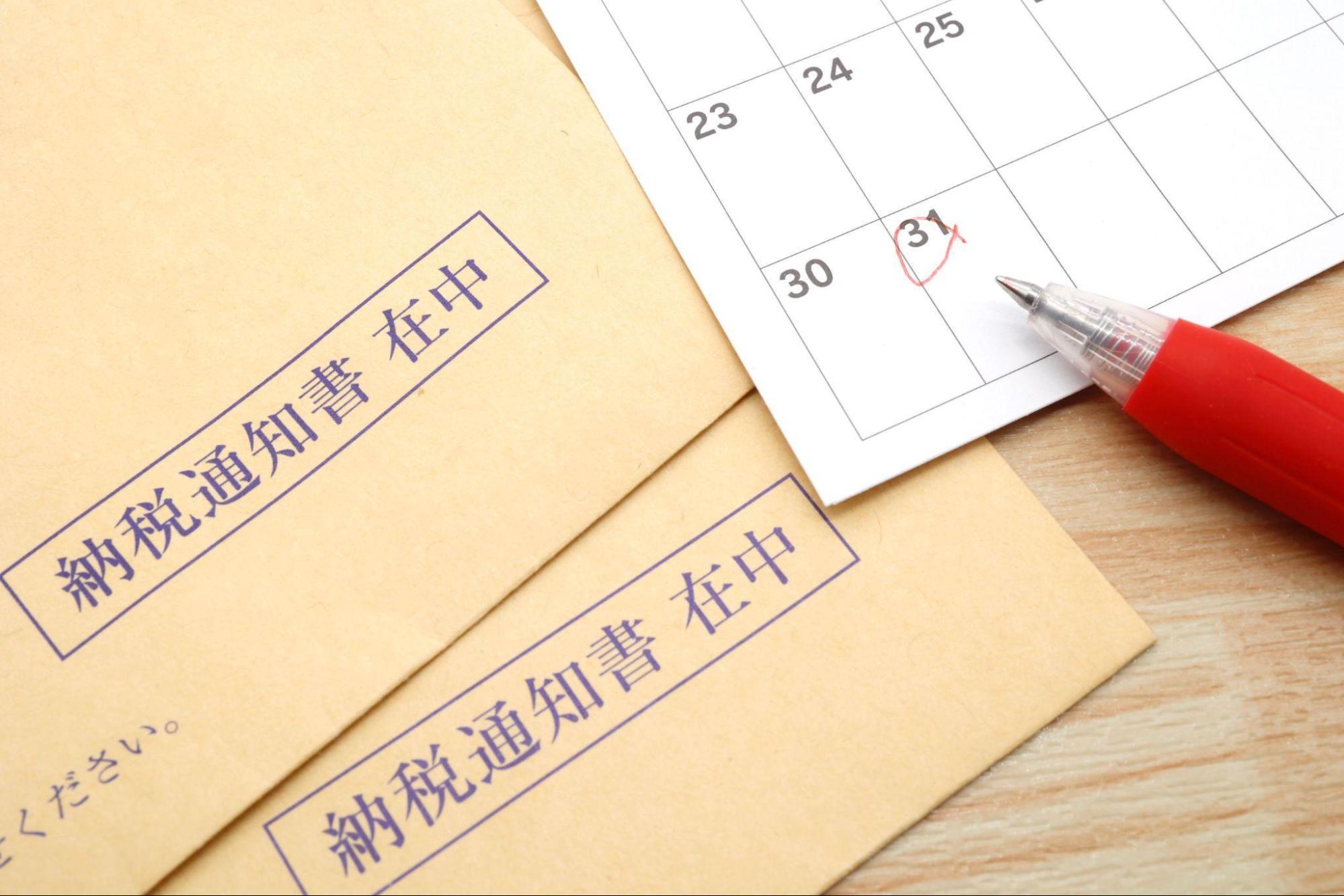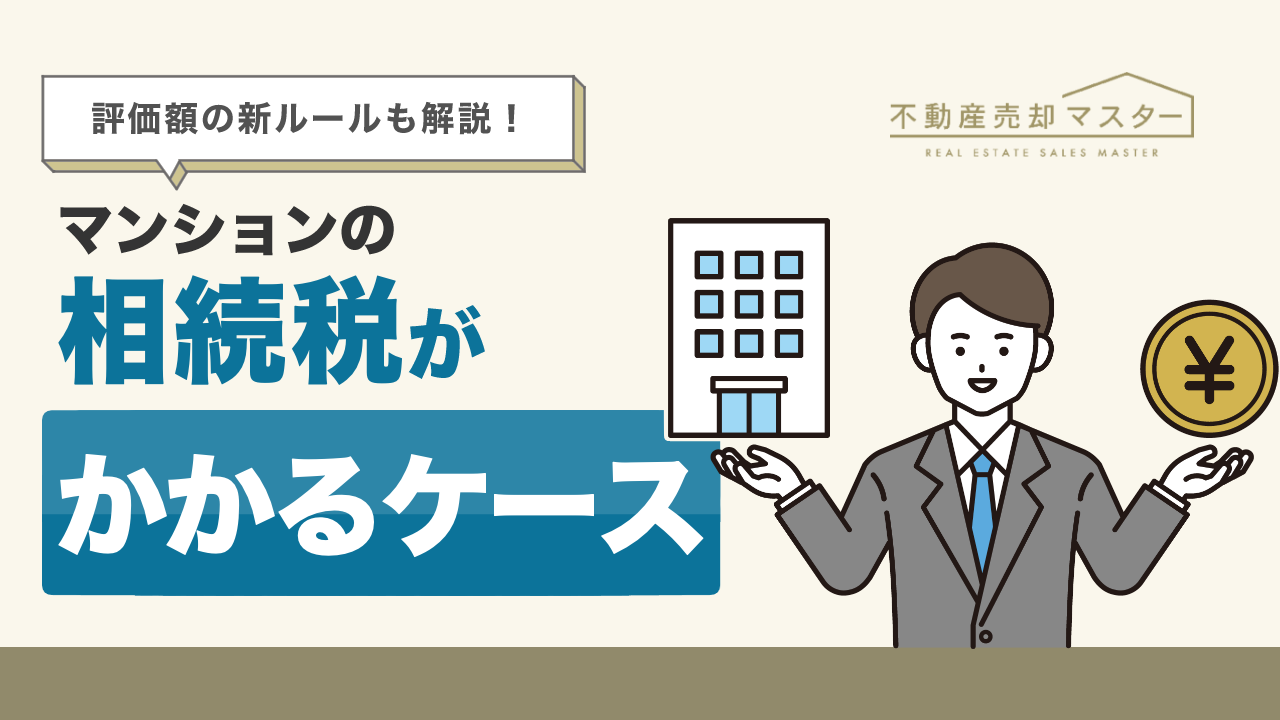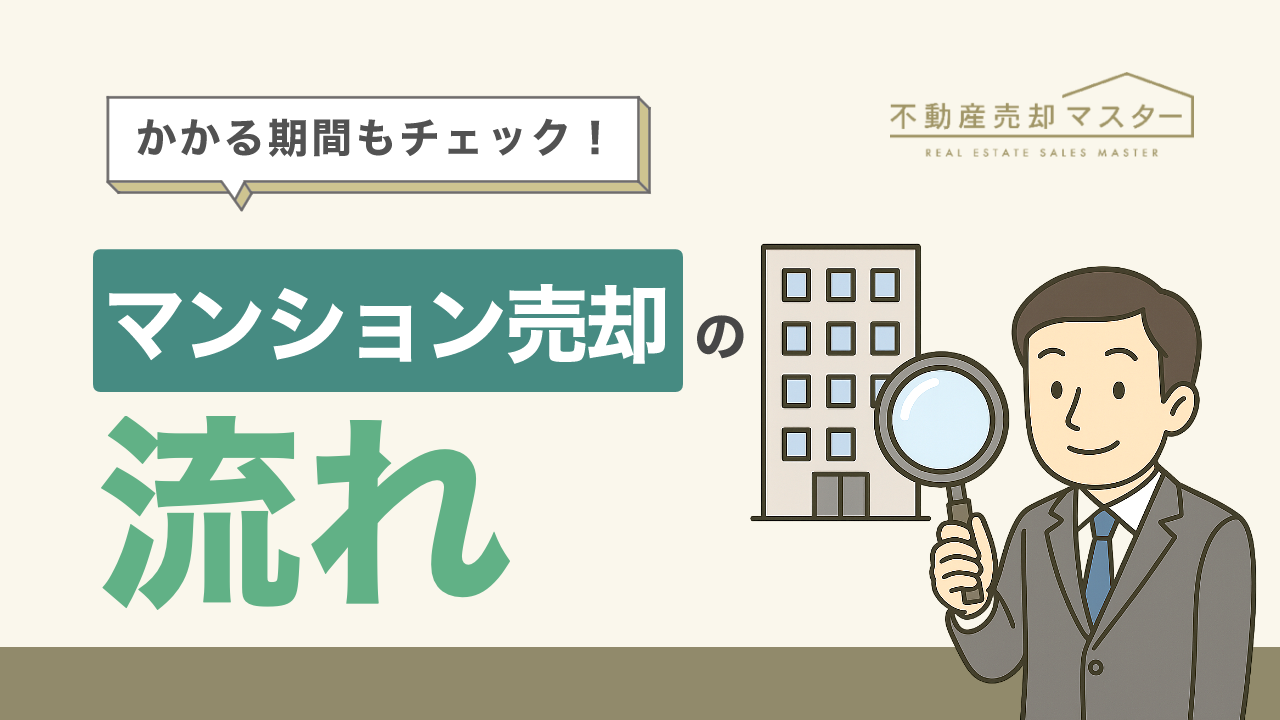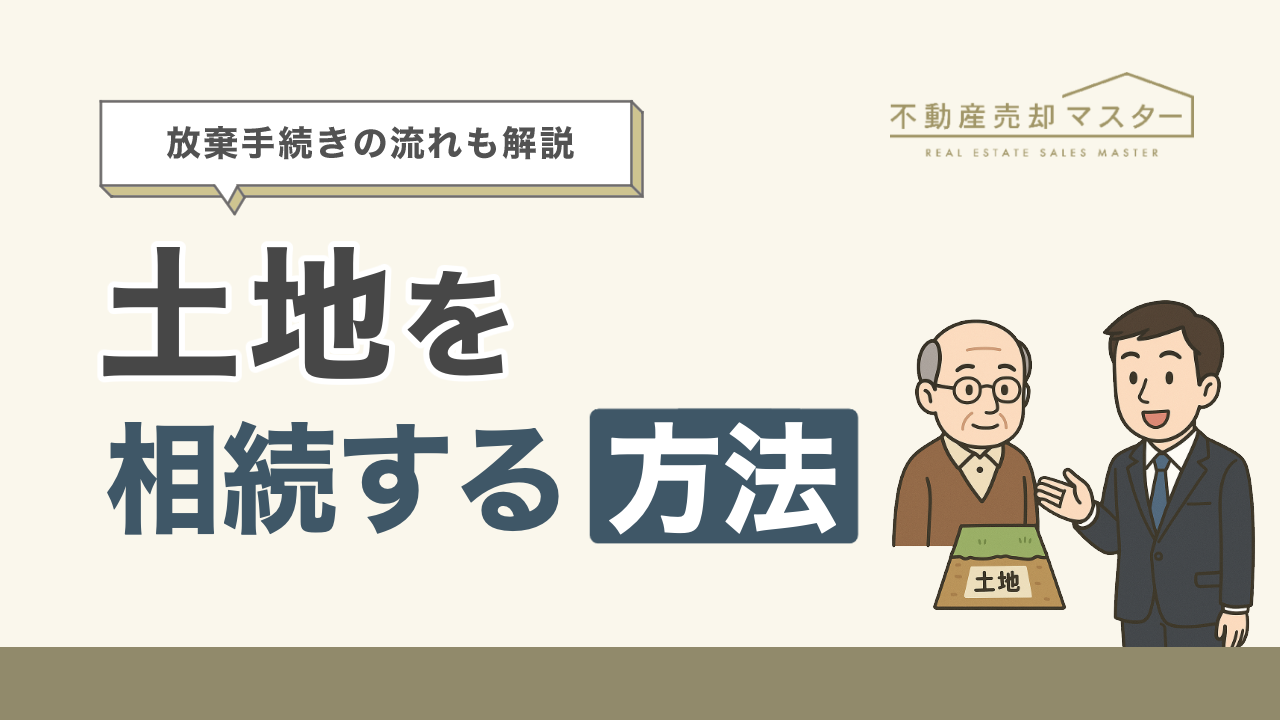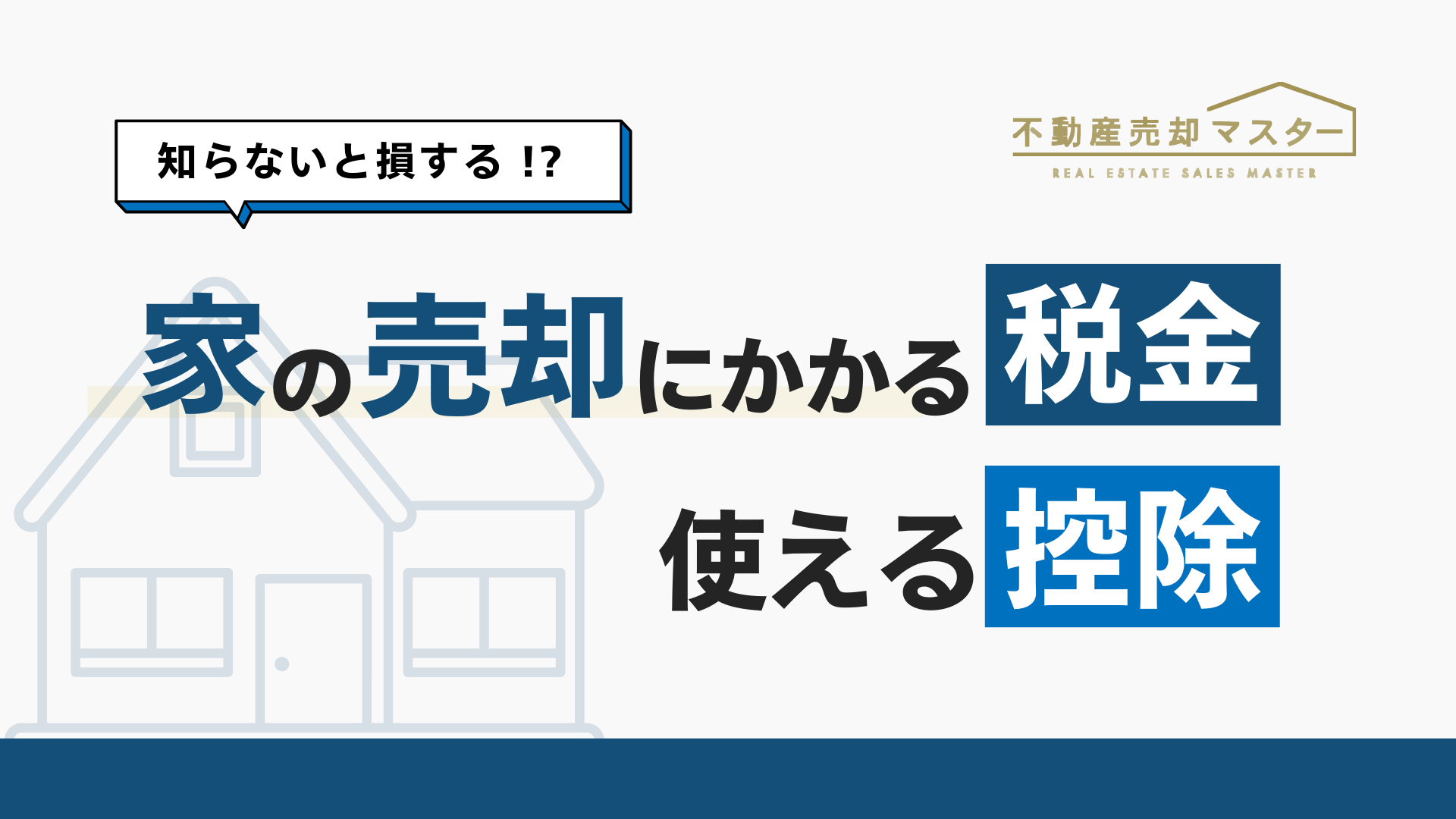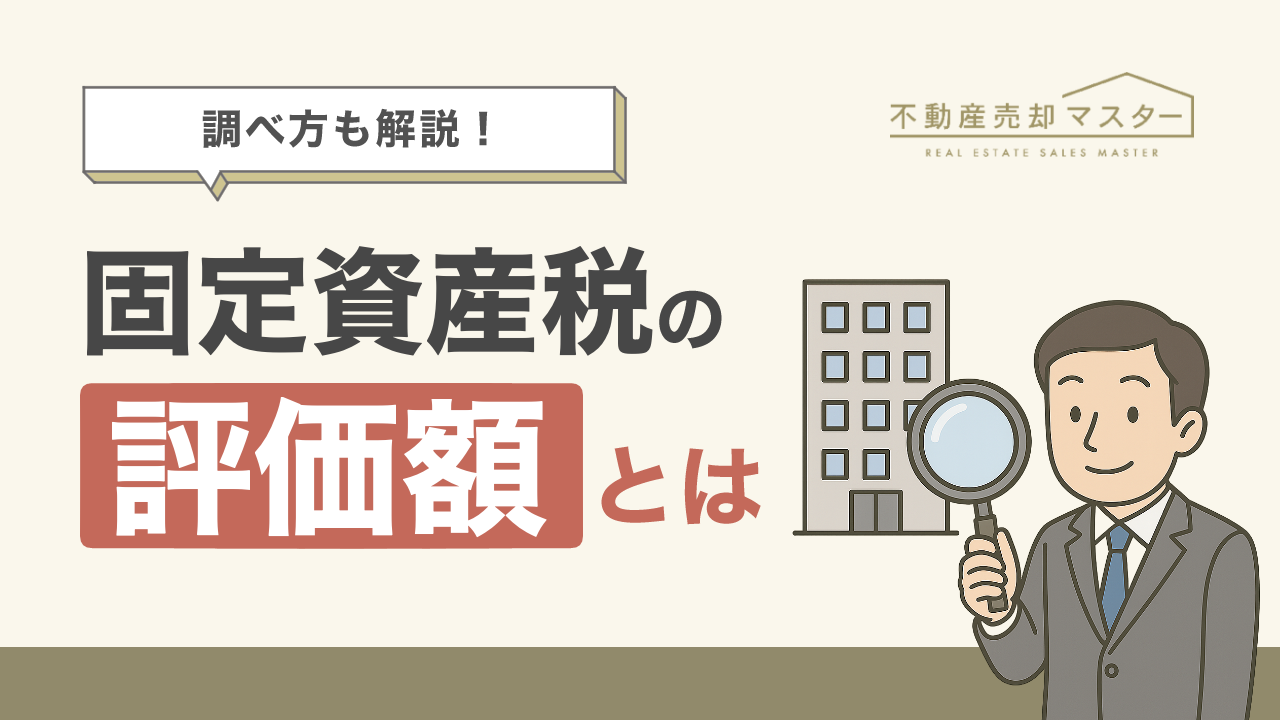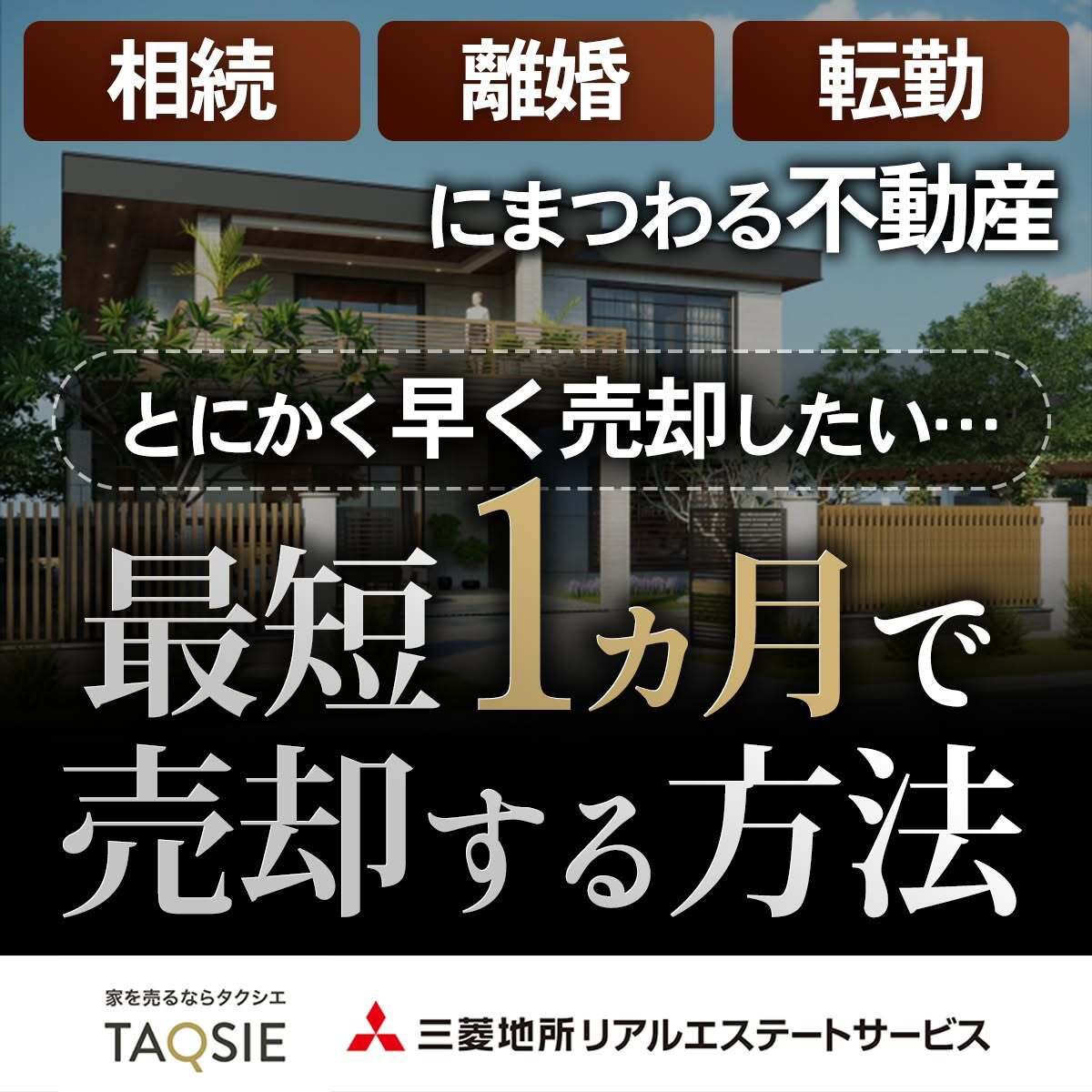マンションを所有していると固定資産税が課税されます。固定資産税は毎年納付しなければならず家計に影響を与えるため、マンション購入を検討する際には、マンションの固定資産税額の目安を把握しておくことが大切です。
本記事では、マンションの固定資産税の計算方法を紹介します。
- この記事を読むと分かること
-
- マンションの固定資産税額の目安
- マンションの固定資産税の計算方法
- マンションの固定資産税が上がるケース
家を売りたくなったらタクシエ
三菱地所リアルエステートサービスが
あなたのエリアで実績の多い不動産会社をご紹介!
チャットで完結OK!
しつこい営業電話はありません!
マンションの固定資産税額の目安

一般的に、マンションの固定資産税額は年間10万〜30万円程度です。税額は以下のようなさまざまな要因で変動します。
要因 | 税額への影響 |
|---|
築年数 | 築浅であるほど資産価値が高いため税額が上がる |
占有面積 | 面積広いほど課税対象面積が増えるため税額が高くなる |
設備の充実度 | 設備が充実しているほど税額が高くなる |
立地 | 地価が高いほど税額が高くなる |
マンションのほうが一戸建てよりも固定資産税が高くなる傾向にあります。マンションは鉄筋コンクリート造など耐久性の高い構造であるからです。
マンションの法定耐用年数が47年と長めに設定されており、築年数が経過しても建物評価額は急激には下がりにくい傾向です(※)。そのため、固定資産税の減額ペースも緩やかで、築年数が経っても税額があまり下がらないこともあります。
(※)「主な減価償却資産の耐用年数表」(国税庁)
固定資産税と都市計画税の違い

固定資産税と都市計画税の主な違いは、課税対象エリアと税率です。
税金の種類 | 固定資産税 | 都市計画税 |
|---|
課税対象エリア | 全国の土地・建物に対して課税 | 市街化区域内の土地・建物に対して課税 |
税率 | 1.4%(標準税率) | 上限0.3% |
参考:「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)」(東京都主税局)
固定資産税は、すべての土地・建物に対して課税される税金です。日本全国どこに不動産を所有していても納税義務があります。
一方、都市計画税は、都市計画によって指定された「市街化区域内」にある不動産に対して課税される税金です。マンションが市街化区域外にある場合、都市計画税は発生しません。
また、固定資産税の標準税率は1.4%です。それに対し、都市計画税の税率は0.3%が上限で、税率は自治体によって異なります。
▼関連記事
固定資産税とは?仕組みや支払時期、負担を減らす方法をわかりやすく解説
マンションの固定資産税の計算方法

マンションの固定資産税を算出する際は、土地と建物それぞれ分けて行います。固定資産税の計算方法を確認しておきましょう。
▼関連記事
固定資産税の計算方法は?一軒家・マンション・土地別にシミュレーションも紹介
土地の固定資産税の計算方法
土地に対する固定資産税は、以下の計算式で算出されます。
土地の固定資産税額=課税標準額 × 税率(原則1.4%) |
参考:「固定資産税」(総務省)
税額を決める際には、土地の評価額に軽減措置や調整措置を適用して算出された「課税標準額」が用いられます。居住用の土地には以下の特例が自動で適用され、課税標準額が軽減されます。
用地の区分 | 面積の条件 | 軽減内容 |
|---|
小規模住宅用地 | 200㎡以下の部分 | 評価額の6分の1を課税標準額とする |
一般住宅用地 | 200㎡を超える部分 | 課税標準額が評価額の3分の1を課税標準額とする |
参考:「固定資産税」(総務省)
そのため実質的な計算は、以下のように行われます。
土地の固定資産税額=(土地の評価額 × 特例率)× 税率(1.4%) |
参考:「固定資産税」(総務省)
建物の固定資産税の計算方法
建物の固定資産税額も以下の計算式で求めます。
建物の固定資産税額=課税標準額 × 税率(1.4%) |
参考:「固定資産税」(総務省)
課税標準額は、建物の評価額に軽減措置などを適用して調整された金額です。建物の評価額は、同等の建物を新築した場合にかかる再建築価格に、築年数に応じた経年減点補正率(価値の減少率)をかけて算出されます。
マンションの固定資産税が上がるケース

マンションの固定資産税が上がるケースは、以下の2つが挙げられます。
- 評価替えにより土地の価値が上がった場合
- 負担調整措置が取られている場合
それぞれの内容について解説します。
評価替えにより土地や建物の価値が上がった場合
評価替えによりマンションの土地と建物の価値が上昇した場合、マンションの固定資産税が増額する可能性があります。評価替えとは、総務大臣が定めた固定資産評価基準にもとづいて、土地と建物の評価額を見直すことです。評価替えは3年ごとに行われます。
固定資産税を算出する際に用いられる課税標準額は、固定資産評価額をもとに計算された金額なので、評価替えにより評価額が上昇すれば、固定資産税額も上がる仕組みです。
▼関連記事
固定資産税の評価額とは?調べ方や計算方法をわかりやすく解説
負担調整措置が取られている場合
評価額が据え置かれていても、負担調整措置の影響で固定資産税が上がるケースがあります。
負担調整措置とは、固定資産税の急激な増減を避けるために、税額の変動を段階的に調整する制度です。評価額が急上昇しても、負担調整措置により大幅な税額の増加にはならず、数年かけて税額が引き上げられることがあります。
マンションの固定資産税を軽減できる制度
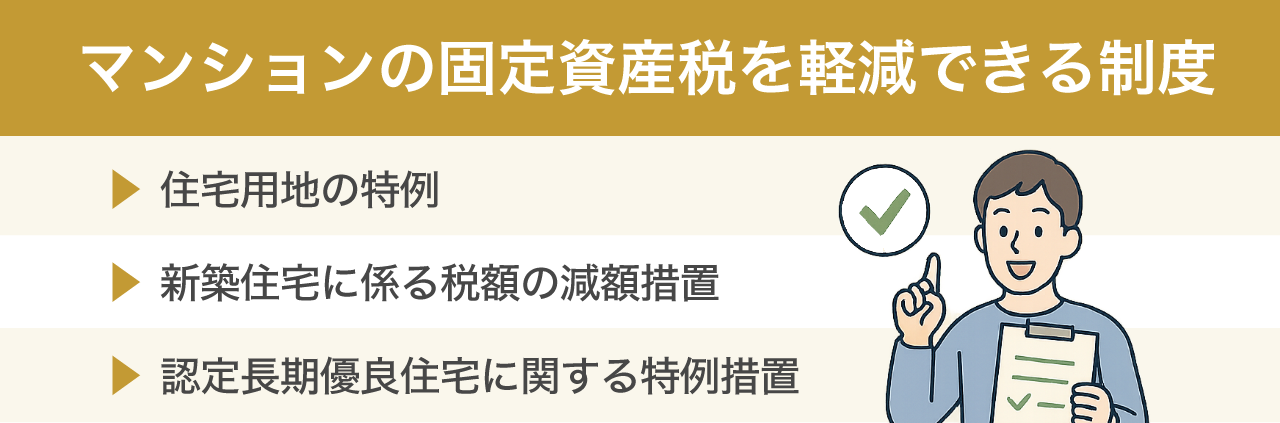
マンションの固定資産税を軽減できる制度には、以下のようなものがあります。
- 住宅用地の特例
- 新築住宅に係る税額の減額措置
- 認定長期優良住宅に関する特例措置
それぞれの優遇制度について解説します。
▼関連記事
不動産売却で生じる税金は?節税対策や確定申告が必要なケースも解説
住宅用地の特例
マンションの土地にかかる固定資産税は、住宅用地の特例を受けることで軽減されます。居住用として使用している土地には、以下の優遇措置が適用されます。
用地の区分 | 面積の条件 | 軽減内容 |
|---|
小規模住宅用地 | 200㎡以下の部分 | 評価額の6分の1を課税標準額とする |
一般住宅用地 | 200㎡を超える部分 | 課税標準額が評価額の3分の1を課税標準額とする |
参考:「固定資産税」(総務省)
マンションの敷地は、住戸ごとに決まった持ち分割合で共有されています。そのため、それぞれの住戸に対応する土地に住宅用地の特例が適用され、土地にかかる固定資産税が軽減されます。
新築住宅に係る税額の減額措置
新築住宅に係る税額の減額措置を受けることで、マンションの固定資産税の負担を抑えられます。新築住宅に係る税額の減額措置とは、一定の要件を満たす新築住宅に対して、建物部分の固定資産税額が2分の1に軽減される制度です(※)。
新築マンションの場合は5年間、減額措置が適用されます。主な適用要件は以下のとおりです。
- 2026年3月31日までに新築された住宅である
- 住宅部分の床面積が50㎡以上280㎡以下である(共同住宅は40㎡以上)
- 自分の居住用の住宅である
- 床面積の1/2以上が住宅として使用されている(居住と事務所などを兼ねた併用住宅の場合)
原則として減額措置は自動で適用されますが、自治体によっては申請が必要な場合もあるため確認しておきましょう。
(※)「新築住宅に係る税額の減額措置」(国土交通省)
認定長期優良住宅に関する特例措置
認定長期優良住宅に該当する新築マンションに居住している場合は、固定資産税の軽減期間が通常より延長され、7年間にわたり特例措置を受けられます(※)。
認定長期優良住宅とは、国が定めた耐震性・省エネ性・維持管理のしやすさなどの基準を満たし、所管行政庁から認定を受けた住宅です。
本特例は、居住用の住宅部分のみに適用されます。店舗や事務所を併設している部分や、自らが居住していない賃貸用の住戸は適用対象外です。
(※)「認定長期優良住宅に関する特例措置」(国土交通省)
【新築・中古別】マンションの固定資産税シミュレーション

ここからは、新築・中古別でマンションの固定資産税をシミュレーションしていきます。
- 2000万円の新築マンションの場合
- 3000万円の新築マンションの場合
- 4000万円の新築マンションの場合
- 5000万円の新築マンションの場合
- 築10年の中古マンションの場合
- 築20年の中古マンションの場合
- 築30年の中古マンションの場合
価格帯や築年数ごとにどれくらい税額の差があるのか見ていきましょう。
2,000万円の新築マンションの場合
以下の条件で、2,000万円の新築マンションを購入したケースで、概算の固定資産税をシミュレーションします。
- 建物価格:1,200万円
- 土地価格:800万円
- 購入費用総額:2,000万円
- 建物の固定資産評価額:建物価格の70%
| | 税額(特例なし) | 税額(新築特例あり) |
|---|
土地 | 約11.12万円(800万円 × 1.4%) | 約11.12万円 |
建物 | 約11.76万円 建物評価額:1,200万円 × 70%=840万円 固定資産税額:840万円 × 1.4% = 約11.76万円 | 約5.88万円(2分の1に軽減) |
合計 | 約22.88万円/年 | 約17.00万円/年 |
上記の例の場合、固定資産税額は約22.88万円/年です。新築住宅に係る税額の減額措置が適用される5年間は、固定資産税が約17.00万円/年になります。減額措置の適用期間を考慮して、将来の税負担を見据えた資金計画を立てましょう。
3,000万円の新築マンションの場合
以下の条件で、3,000万円の新築マンションを購入したケースの固定資産税額を見ていきましょう。
- 建物価格:1,800万円
- 土地価格:1,200万円
- 購入費用総額:3,000万円
- 建物の固定資産評価額:建物価格の70%
| | 税額(特例なし) | 税額(新築特例あり) |
|---|
土地 | 約16.8万円(1,200万円 × 1.4%) | 約16.8万円 |
建物 | 約17.64万円 建物評価額:1,800万円 × 70%=1,260万円 固定資産税額;1,260万円 × 1.4% = 約17.64万円 | 約8.82万円(2分の1に軽減) |
合計 | 約34.44万円/年 | 約25.62万円/年 |
築6年目以降は建物の軽減措置が終わり、税額は約34.44万円に戻ります。
4,000万円の新築マンションの場合
以下の条件で、4,000万円の新築マンションを購入したケースの固定資産税額を見ていきましょう。
- 建物価格:2,400万円
- 土地価格:1,600万円
- 購入費用総額:4,000万円
- 建物の固定資産評価額:建物価格の70%
| | 税額(特例なし) | 税額(新築特例あり) |
|---|
土地 | 約22.4万円(1,600万円 × 1.4%) | 約22.4万円 |
建物 | 約23.52万円 建物評価額:2,400万円 × 70%=1,680万円 固定資産税額:1,680万円 × 1.4% = 約23.52万円 | 約11.76万円(2分の1に軽減) |
合計 | 約45.92万円/年 | 約34.16万円/年 |
新築住宅に係る税額の減額措置を受けても、固定資産税額は年間約34.16万円と高額です。マンションの購入時は、将来的な税負担も考慮することが大切です。
5,000万円の新築マンションの場合
以下の条件で、5,000万円の新築マンションを購入したケースの固定資産税額を見ていきましょう。
- 建物価格:3,000万円
- 土地価格:2,000万円
- 購入費用総額:5,000万円
- 建物の固定資産評価額:建物価格の70%
| | 税額(特例なし) | 税額(新築特例あり) |
|---|
土地 | 約28万円(2,000万円 × 1.4%) | 約28万円 |
建物 | 約29.4万円 建物評価額:3,000万円 × 70%=2,100万円 固定資産税額;2,100万円 × 1.4% = 約29.4万円 | 約14.7万円(2分の1に軽減) |
合計 | 約57.4万円/年 | 約42.7万円/年 |
上記の例の場合、約57.4万円/年の固定資産税がかかります。高価格帯のマンションでは、減額措置終了後の固定資産税の負担がより大きいため、長期的な支出を見据えておくことが重要です。
築10年の中古マンションの場合
以下の条件で、築10年の中古マンションの固定資産税額を見ていきましょう。
- 建物価格:1,800万円
- 土地価格:1,200万円
- 購入費用総額:3,000万円
- 新築時の建物評価額:1,260万円(建物価格の70%)
- 築10年時の建物評価額:新築時評価額の65%
- 土地の評価額は据え置き
| | 築10年後の評価額 | 固定資産税額 |
|---|
土地 | 1,200万円 | 約16.8万円(1,200万円 × 1.4%) |
建物 | 約819万円(1,260万円 × 65%) | 約11.47万円(819万円 × 1.4%) |
合計 | ー | 約28.27万円/年 |
上記の例の場合、固定資産税額は約28.27万円/年です。築10年の中古マンションでは、建物評価額が新築時より下がるため固定資産税の負担が軽減されます。ただし、土地の税額は変わらず、全体の税負担の多くを土地部分が占めます。
築20年の中古マンションの場合
以下の条件で、築20年の中古マンションの固定資産税額を見ていきましょう。
- 建物価格:1,800万円
- 土地価格:1,200万円
- 購入費用総額:3,000万円
- 新築時の建物評価額:1,260万円(建物価格の70%)
- 築20年時の建物評価額:新築時評価額の45%
- 土地の評価額は据え置き
| | 築20年後の評価額 | 固定資産税額 |
|---|
土地 | 1,200万円 | 約16.8万円(1,200万円 × 1.4%) |
建物 | 約567万円(1,260万円 × 45%) | 約7.94万円(567万円 × 1.4%) |
合計 | ー | 約24.74万円/年 |
上記の例の場合、約24.74万円/年の固定資産税が発生します。築20年の中古マンションでは、築年数の経過によって建物の評価額は新築時の半分程度になるため、税額が大幅に下がります。
築30年の中古マンションの場合
以下の条件で、築30年の中古マンションの固定資産税額を見ていきましょう。
- 建物価格:1,800万円
- 土地価格:1,200万円
- 購入費用総額:3,000万円
- 新築時の建物評価額:1,260万円(建物価格の70%)
- 築30年時の建物評価額:新築時評価額の35%
- 土地の評価額は据え置き
| | 築30年後の評価額 | 固定資産税額 |
|---|
土地 | 1,200万円 | 約16.8万円(1,200万円 × 1.4%) |
建物 | 約441万円(1,260万円 × 35%) | 約6.17万円(441万円 × 1.4%) |
合計 | ー | 約22.97万円/年 |
上記の場合における固定資産税額は、約22.97万円/年です。築30年ともなると、建物の評価額は新築時の3分の1程度になるため、税負担はさらに軽減されます。
ただし、築30年以上になると建物部分の評価額は下げ止まっている傾向にあります。そのため、固定資産税額は大きく下がりにくくなるでしょう。
マンションの固定資産税の納付時期・納付方法
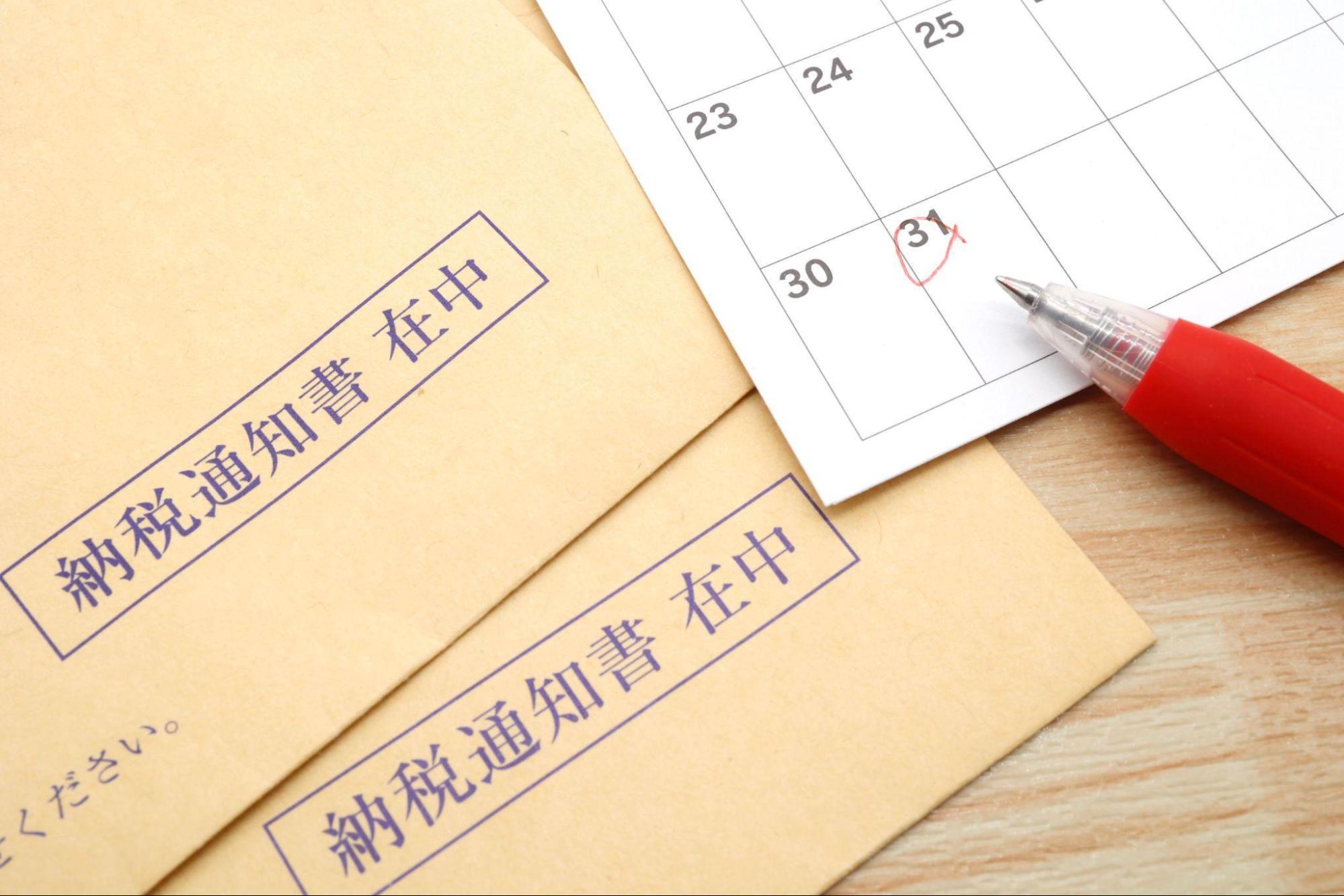
マンションの固定資産税は、年4回の分割納付または一括で納付できます。分割納付の期日は自治体によって異なりますが、以下のようなスケジュールが一般的です。
- 6月(第1期)
- 9月(第2期)
- 12月(第3期)
- 翌年2月(第4期)
毎年4〜6月頃に納税通知書が送付され、第1期から順次納付します。一括納付を選択した場合は、第1期に全額を納付します。固定資産税の主な納付方法は、以下のとおりです。
- 口座振替
- クレジットカード決済
- スマホ決済(PayPay、LINE Payなど)
- eLTAX(地方税共通納税システム)による電子納税
- 金融機関やコンビニでの現金払い
納税を怠ると延滞金が発生するため、期限内に納付しましょう。
固定資産税が負担ならTAQSIE(タクシエ)に売却相談を!
マンションの固定資産税は、建物や土地の評価額にもとづいて決まり、築年数や立地などによって税額が大きく変動します。そのため、長期的な支出を見据えて資金計画を立てることが大切です。
現在所有している不動産の固定資産税が負担に感じ、売却をしてマンション購入を検討している場合は、不動産買取・仲介担当者とのマッチングサービス「TAQSIE(タクシエ)」をご利用ください。
大手不動産会社84社の中から厳選した、不動産売却のプロを3名ご紹介いたします。無料で会員登録でき、チャットで気軽に売却相談できるので、ぜひご活用ください。
三菱地所リアルエステートサービス 新事業推進部
「不動産売却マスター」編集長
【保有資格】宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、衛生管理者、ファイナンシャルプランナー3級
2008年入社。人事部門で福利厚生制度などの企画運営、住宅賃貸部門でタワーマンション営業所長、高級賃貸マンション企画などを経て、2018年より経営企画部で主に事業開発を担当し、複数の新規事業立上げに従事。2020年度三菱マーケティング研究会ビジネスプランコンテスト最優秀賞受賞。「TAQSIE」では初期構想から推進役を担い、現在もプロジェクト全般に関わっている。
「不動産の売却に特化した情報を発信する『不動産売却マスター』編集部です。不動産の売却や買取をスムーズに進めるポイントや、税金、費用などをわかりやすく解説します」
あなたのケースにあった
ご成約者の声を見てみる
絞り込む