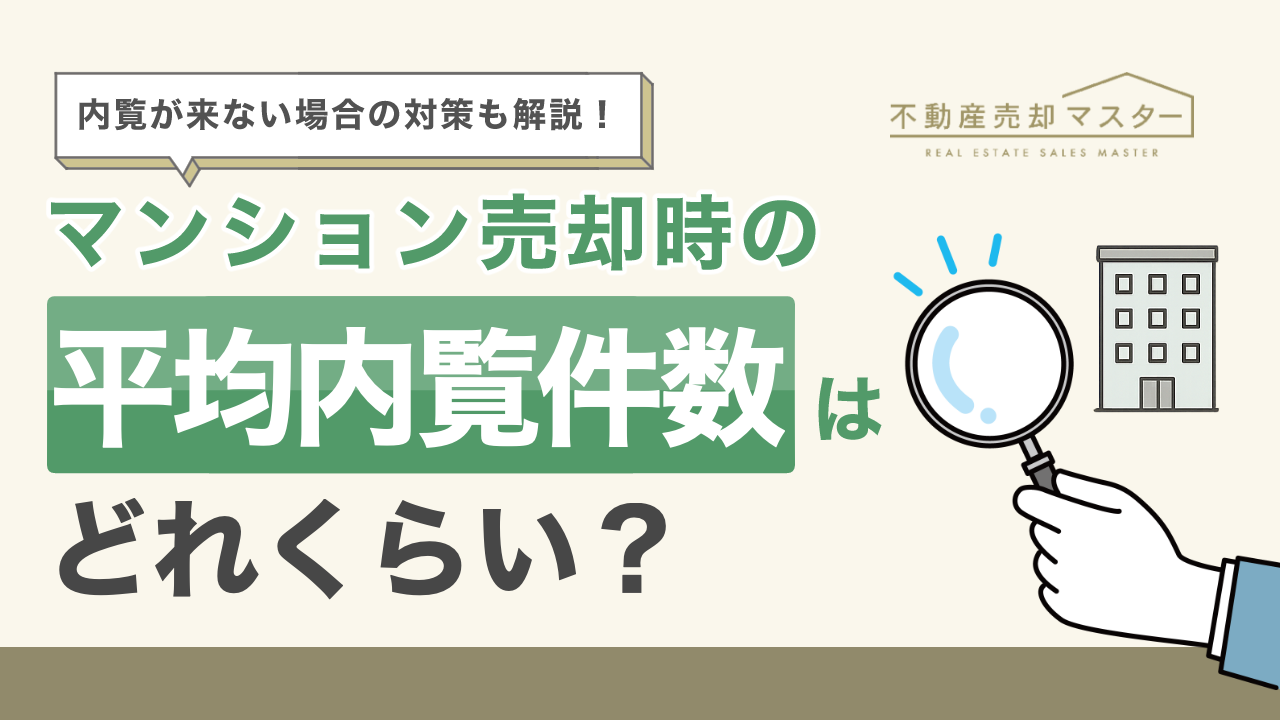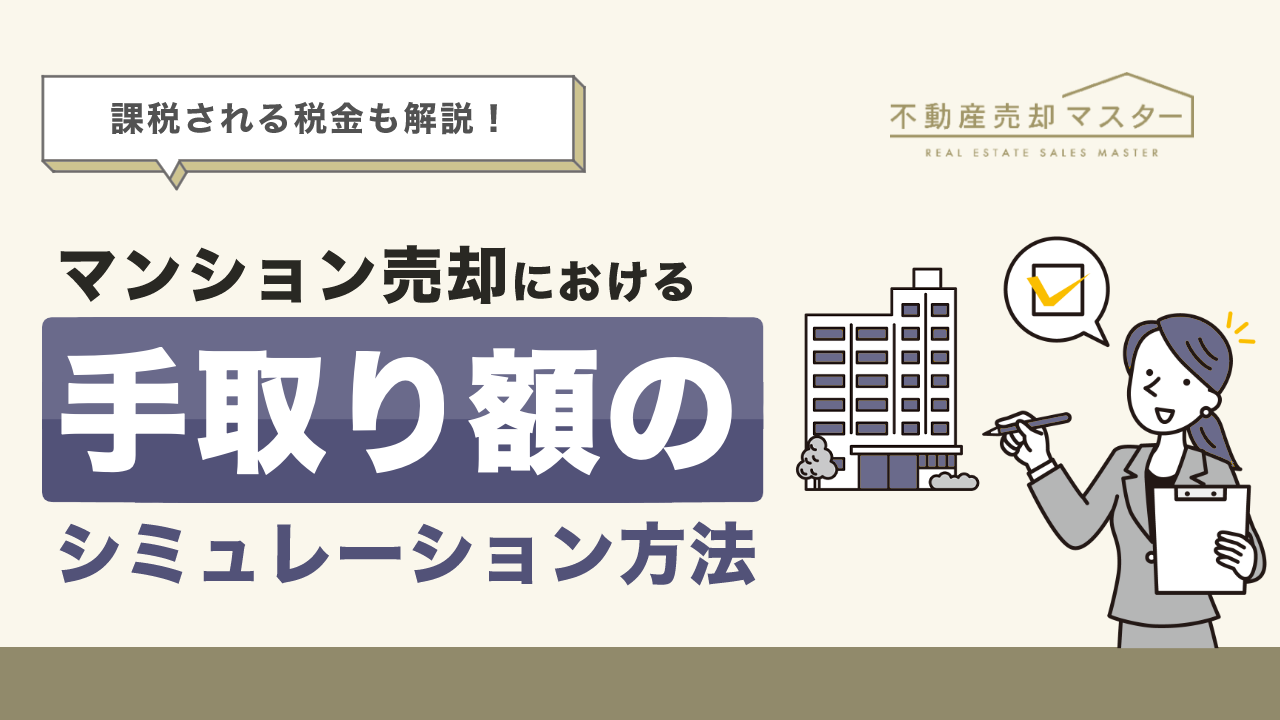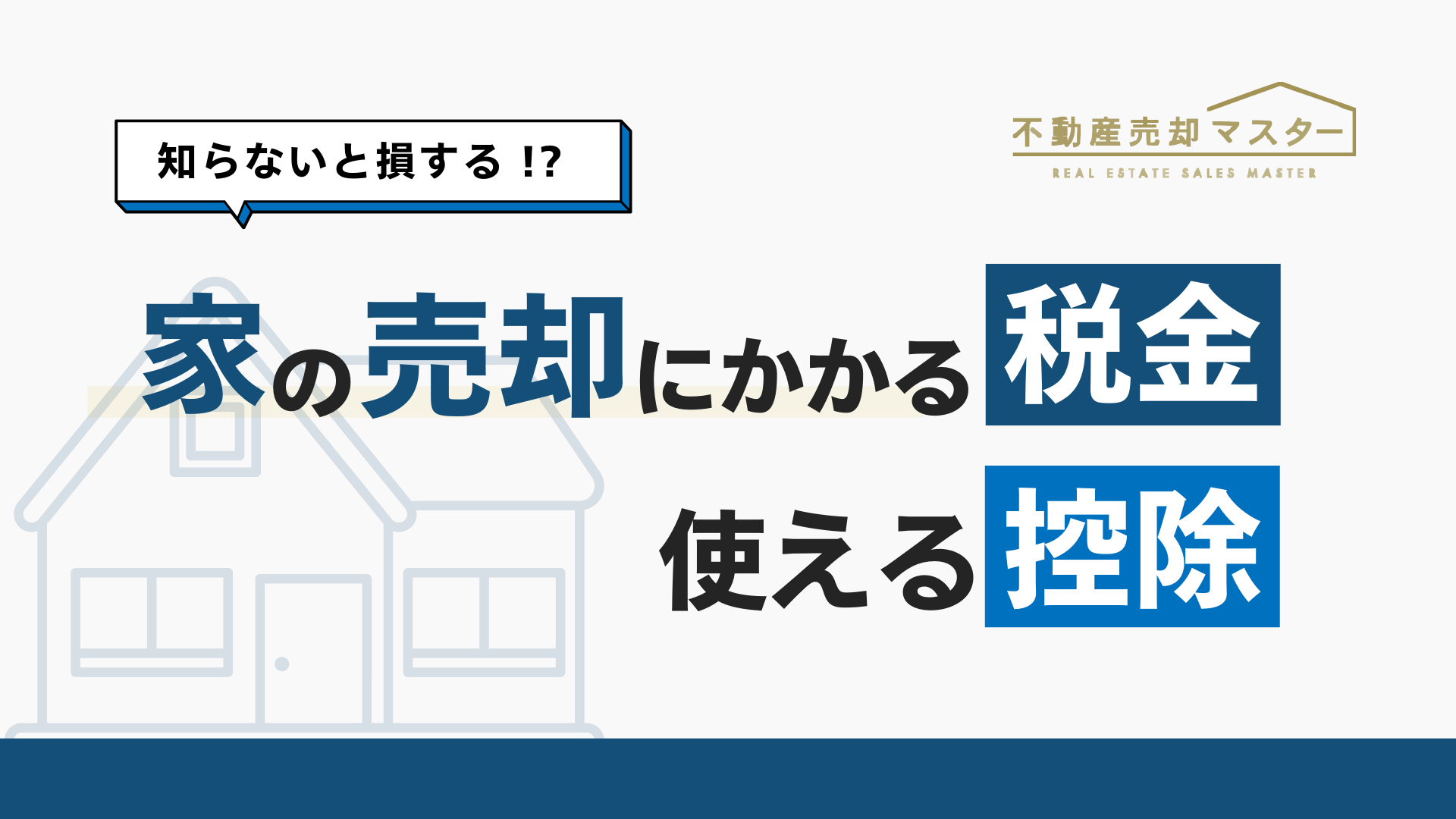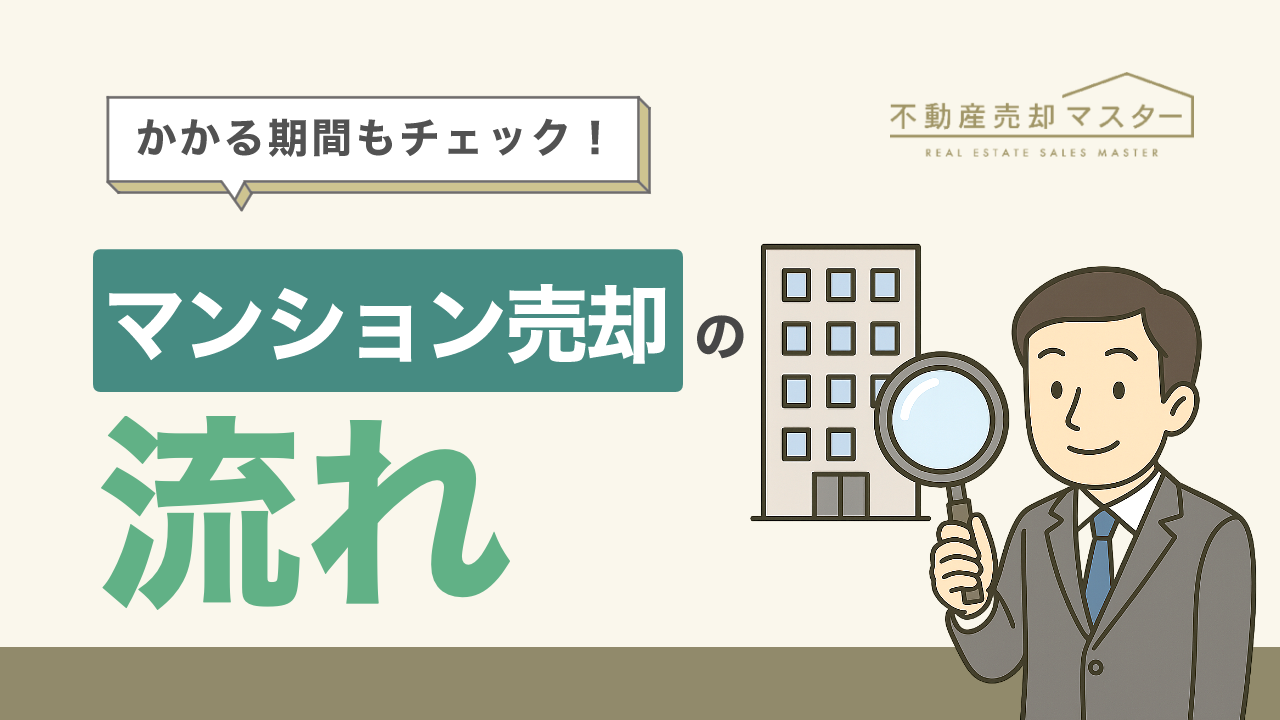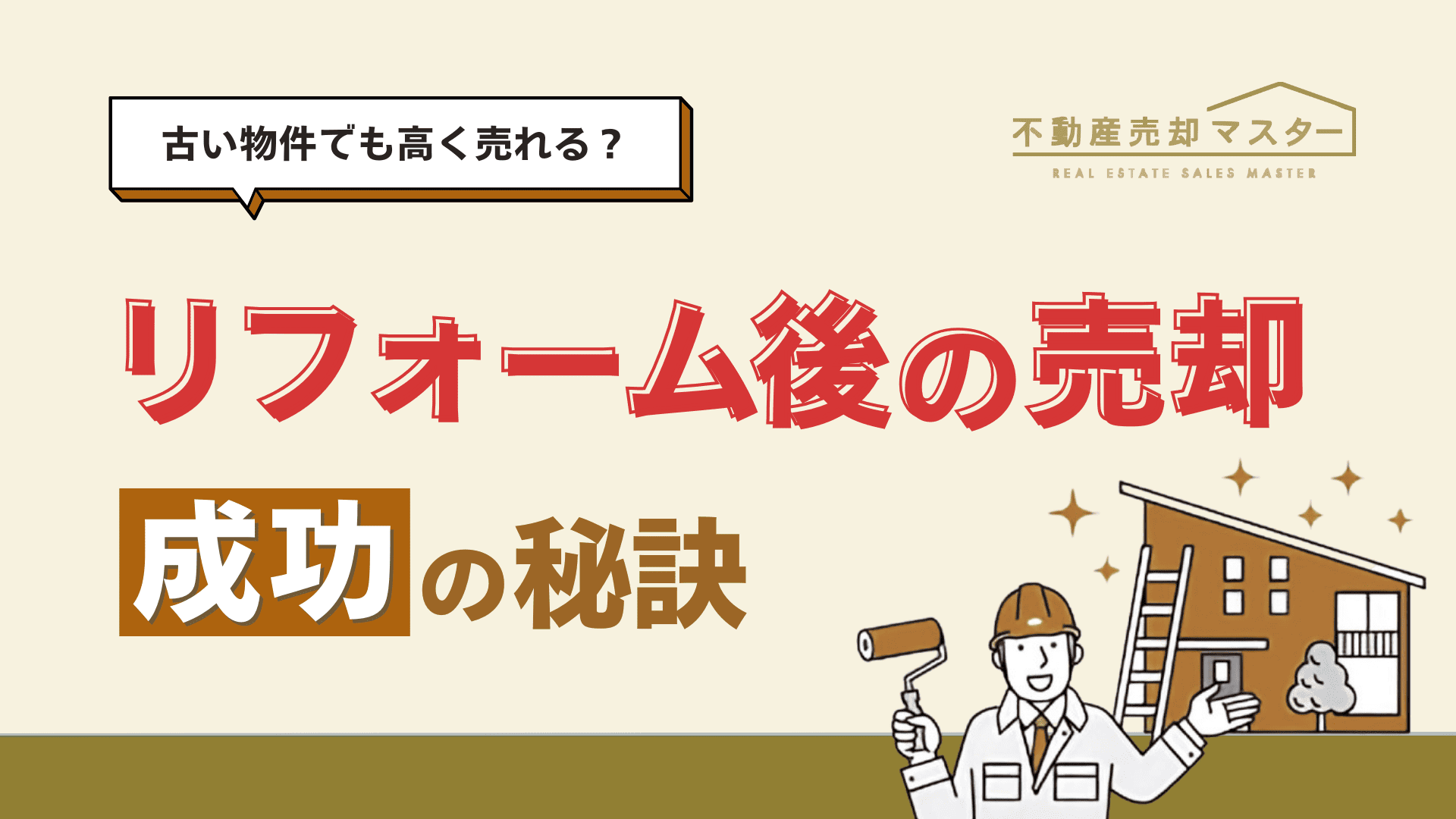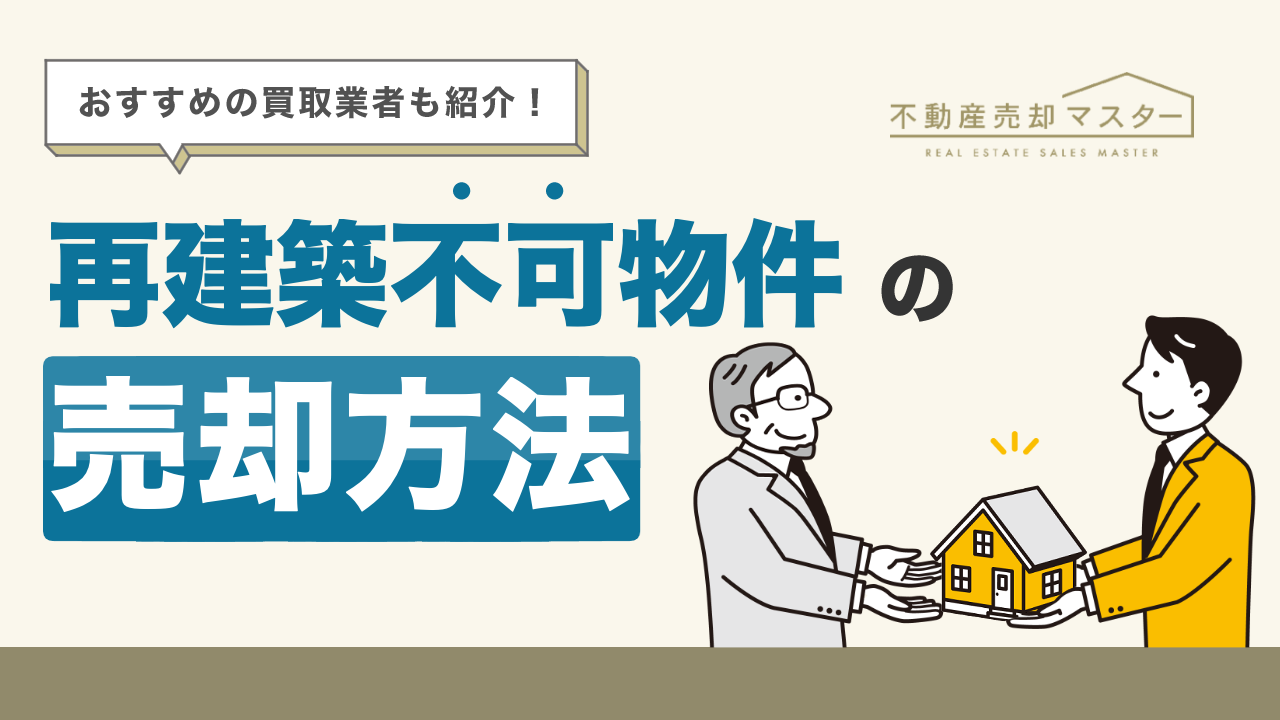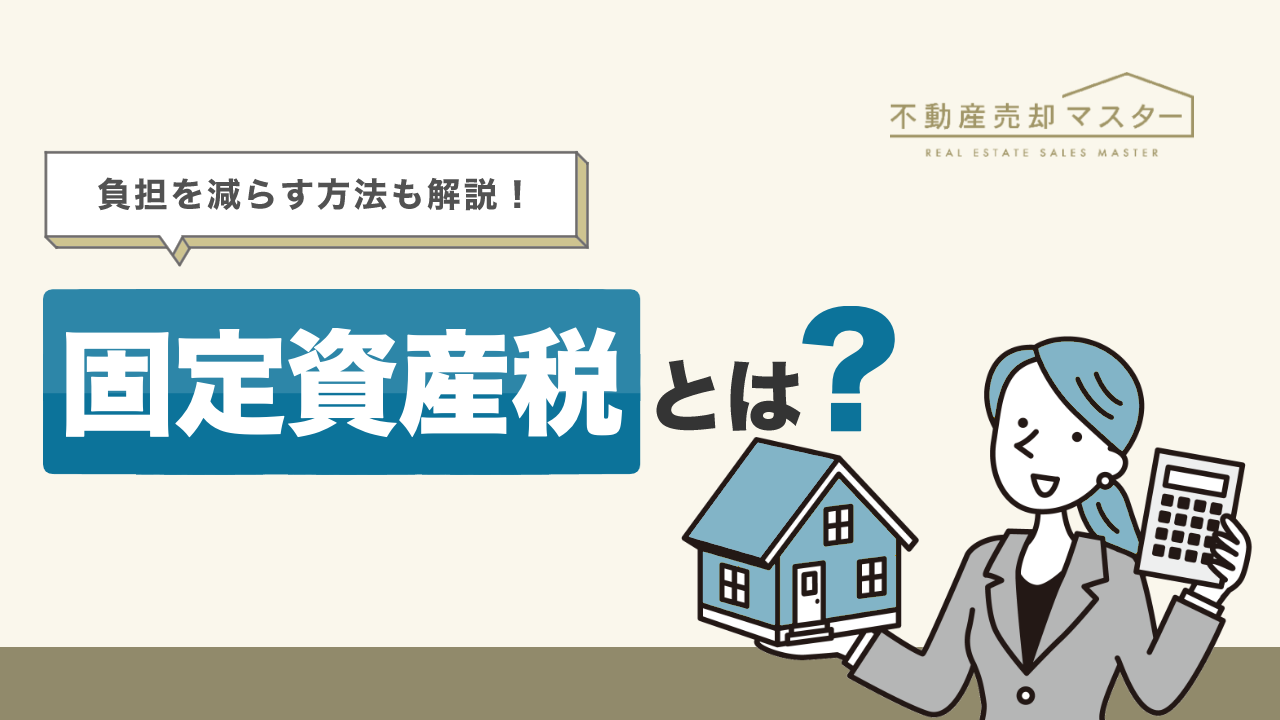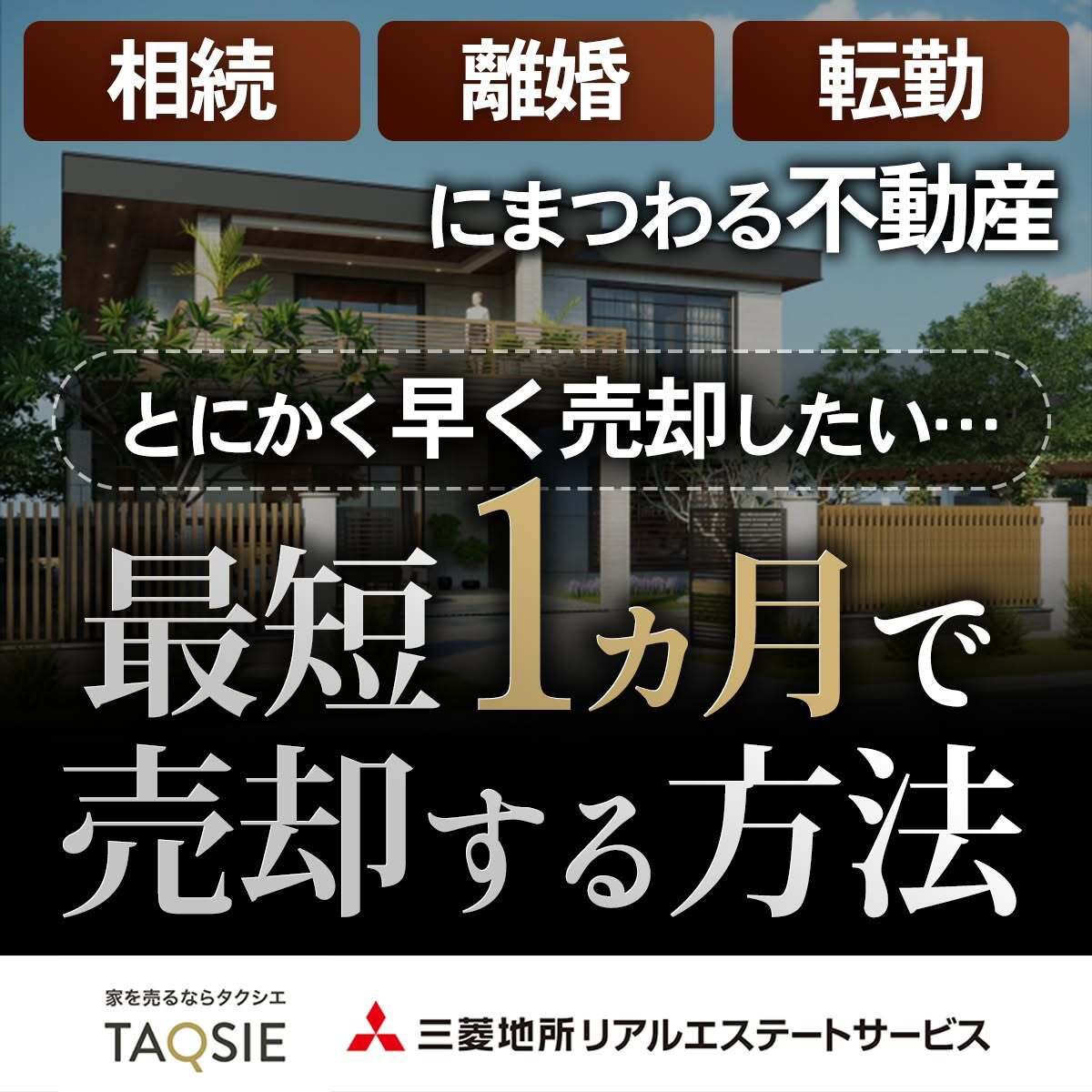農地を売却したいと考えていても、実際の売却までにはいくつかの重要なステップと制限があります。農地法による規制や、農業委員会の許可取得など、一般の不動産売却とは異なる独自の手続きが必要となります。
農地の売却方法には、農地のまま売却する方法と宅地などに転用して売却する方法があります。それぞれのアプローチには固有のメリットとデメリットがあり、状況に応じて最適な選択肢を検討する必要があります。
売却を成功させるためには、農地法の理解から必要な許可申請、適切な買い手の選定まで慎重に進めていく必要があります。この記事では、農地売却に関する重要な情報とスムーズな売却のためのポイントについて詳しく解説していきます。
- この記事を読むと分かること
-
- 農地法の厳しい制限により、簡単には売却できない
- 農地のまま売るか転用して売るかの2つの方法があるが、それぞれに手続きが必要
- 転用には農業委員会の許可と3〜6ヶ月程度の時間を要する
家を売りたくなったらタクシエ
三菱地所リアルエステートサービスが
あなたのエリアで実績の多い不動産会社をご紹介!
チャットで完結OK!
しつこい営業電話はありません!
農地は売却することが難しい

農地の売却を考えている方にとって、最初の関門となるのが厳しい法規制の存在です。農地は一般の不動産とは異なり、農地法による様々な制限が設けられているため、売却までの道のりは複雑になります。
最初のステップとして、地域の農業委員会に相談し、所有する農地の区分や適用される規制の確認を行います。農地区分によって転用の可否や手続きの複雑さが異なってくるためです。
次に、必要書類の収集や測量の手配など具体的な準備に入ります。この段階で不動産の専門家や行政書士への相談も検討しましょう。専門家のサポートを得ることで、適切な売却方法の選択や手続きの円滑な進行が期待できます。
売却完了までの期間は、通常の土地売却であれば3〜6ヶ月程度で売却できますが、農地の場合は売却できる人に制限があるため、通常よりも時間がかかる可能性があります。
また転用を伴う場合は6ヶ月から1年程度を見込む必要があります。転用には許可が必要になるため、普通の土地売却よりも時間がかかります。
上記の点から、農地を売却することは難しいとされていますが、適切な手順を踏んで進めることで売却まで進めることができます。
▼関連記事
土地が売れない6つの理由・特徴を解説!手放したいときの対処法やおすすめの買取業者も紹介
旗竿地が売れない理由は?売却のコツ・注意点、売れる旗竿地の特徴
農地法で制限されている
農地法による売却制限は、主に売却先と利用目的に関するものです。2023年(令和5年)4月1日以前は、農家・農業従事者のみでしか売買が行えませんでしたが、農地法の一部改正により、農地の売却先は原則として、「その土地で農業を営む意思と能力のある個人または法人」までが対象となりました。
農地法とは
農地法とは、農地の保全と効率的な利用を目的として1952年に制定された法律です。この法律は、農地の売買や賃借を制限し、所有権の移転には原則として農業委員会の許可を必要とします。また、農地から宅地などへの転用も規制されており、無秩序な農地転用や転売を防止する仕組みを設けています。農地法の基本理念は、農地は農業従事者によって所有・利用されるべきという考えに基づいており、国内の農業生産基盤を守る重要な役割を果たしています。
以下は農地法で制限される主な内容となります。
| 制限項目 |
内容 |
詳細 |
| 農地転用の規制 |
農地を農地以外の用途に変更する際の制限 |
・宅地や工場用地への転用には許可が必要
・国民・地域の貴重な資源として保護 |
| 権利取得の制限 |
農地取得に関する許可制 |
・農業委員会の許可が必要
・下限面積要件あり
・地域との調和要件あり |
| 利用関係の調整 |
貸借・売買・利用権に関する規制 |
・貸借期間は最長50年
・農協による農業経営は組合員合意で可能 |
| 遊休農地対策 |
未利用農地への対応措置 |
・農業委員会による指導・通知・勧告
・都道府県知事による裁定制度
・所有者不明農地の利用制度 |
| 権利者の責務 |
所有者・賃借者の義務 |
・適正かつ効率的な利用の確保
・法改正で新設された規定 |
このような制限は、一見厳しく感じられるかもしれませんが、適切な手続きを踏むことで売却が可能となっています。ただ制限のない土地売却と比較すると、売るまでの道のりが難しいと感じるケースも多いでしょう。
宅地転用するにも農業委員会の許可が必要
農地を宅地などに転用して売却する場合、農業委員会の許可取得が重要なステップとなります。一般的な許可取得までの期間は案件の複雑さにもよりますが、最低でも6ヶ月程度を見込む必要があるでしょう。
【許可取得の一般的な流れ】
- 事前相談(約1〜2週間)
- 申請書類の作成(約2〜4週間)
- 農業委員会での審査(約1〜2ヶ月)
- 都道府県知事による審査(約1〜2ヶ月)
- 許可書の発行(約1〜2週間)
※上記に記載されている期間はあくまで目安となります。実際のケースと異なる可能性がございます。
次項で詳しく説明しますが、農地区分が第3種農地である場合(市街化区域内の農地や、周辺に住宅地が広がっている)は、比較的許可が得やすい傾向にあるとされています。
第3種農地以外は原則転用が難しい
農地区分の違いは、売却の可能性に大きく影響を与える要素となっています。第3種農地は市街地に近接し、都市施設の整備が進んでいる区域に位置する農地を指します。これに対して、第1種農地や第2種農地は、優良な農地として保護される傾向が強いとされています。
以下は農地区分と、その特徴になります。
| 農地区分 |
特徴 |
| 第1種農地 |
優良な農地として厳重に保護 |
| 第2種農地 |
周辺の土地利用状況から転用が検討可能 |
| 第3種農地 |
原則として転用が認められやすい |
| 農用地区域 |
原則として転用が認められない |
自身の農地がどの区分に該当するかは、地域の農業委員会に確認するとよいです。
農地を売却するための方法

農地を売却する方法は、大きく分けて「農地のまま売却」と「転用して売却」の2つの選択肢があります。農地の立地や特性、売却の目的によって、最適な方法を選択する必要があります。
以下の表にメリット・デメリットをまとめましたので、参考にしてください。
| 売却方法 |
メリット |
デメリット |
| 農地のまま売却 |
・手続きが比較的簡単
・短期間で売却可能 |
・売却価格が低め
・買い手が限定的 |
| 転用して売却 |
・高値での売却が可能
・買い手の範囲が広い |
・手続きが複雑
・費用と時間がかかる |
農地のまま売却する場合は、農業従事者や農業法人が主な買い手となります。この場合、農地法の規定に基づき、農業委員会の許可を得る必要があります。比較的手続きがシンプルで、短期間での売却が可能です。ただし、売却価格は宅地などと比べて低くなる傾向があります。
一方、転用して売却する場合は、より高値での売却が期待できますが、農業委員会の許可取得や各種申請など、複雑な手続きが必要となります。転用の種類(住宅地、商業地など)によって必要な手続きが異なり、完了までにより長い期間を要することが一般的です。
どちらの方法を選ぶかは、農地の立地条件や区分、周辺環境、売却の緊急性などを総合的に判断して決める必要があります。特に農地区分は重要で、上記見出しで紹介した通り、第3種農地は比較的転用が認められやすい一方、第1種農地や農用地区域は転用が制限される傾向にあります。実際の売却方法の選択には、地域の農業委員会や不動産の専門家に相談することをお勧めします。
▼関連記事
土地売却の流れを紹介!税金対策や高額売買するためのポイントなども解説
土地売却・査定の流れを解説!査定額を決める要素や成功ポイントも紹介【2024年最新版】
土地買取の成功ガイド!買取相場や不動産会社の探し方、高値買取のコツなどを解説
農地のまま売却する
農地のまま売却する場合、農業従事者や農業法人が主な買い手となります。農地法の規定により、買い手となれるのは農業経営に意欲と能力のある個人または法人に限定されています。
売却の手順は以下の流れで進めていきます。
| 手順 |
具体的な内容 |
必要な対応 |
| 事前相談 |
農業委員会での確認 |
売却条件の整理 |
| 買い手探し |
複数の手法で募集 |
広域での周知 |
| 許可申請 |
法的手続きの実施 |
書類準備と提出 |
最初に農業委員会への相談を行い、農地の状況確認と売却要件を把握します。その後、農地の現況証明や登記事項証明書など必要書類を収集し、同時に農地バンクへの登録や農協への相談を行い、買い手候補を募ります。近隣の農家や地域の農業法人にも売却情報を周知することで、より多くの候補者と接触できます。
買い手が決まったら、農業委員会への許可申請を行います。この際、買い手の営農計画書や耕作証明書なども必要となります。農地法第3条に基づく許可基準を満たしていることを確認し、必要書類を整えて申請を行います。許可が下りれば、売買契約の締結と所有権移転登記の手続きへと進みます。
手続き全体を通じて、法的要件の遵守と適切な書類作成が重要です。不明な点がある場合は、行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。
農地転用して売却する
農地転用による売却は、より高値での売却が期待できる一方で、複雑な手続きと時間が必要となります。転用の種類によって必要な手続きや許可要件が異なってきます。
| 転用目的 |
主な用途 |
重要な確認事項 |
| 住宅地 |
個人住宅・宅地分譲 |
周辺の住宅状況 |
| 商業地 |
店舗・事務所 |
都市計画との整合性 |
| 工業地 |
工場・倉庫 |
環境への影響 |
| 公共施設 |
学校・病院 |
地域の需要 |
転用申請の手続きは、まず農業委員会への事前相談から始まります。この段階で、転用の可能性や必要な書類について確認することができます。転用申請には、土地の測量や各種調査、申請書類の作成など、多くの準備が必要となります。特に重要なのが、その土地が属する農地区分の確認です。第3種農地は比較的転用が認められやすい一方、第1種農地や農用地区域では転用が制限される傾向にあります。
申請時には、転用の必要性や周辺農地への影響、土地利用計画の妥当性などについて、詳細な説明が求められます。また、都市計画法や建築基準法など、農地法以外の法令との整合性も確認する必要があります。このような複雑な手続きを確実に進めるためには、行政書士や不動産の専門家への相談が推奨されます。
転用後の用途は、その地域の都市計画や周辺環境との整合性を考慮して決定します。特に、周辺の土地利用状況や地域の将来的な発展計画との調和が重要な判断基準となります。また、転用後の土地利用が確実に実現できることを示すため、具体的な事業計画の提出も必要となります。
農地売却の注意点

農地の売却には、一般の不動産売却とは異なる独自の注意点があります。売却を成功させるためには、主に時間、価格、手続きの3つの観点で、事前の理解と準備が必要となります。
| 注意点 |
主な課題 |
対応策 |
| 売却期間 |
・許可取得に時間を要する
・買い手探しに時間がかかる |
・早期の準備
・専門家への相談 |
| 価格面 |
・宅地より価格が低い |
・適切な価格設定
・複数の売却方法検討 |
| 法的手続き |
・複数の許可が必要
・書類作成が複雑 |
・専門家の活用
・事前の情報収集 |
まず、売却準備の段階で重要となるのが、農地区分の確認と売却方法の決定です。農地区分によって転用の可能性が変わってくるため、地域の農業委員会に早めに相談することが推奨されます。また、農地のまま売却するか転用して売却するかの判断もこの段階で行う必要があります。
次に、適切な専門家の選定も重要です。農地売却では、農業委員会への相談だけでなく、不動産の専門家や行政書士など、複数の専門家のサポートが必要となる場合があります。特に転用を検討する場合は、手続きが複雑になることから、専門家との早期の連携が望ましいでしょう。
さらに、売却条件の設定には、立地条件や周辺環境、地域の農地取引の相場など、多くの要素を考慮する必要があります。これらの情報収集と分析にも、専門家のアドバイスが有効です。慎重な準備と検討を行うことで、より円滑な売却が期待できます。
売却には時間がかかるケースが多い
先述したように、農地売却にかかる期間は売却方法や物件の特性によって大きく異なりますが、通常の不動産売却よりも長期間を要する傾向にあります。
売却期間の長期化は、主に三つの要因から生じます。
| 手続き内容 |
必要な準備 |
| 事前調査 |
農地区分確認、書類収集 |
| 許可申請 |
申請書類作成、各種証明書 |
| 買い手探し |
農業委員会に相談、広告出稿 |
一つ目は、必要書類の準備です。登記簿謄本や農地等権利移動許可申請書、営農計画書など、一般的な不動産売却より多くの書類が必要となります。
二つ目は、農地法に基づく各種許可の取得です。農業委員会での審査や、必要に応じて都道府県知事の許可取得などの手続きが必要となります。
三つ目は、適切な買い手の選定です。農地のままでの売却では買い手が限定されるため、条件に合う相手を見つけるのに時間がかかることがあります。
このような長期化を避けるためには、事前の準備と適切な専門家への相談が重要です。特に、農業委員会への早期相談により、必要な手続きと準備書類を明確にしておくことが推奨されます。
また、不動産の専門家や行政書士に依頼することで、書類作成や審査対応をスムーズに進めることができます。売却開始前に、これらの専門家と相談しながら、具体的なスケジュールを立てることが望ましいでしょう。
農地のままだと売却価格が安くなる傾向にある
農地としての売却価格は、宅地など他の用途の土地と比べて低くなる傾向があります。これには主に三つの理由があります。
農地価格の主な決定要因は、その土地での農業による収益性です。これは土地の肥沃度や日当たり、水はけの良さなど、農業に適した条件が重要な評価基準となるためです。また、農地法による利用制限があるため、自由な土地活用ができないことも価格に影響を与えています。
価格は立地条件によっても大きく変動します。市街地に近い農地や、道路に面している農地は、将来的な転用の可能性も考慮されて比較的高値になることがあります。一方、山間部や交通の便が悪い場所では、価格は低めとなる傾向にあります。
適正価格を知るためには、地域の農業委員会や不動産業者に相談することが効果的です。特に、近隣での取引実績や地域の農地価格の相場を確認することで、より現実的な価格設定が可能となります。また、農地の状態を良好に保ち、境界確定や必要書類を整備しておくことで、より良い条件での売却につながる可能性があります。
▼関連記事
【2025年】土地の売却相場はいくら?路線価や地価公示価格からの調べ方も解説
許可申請など転用には複雑な手続きが必要
農地転用の手続きには、複数の行政機関との調整と多くの書類作成が必要となります。転用許可を得るためには、計画的な準備と段階的な手続きの実施が重要です。
| 手続きの段階 |
必要な対応 |
重要なポイント |
| 事前準備 |
土地調査、計画書作成 |
周辺環境への配慮 |
| 許可申請 |
申請書類、証明書類提出 |
不備のない書類作成 |
| 審査対応 |
説明資料、補足資料提出 |
迅速な対応 |
まず、転用計画の作成から始まります。この段階では、転用後の土地利用計画や周辺農地への影響などを詳細に検討する必要があります。土地の測量や土壌調査なども実施し、技術的な面での実現可能性も確認します。
次に、農業委員会への許可申請を行います。申請には、転用の必要性を示す書類、土地の現況図、事業計画書、資金計画書など、多くの書類が必要となります。これらの書類は不備があると差し戻されるため、不備なく正確に作成することが求められます。
審査過程では、農業委員会による現地確認や、必要に応じて追加資料の提出などが求められることがあります。また、都道府県知事の許可が必要な場合は、さらなる審査期間を要します。これらの手続きを確実に進めるためには、行政書士や不動産の専門家への相談が効果的です。専門家は必要書類の作成支援や、行政機関との調整をサポートしてくれます。
まとめ
農地の売却は、一般の不動産売却と比べて複雑な手続きと時間が必要となりますが、適切な準備と専門家のサポートがあれば十分に実現可能です。
売却を成功させるためには、計画的な準備が不可欠です。まず、地域の農業委員会に相談し、所有する農地の区分や適用される規制を確認します。これにより農地のまま売却するか、転用して売却するかの判断材料が得られます。農地区分の確認と同時に、周辺の取引事例も調査しておくと、より具体的な計画を立てることができます。
次に、必要書類の収集と専門家への相談を行います。農地売却には複数の許可や申請が必要となるため、不動産の専門家や行政書士など、適切な専門家のサポートを受けることで、手続きをスムーズに進めることができます。特に、転用を検討する場合は、早い段階から専門家に相談することで、手続きの漏れを防ぐことができます。
最後に、具体的な売却方法の検討と実行に移ります。農地区分や立地条件、売却の緊急性などを考慮し、最適な方法を選択します。農業委員会や専門家の助言を参考に、着実に手続きを進めていくことで、確実な売却が期待できます。手続きには時間がかかりますが、準備を怠らず、必要な相談と対応を行うことで、スムーズな売却につなげることができます。
農地を売却するならTAQSIE(タクシエ)に登録
今回は、農地の売却についての重要ポイントにも触れながらご紹介させていただきました。
TAQSIE(タクシエ)は、不動産のプロの方々が所属しているサービスとなっております。一人ひとりが、宅地建物取引士の資格はもちろん豊富な実績がある精鋭たちです。
不動産売却についてのお悩みの方は、登録は無料なので、お気軽にご利用ください。
あなたのケースにあった
ご成約者の声を見てみる
絞り込む