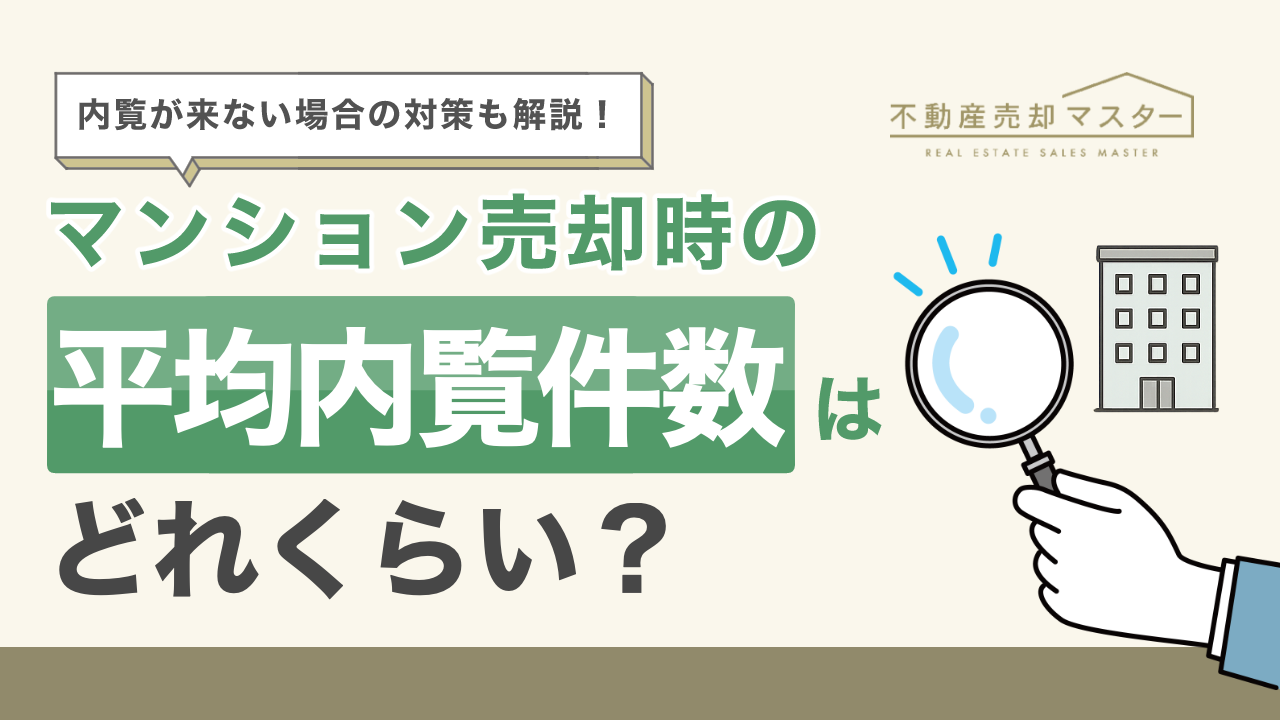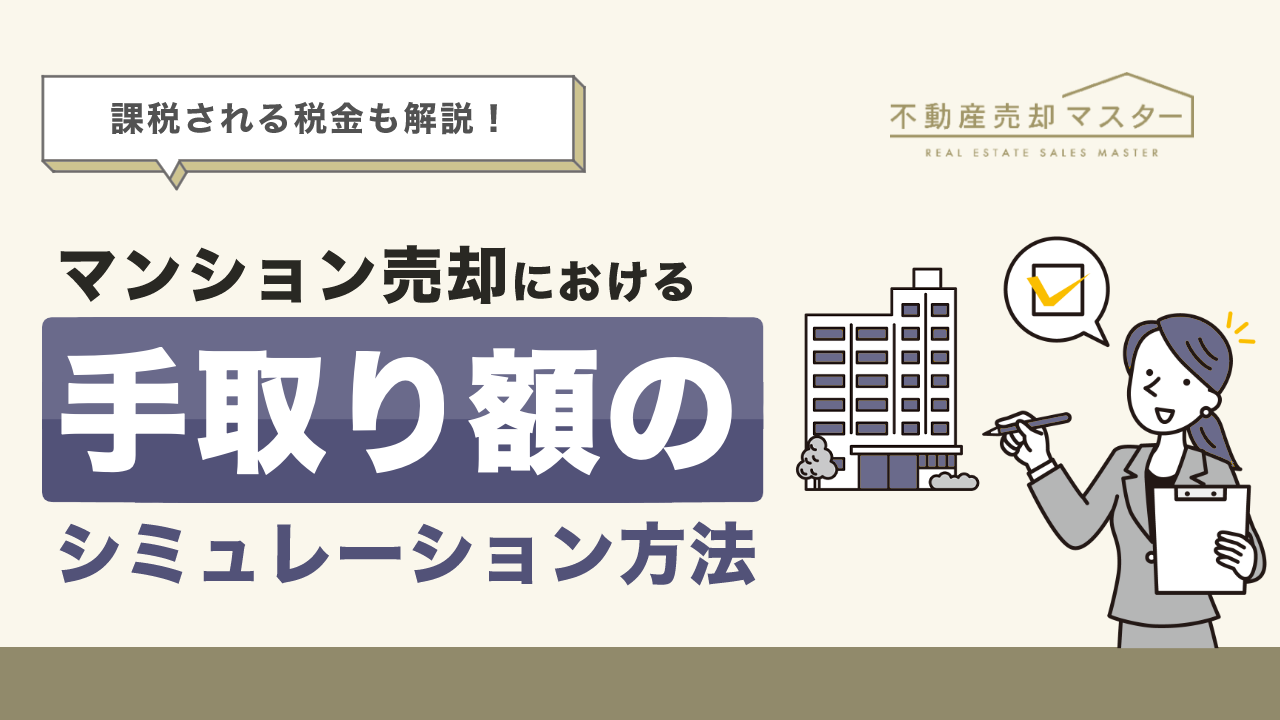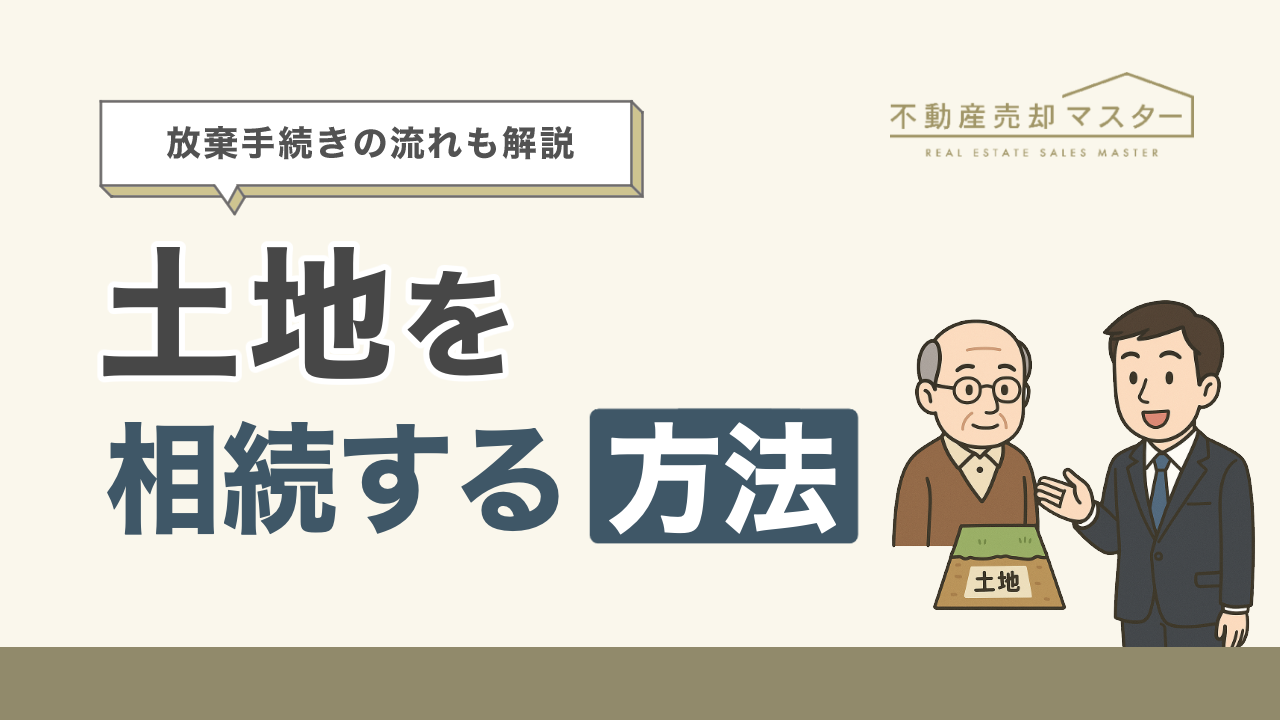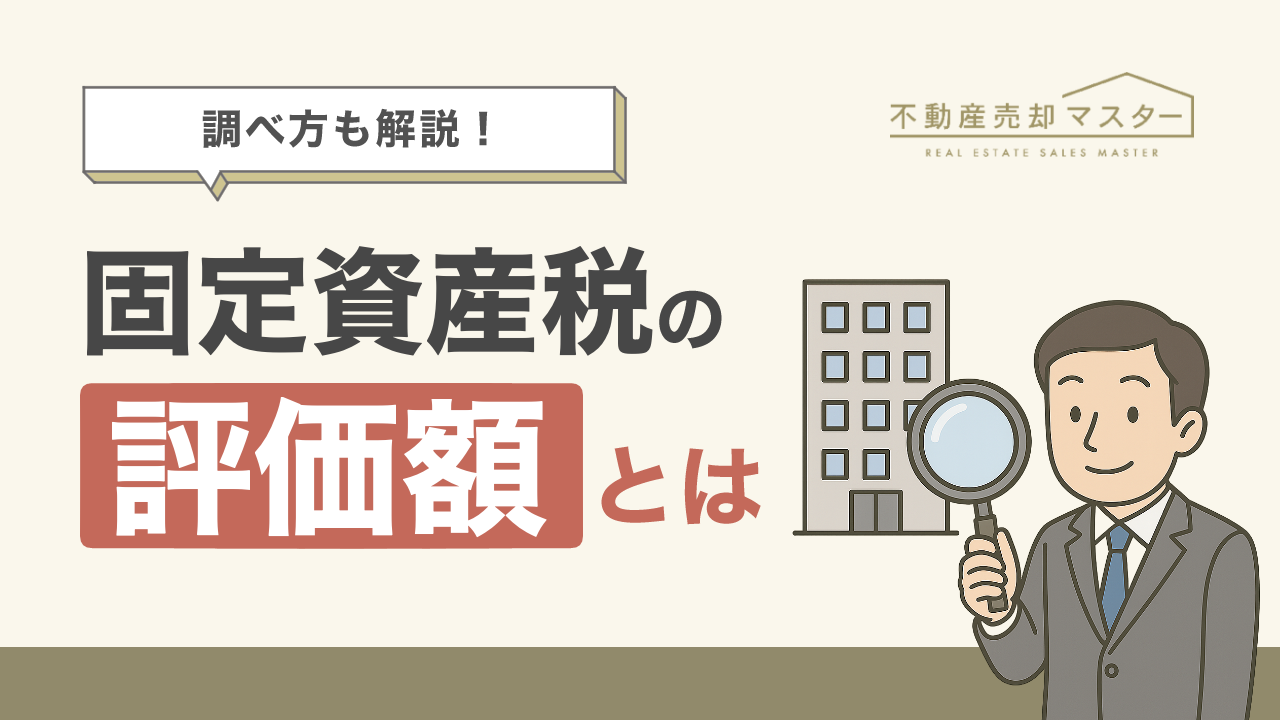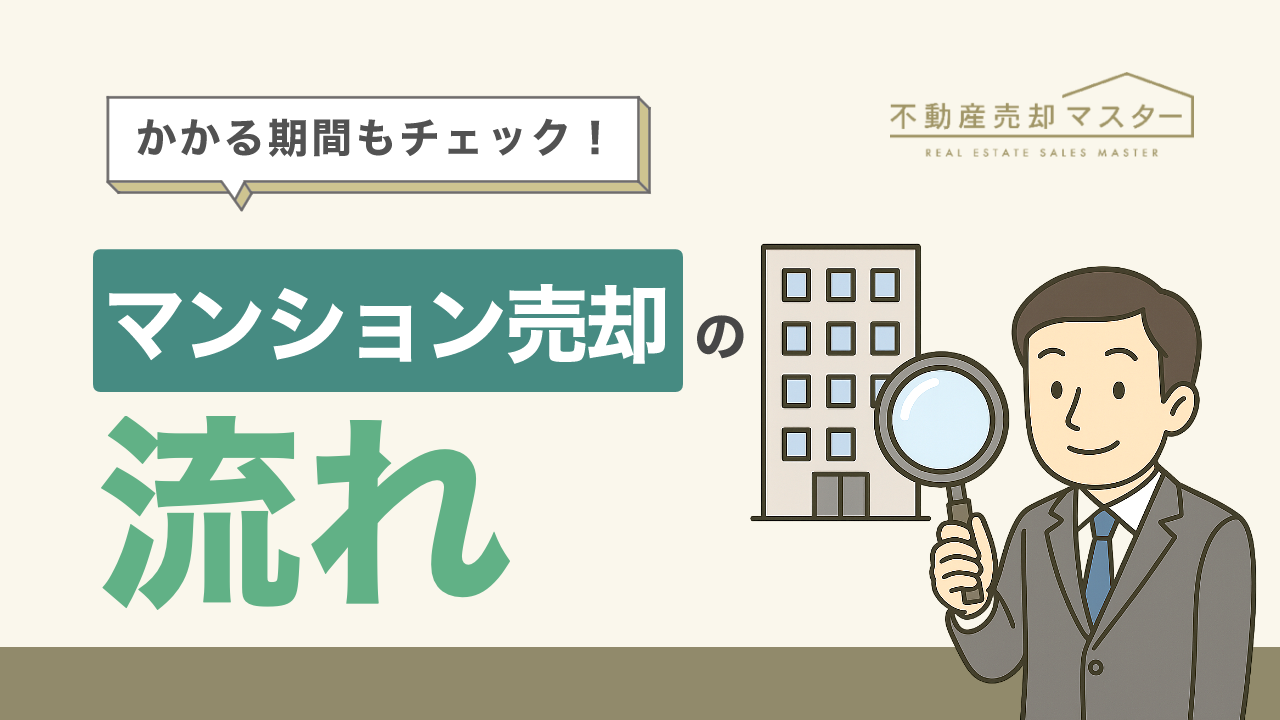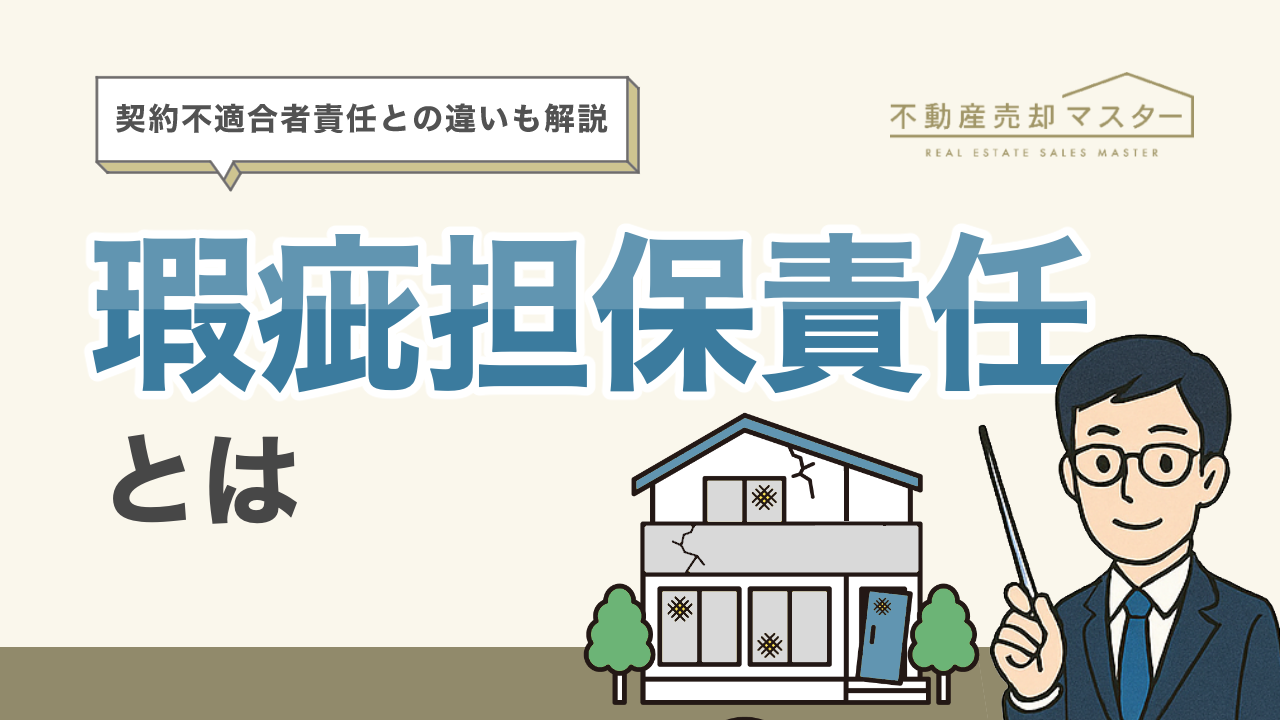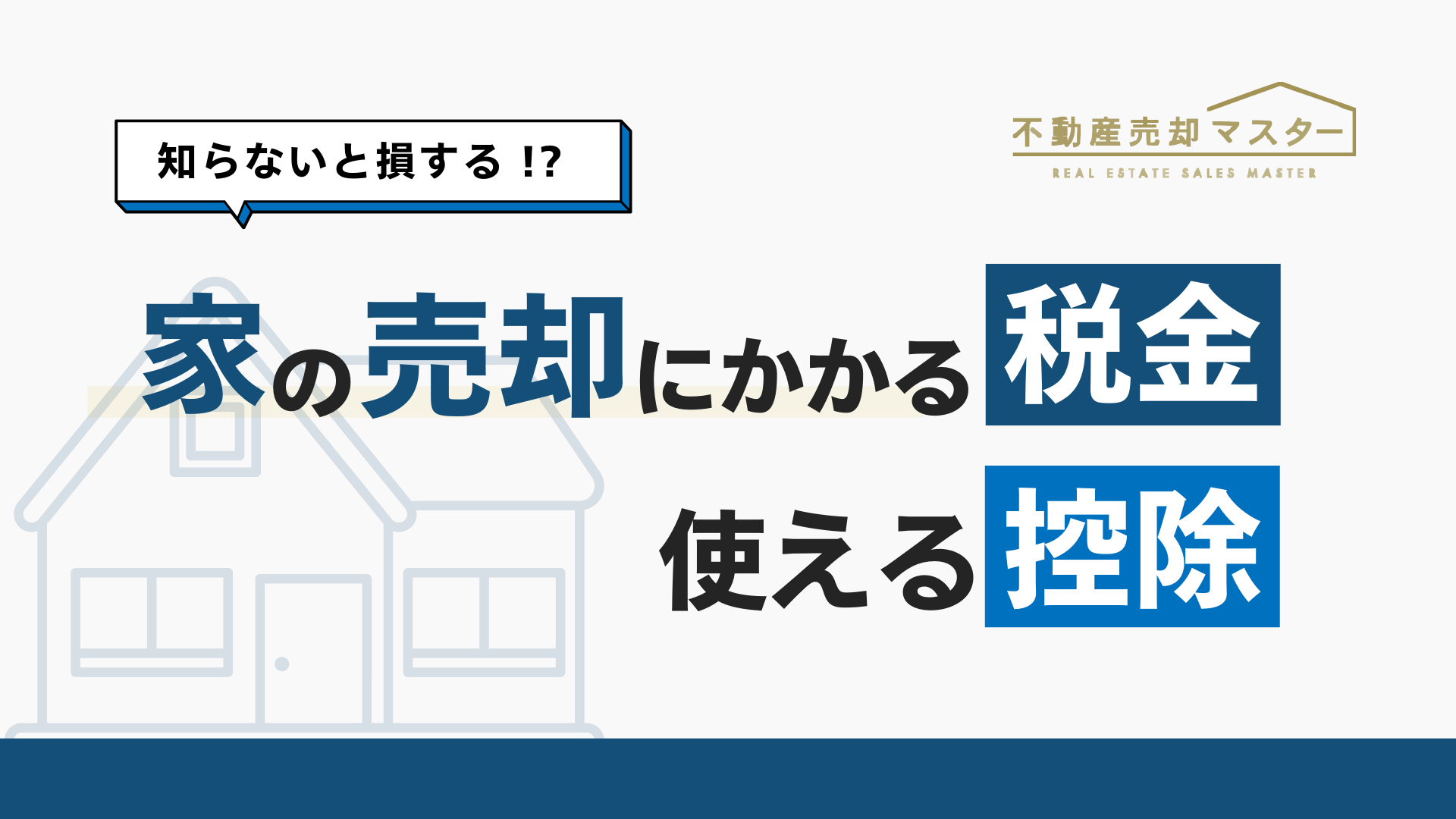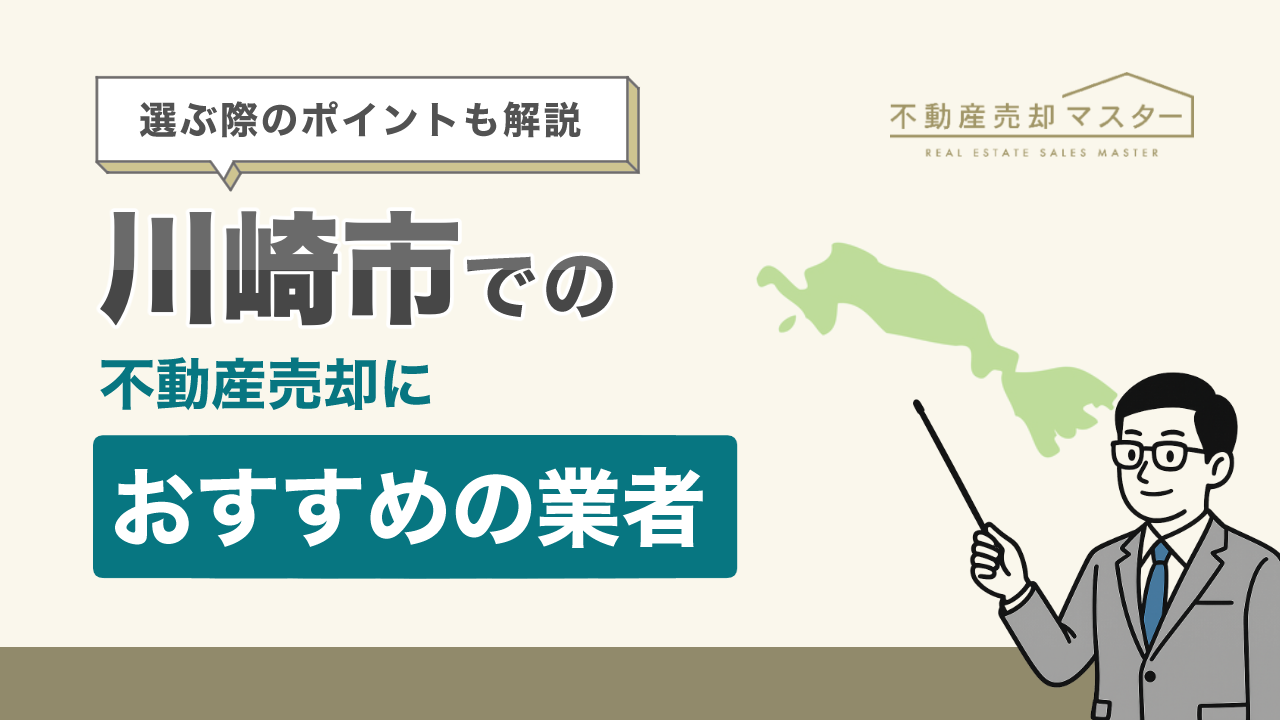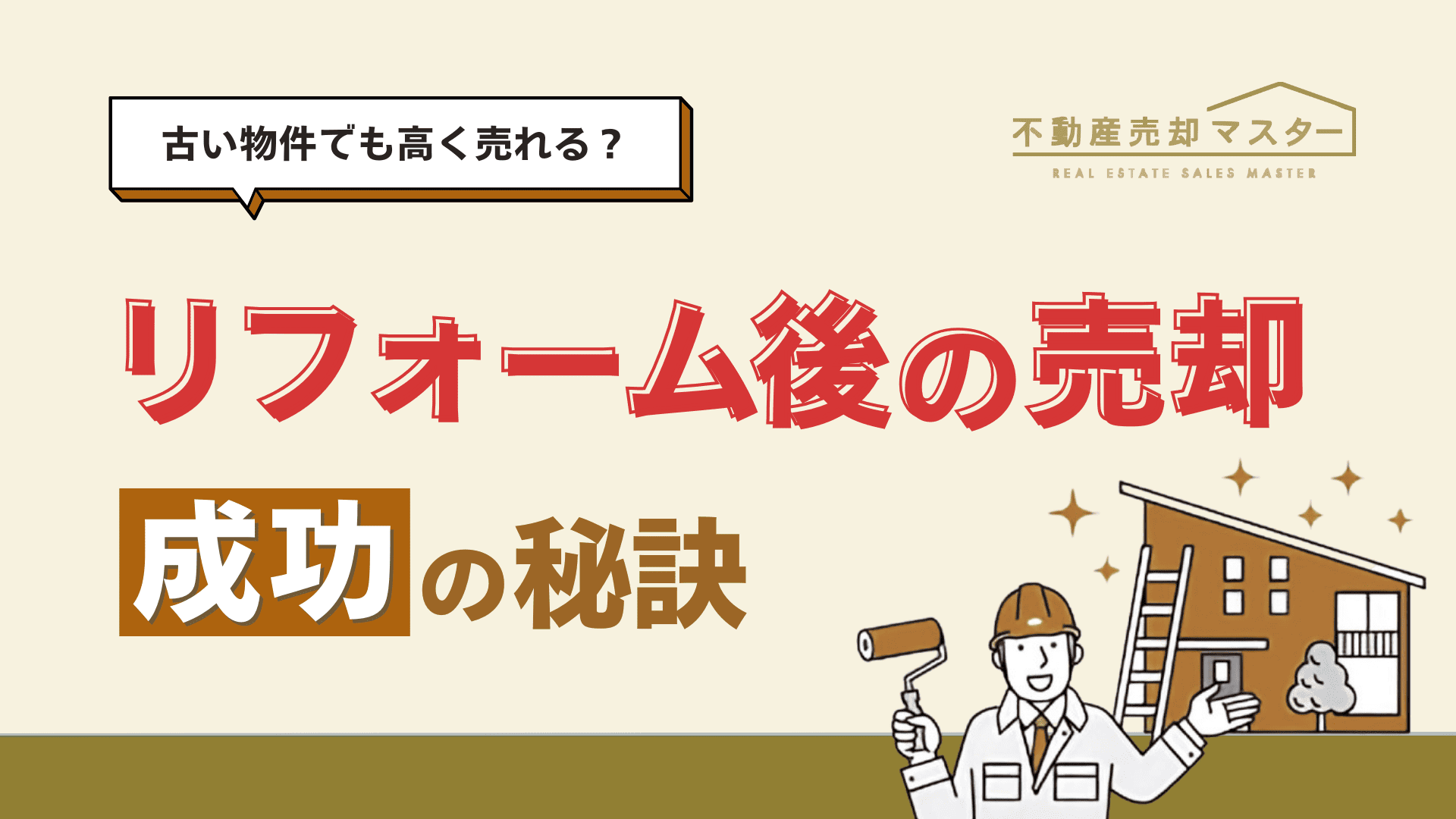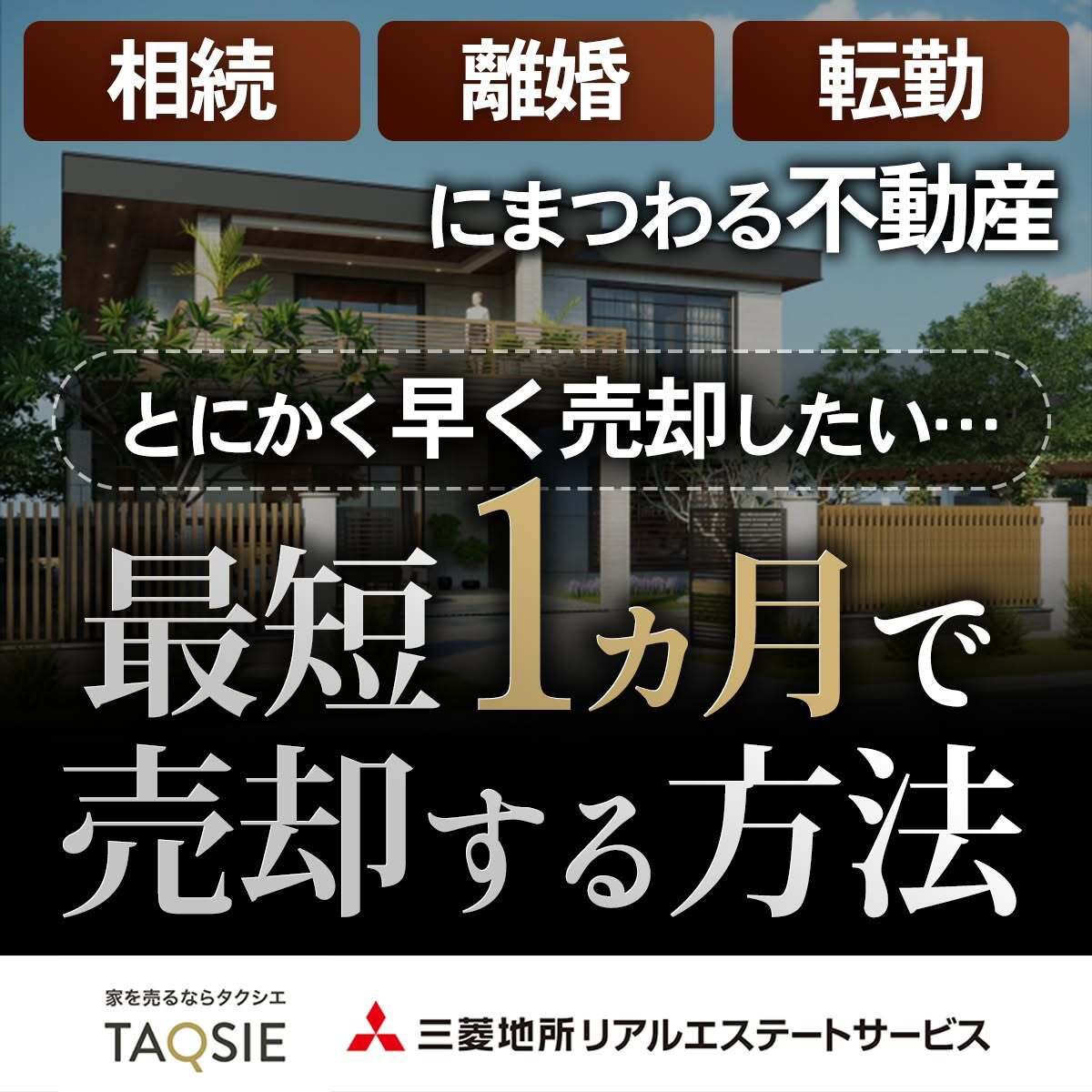都市部では高価な土地の相続税が懸念されます。適切な対策は負担を軽減できることがあります。この記事では、相続税の評価と計算方法、節税策、土地相続の要点と注意点を解説します。これらの情報を土地相続の計画に活用してください。
- この記事を読むと分かること
-
- 土地相続税は、相続税評価額に基づいて計算され、更地や建物の有無によって評価方法が異なります。
- 相続税の計算には遺産総額の算出、基礎控除額の差し引き、法定相続分の計算が含まれます。
- 土地相続時の税金対策として、特例や控除を利用することが可能です。
家を売りたくなったらタクシエ
三菱地所リアルエステートサービスが
あなたのエリアで実績の多い不動産会社をご紹介!
チャットで完結OK!
しつこい営業電話はありません!
土地にもかかる!相続税の基礎知識
まずは、そもそも相続税とはどのような税金なのかを確認しておきましょう。
相続税とは
相続税とは、亡くなった親などから財産を受け継いだ(相続した)ときに、その受け取った財産に対してかかる国税です。
相続税の対象となる財産には、現金や預貯金、株式などの有価証券のほか、土地や家などの不動産も含まれます。これらの財産から借入金や未払金、葬式費用などを差し引いたものを相続遺産総額とし、相続税を計算します。
相続税が課税されるケースとは
遺産を相続したら必ず相続税が課税されるわけではありません。相続税に対しては基礎控除が認められているため、基礎控除額を上回らなければ相続税の申告自体が不要です。基礎控除額は、以下の計算式で求めます。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
例えば相続人が配偶者と3人の子である場合、基礎控除額は3,000万円+(600万円×4人)=5,400万円です。相続遺産総額と基礎控除額を比較して、「相続遺産総額>基礎控除」であれば相続税が課税され、「相続遺産総額≦基礎控除」であれば相続税は発生しないと判断します。
相続税の申告・納税の期限
相続税の申告・納付期限は、相続の発生から10カ月です。10カ月は意外と短く、葬儀を終えて遺品を整理し、四十九日や百か日の法要をおこなうなどしていると「気がついたら期限が目の前に迫っていた!」ということも珍しくありません。
そのため相続が発生したときには相続税の期限を確認したうえで、早めに相続遺産の確定を進めることが重要です。
関連記事:
不動産の相続手続きの流れは?かかる税金や評価額の計算方法を解説
土地を相続する方法は?放棄手続きの流れや発生する税金についても解説
土地相続の完全ガイド|手続きの流れ、費用、税金対策まで徹底解説
土地の相続税評価額の調べ方
相続した土地に対する相続税は、時価ではなく「相続税評価額」に対して課税されます。ここでは相続した土地の相続税評価額の計算方法を解説します。
更地の評価方法
更地の相続税評価額は、「路線価方式」か「倍率方式」でおこなうことが国税庁により決められています。
路線価とは、国税庁が定める道路に面する標準的な宅地の1㎡あたりの価額です。路線価は主に市街地に設定されており、郊外など路線価がないエリアでは倍率方式が採用されます。
それぞれどのように相続税評価額を出すのか、順番に確認しましょう。
路線価方式
路線価方式では、道路ごとに定められている「相続税路線価」を目安に相続税評価額を算出します。
路線価は国税庁の路線価図・評価倍率表から調べます。土地のある都道府県から地域を絞り込み、道路上に1㎡あたりの単価が記載された路線価図を表示しましょう。
土地が面する道路上に表示されている数字が、その土地の路線価です。路線価は千円単位で示されるため、300となっている場合には30万円を示します。路線価から相続税評価額を算出する計算式は以下の通りです。
相続税評価額=路線価×補正率×土地面積(㎡)
補正率とは、いびつな土地に対して評価を下げるために補正する割合です。例えば
・不整形地(三角形や旗竿地など、四角形ではない形状の土地)
・間口が狭い(間口8m未満※普通住宅地区の場合)
・奥行きが長い(間口の2倍以上)
といった土地は、補正率をかけることで評価額が下がります。補正率については、国税庁のサイトで確認が可能です。
以下の土地を例に、路線価方式で相続税評価額を算出してみましょう。
出典元:https://www.rosenka.nta.go.jp/main_r04/tokyo/tokyo/prices/html/46020f.htm
この土地が接している道路上の数字は340となっているので、路線価は34万円です。補正する必要がないとした場合、この土地の相続税評価額は34万円×120㎡と計算し、4,080万円になります。
倍率方式
路線価がないエリアでは、固定資産税評価額をもとに評価する倍率方式が採用されます。固定資産税評価額は、毎年市町村役場からとどく固定資産税納税通知書に添付されているものを確認するか、役場にある固定資産課税台帳で調べましょう。
評価倍率は、国税庁の路線価図・評価倍率表で土地がある地域を絞り込んでいくことで調べます。路線価がない場合には、上部に表示されている「この市区町村の評価倍率表を見る」のリンクをクリックして評価倍率を確認しましょう。
倍率方式で相続税評価額を出す際の計算式は以下の通りです。
相続税評価額=固定資産税評価額×評価倍率
土地の評価倍率を調べたら1.2倍だったケースで相続税評価額を出してみましょう。
出典元:https://www.rosenka.nta.go.jp/main_r04/kanazawa/fukui/ratios/html/e31103rf.htm
固定資産税評価額が2,000万円だとした場合、2,000万円×1.2倍=2,400万円がこの土地の相続税評価額です。
居住用や事業用にしていた宅地の評価方法
被相続人の自宅が建っている土地などは、「小規模宅地の特例」が適用されると評価額を減額できます。
この特例は、一定の要件を満たしたときに、土地の相続税評価額が50〜80%減額できる制度です。被相続人、または被相続人と生計を同じにしていた親族が居住用・事業用としていた宅地(マンションの場合は敷地権)のみが対象となり、建物には適用されません。
小規模宅地の特例は減額率が大きいため、適用されると大きく節税できるので、制度の対象とならないかを必ず確認しましょう。
減税率は、土地がどのように使われていたのかによって以下のように異なります。
| 土地の種類 |
内容 |
上限面積 |
減額割合 |
| 特定居住用宅地 |
被相続人などが居住用にしていた宅地 |
330㎡ |
80% |
| 特定事業用宅地 |
被相続人などが事業用にしていた宅地(貸付事業をのぞく) |
400㎡ |
80% |
| 特定同族会社事業用宅地 |
特定同族会社の事業用にしていた宅地(貸付事業をのぞく) |
400㎡ |
80% |
| 貸付事業用宅地 |
被相続人などが貸付事業用(不動産貸付)にしていた宅地 |
200㎡ |
50% |
それぞれ適用される要件も異なりますが、ここでは特定居住用宅地を相続する場合の主な要件をご紹介します。
【被相続人が暮らしていた宅地】
| 取得者 |
取得者ごとの要件 |
| ① 配偶者 |
とくに要件はありません。 |
| ② 被相続人と同居していた親族 |
相続税の申告期限まで住み続け、かつ所有していること |
| ③ 被相続人と同居していない親族(家なき子) |
・①②がいないこと
・相続開始時に日本で納税義務があり、日本国籍があること
・相続開始前3年以内に、自分や配偶者、3親等以内の親族などが所有する家に住んだことがないこと
・相続開始時から相続税の申告期限までその宅地を所有していること |
【被相続人と生計を同じにしていた親族が暮らしていた宅地】
| 取得者 |
取得者ごとの要件 |
| ① 配偶者 |
とくに要件はありません。 |
| ② 被相続人と同居していた親族 |
相続開始前から相続税の申告期限まで住み続け、かつ所有していること |
参考:国税庁
賃貸住宅が建っている土地の場合
アパートやマンションなど賃貸住宅が建っている「貸家建付地」呼ばれる土地は、評価が低くなります。貸家建付地の相続税評価額の計算方法は以下の通りです。
土地の評価額=①自用地評価×{1-(②借地権割合×③借家権割合×④賃貸割合)}
①は路線価方式もしくは倍率方式で算出した相続税評価額を代入します。
②の借地権割合は路線価の横に示されるアルファベットによって以下のように決まります。
| 記号 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
| 借地権割合 |
90% |
80% |
70% |
60% |
50% |
40% |
30% |
③の借家権割合は入居者などがその建物を借りる権利で、全国一律30%と決められています。
④の賃貸割合は入居率を指し、賃貸している部屋数ではなく床面積の割合で示します。例えば床面積の合計が100㎡のアパートで、15㎡の部屋と20㎡の部屋が空室となっている場合の賃貸割合は65%になります。
土地を相続したときの相続税の計算方法
それでは実際に土地を相続した場合の相続税の計算方法を確認しましょう。
関連記事:
STEP1. 遺産総額を算出する
相続税は、土地や預貯金などの個別の遺産ごとではなく、遺産全体の総額に対してかかるため、まず遺産総額を算出することから始めましょう。
遺産には、土地や建物などの不動産、現金や預貯金、株券などの有価証券、相続開始前3年以内に贈与された財産、退職金や死亡保険金などが含まれます。これらの総額から、借金や葬式費用などの負債や経費を控除し、遺産総額を計算します。
STEP2.基礎控除額を差し引き課税遺産総額を出す
遺産総額から差し引く基礎控除額を計算します。基礎控除額は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)なので、配偶者と2人の子が相続する場合は4,800万円を遺産総額から控除します。
相続税はいくらから?
相続税は、遺産を相続した人全員に課税されるわけではなく、遺産の総額が一定額以下であれば、課税されることはないです。
相続税がかからない一定の金額を「基礎控除額」といいますが、この起訴控除額内であれば相続税がかかることはありません。
相続人の人数などによって基礎控除額が変わってしまいますが、基礎控除額の最低額は3,600万円となっています。
つまり、3,600万円を下回る遺産総額であれば、原則として相続税はかかりません。
STEP3.法定相続分の相続税額を求める
相続人それぞれの法定相続分に応じて税額を計算し、相続税の総額を出します。
法定相続割合の主な例
| 配偶者の有無 |
相続人 |
法定相続分 |
| 配偶者がいる |
子がいる場合 |
配偶者 |
2分の1 |
| 子 |
2分の1(人数で分ける) |
| 子がいない場合 |
配偶者 |
3分の2 |
| 父母 |
3分の1(人数で分ける) |
| 子も父母もいない場合 |
配偶者 |
4分の3 |
| 兄弟姉妹 |
4分の1(人数で分ける) |
| 配偶者がいない |
子がいる場合 |
子 |
1分の1(人数で分ける) |
相続税の速算表
| 法定相続分に応ずる取得金額 |
税率 |
控除額 |
| 1,000万円以下 |
10% |
ー |
| 1,000万円超〜3,000万円以下 |
15% |
50万円 |
| 3,000万円超〜5,000万円以下 |
20% |
200万円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 |
30% |
700万円 |
| 1億円超〜2億円以下 |
40% |
1,700万円 |
| 2億円超〜3億円以下 |
45% |
2,700万円 |
| 3億円超〜6億円以下 |
50% |
4,200万円 |
| 6億円超 |
55% |
7,200万円 |
例えば妻と2人の子(長男・長女)が相続した課税遺産総額が3,200万円だった場合、法定相続分で按分した相続税総額は以下のように計算されます。
妻:3,200万円×1/2=1,600万円×15%=240万円−50万円(控除)=190万円
長男:3,200万円×1/2×1/2=800万円×10%=80万円
長女:3,200万円×1/2×1/2=800万円×10%=80万円
相続税の総額=190+80×2=350万円
STEP4.実際の取得割合に応じて税額を出し控除額を差し引く
相続税の総額を、実際に取得した遺産額の割合に応じて按分します。遺言書があればその内容に従い、なければ法定相続割合で按分するか、遺産分割協議で取り決めた割合で按分します。
さらに適用される控除がある場合には差し引いて、実際に納税する額を算出します。先ほどの事例を法定相続割合で按分した場合、それぞれの相続税額と実際の相続税額は以下のようになります。
| 相続人 |
相続税額 |
実際の納税額 |
| 妻 |
350万円×1/2=175万円 |
0円(配偶者の税額軽減特例が適用) |
| 長男 |
350万円×1/2×1/2=87.5万円 |
87.5万円 |
| 長女 |
350万円×1/2×1/2=87.5万円 |
87.5万円 |
※配偶者の税額軽減特例のみが適用された場合
土地相続時の税金対策で使える特例や控除
相続税が発生したときに使える可能性がある主な特例や控除をご紹介します。
配偶者の税額軽減特例
配偶者の税額軽減特例は、配偶者の相続分について利用できる控除です。配偶者の相続分のうち1億6,000万円または法定相続分を超えない範囲で金額が大きいほうを上限として、相続税が非課税となります。(参考:国税庁)
未成年者控除
未成年者控除は、相続人が未成年者の場合に、満18歳になるまでの年数×10万円が控除される制度です。1年未満の期間がある場合は切り上げて計算します。例えば相続人が16歳9カ月だった場合9カ月を切り捨て16歳とし、2年×10万円の20万円が控除できます。(参考:国税庁)
障がい者控除
障がい者控除は、相続人が障がい者であるときに、満85歳になるまでの年数×10万円(特別障がい者であれば20万円)が控除される制度です。1年未満の期間があるときは、切り上げて計算します。例えば相続人が45歳3カ月の障がい者である場合、3カ月を切り捨て45歳とし、85−45=40年×10万円=40万円が控除できます。(参考:国税庁)
贈与税額控除
贈与税額控除は、相続開始前3年以内に贈与を受け贈与税を納めていた場合に、すでに納税済みの贈与税額が控除される制度です。相続遺産には相続開始前3年以内に贈与された財産を足す必要があるので、贈与税を払っていた場合に二重課税になるのを防ぐことが目的です。(参考:国税庁)
関連記事:
不動産を生前贈与するメリットは?手続きのやり方やかかる税金を解説
親が生きているうちに家を売るケースを紹介!生前売却をするメリットや流れを解説
相次相続控除
短期間で相続が発生したことで、同じ財産に対して相続税が重複しないようにするための制度です。被相続人が10年以内に相続を受け相続税を納税していた場合に、10%×年数の割合で控除します。(参考:国税庁)
土地を相続するときのポイントと注意点
最後に、土地を相続するときのポイントや注意点をご紹介します。
関連記事:不動産相続の流れと手続きとは?成功ポイントも解説
土地の権利関係を確認しておく
土地の相続が予想されるときには、土地の権利関係を確認しておきましょう。
現在、相続登記は義務ではないため、今の所有者が明確になっていないケースも少なくありません。その場合、土地を相続するためには祖父母やその前の代までさかのぼって相続人を確定していく必要があり、膨大な手間と時間がかかる可能性があります。被相続人が存命の間に権利関係を整理しておくと、いざ相続が発生したときに慌てずにすむでしょう。
なお2024年(令和6年)4月1日からは、相続が発生してから3年以内の相続登記の義務化が決まっています。正当な理由がないのに期限内に相続登記をしなければ10万円以下の過料が科されることもあるため、実際に相続が発生した場合には早めに相続登記を済ませましょう。
関連記事:家の相続はどう進める?注意点や相続したくないときの対処法も解説
土地の査定を受けて時価を確認しておく
実際に土地を相続するときには、相続税評価額とあわせて時価を確認しておきましょう。路線価をもとに算出される土地の相続税評価額は、時価よりも低くなるのが一般的です。そのため相続税評価額で誰が、どの遺産を相続するかを決めてしまうと、のちのちトラブルになるかもしれません。
土地の査定を受けるときには、相続に詳しい担当者に相談すると、相続方法についてさまざまな提案を受けられるのでおすすめです。土地はそのまま相続する以外にも、分筆して相続する、売却して現金化するなどさまざまな方法があります。土地のあるエリアのニーズによって、どのように相続すればよいのかを一緒に考えてもらうとよいでしょう。
関連記事:
相続した土地の売却にかかる税金は?不動産売却は3年以内が推奨される理由も解説
相続した土地を売却するには?かかる税金や3年以内といわれる理由、相談の流れも紹介
生命保険の相続税はどうなる?
ここまで土地の相続について基礎知識を解説してきましたが、相続でいうと生命保険などで発生する被相続人の死亡保険金なども相続税の対象となることはご存知でしょうか?
生命保険など家族のために保険に入っているケースは多いのでどこまでが非課税なのか課税はどこから発生するのか確認しましょう。
非課税枠は以下の計算式によって求められます。
例えば、法定相続人の数が3人であれば、1,500万円が非課税限度額となり、この非課税限度額を超えた部分が課税の対象となります。
注意点として、以下のことを確認しておきましょう。
- 相続の放棄があったとしても本来の法定相続人の数をもとに算出することができる。
- 法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人まで。
- 相続人以外が取得するときは、非課税の適用は受けることができない。
まとめ
土地にかかる相続税は、路線価や固定資産評価額をもとに相続税評価額を算出します。相続が予想される場合、事前に相続税の発生やその額を把握しておくと安心できます。
相続が実際に発生した際は、適切な相続方法を検討するため、不動産会社による査定を受けて時価を確認することが重要です。相続に詳しい仲介担当者を選ぶことで、相続方法に関する相談も可能になります。
適切な担当者を選びたい場合、担当者紹介サービスがおすすめです。例えば、三菱地所グループが運営するTAQSIE(タクシエ)では、大手不動産会社の精鋭から、条件に合った担当者とマッチングできます。是非、利用を検討してみてください。
あなたのケースにあった
ご成約者の声を見てみる
絞り込む