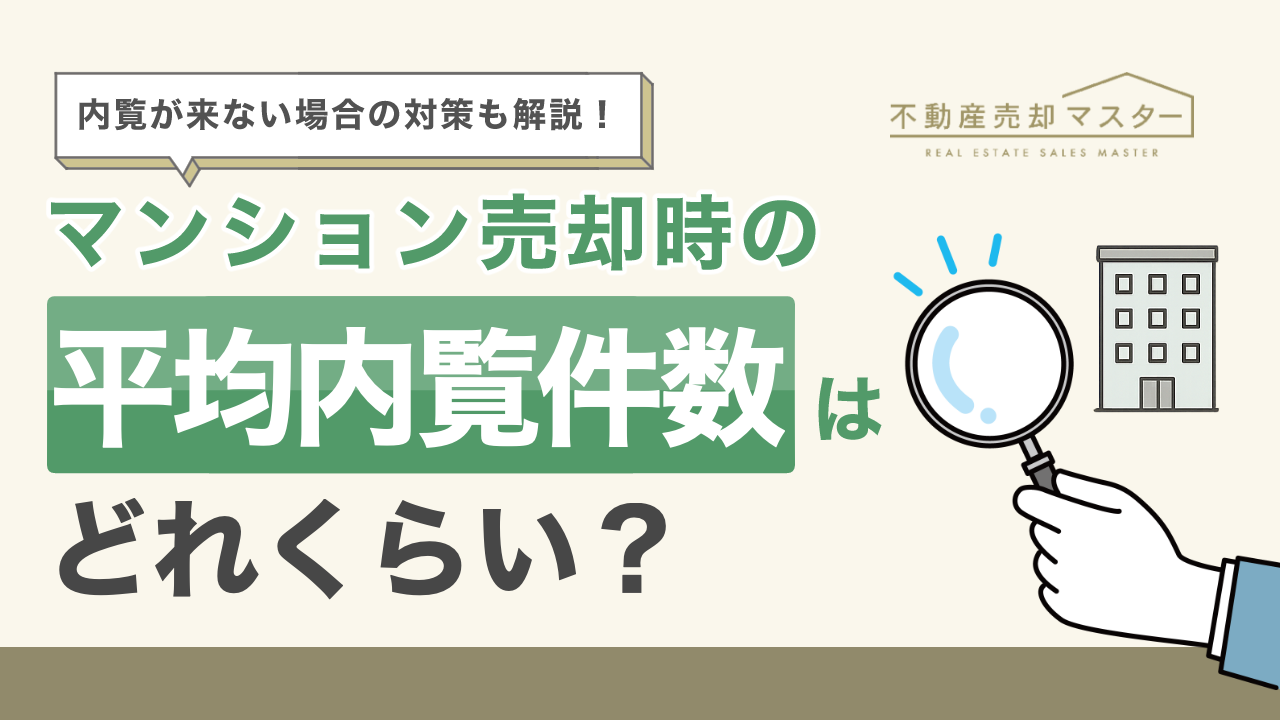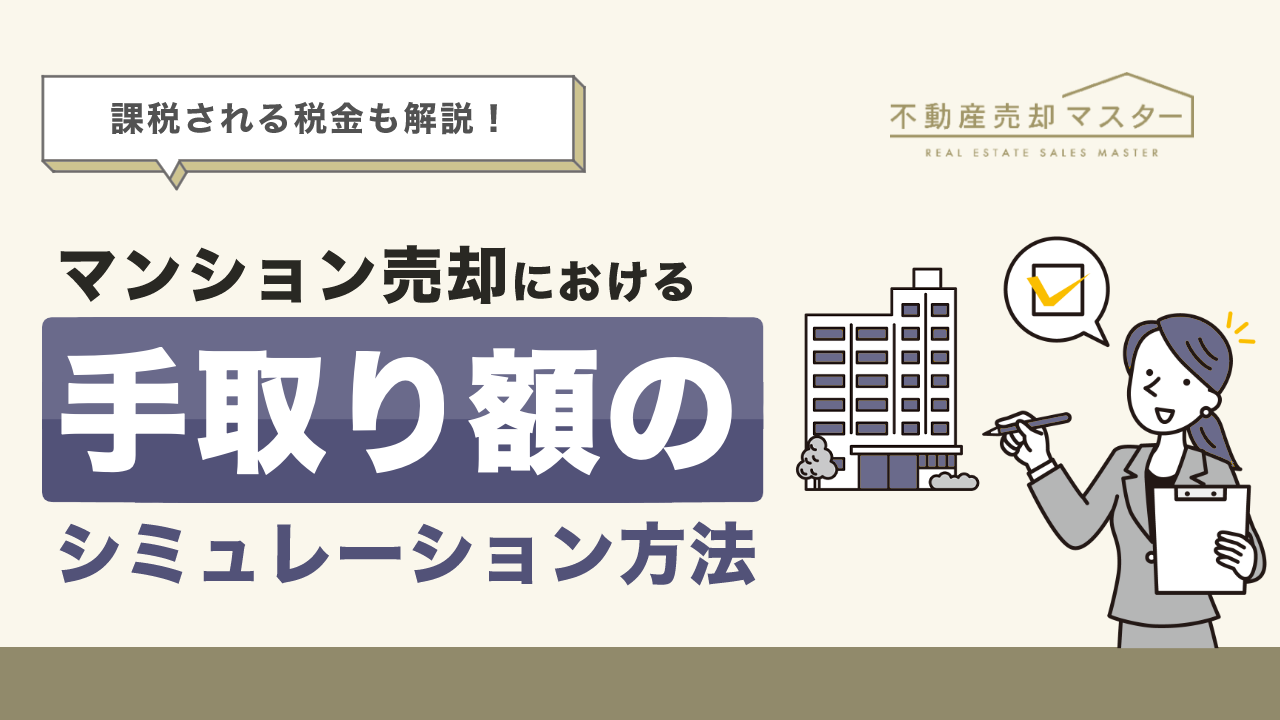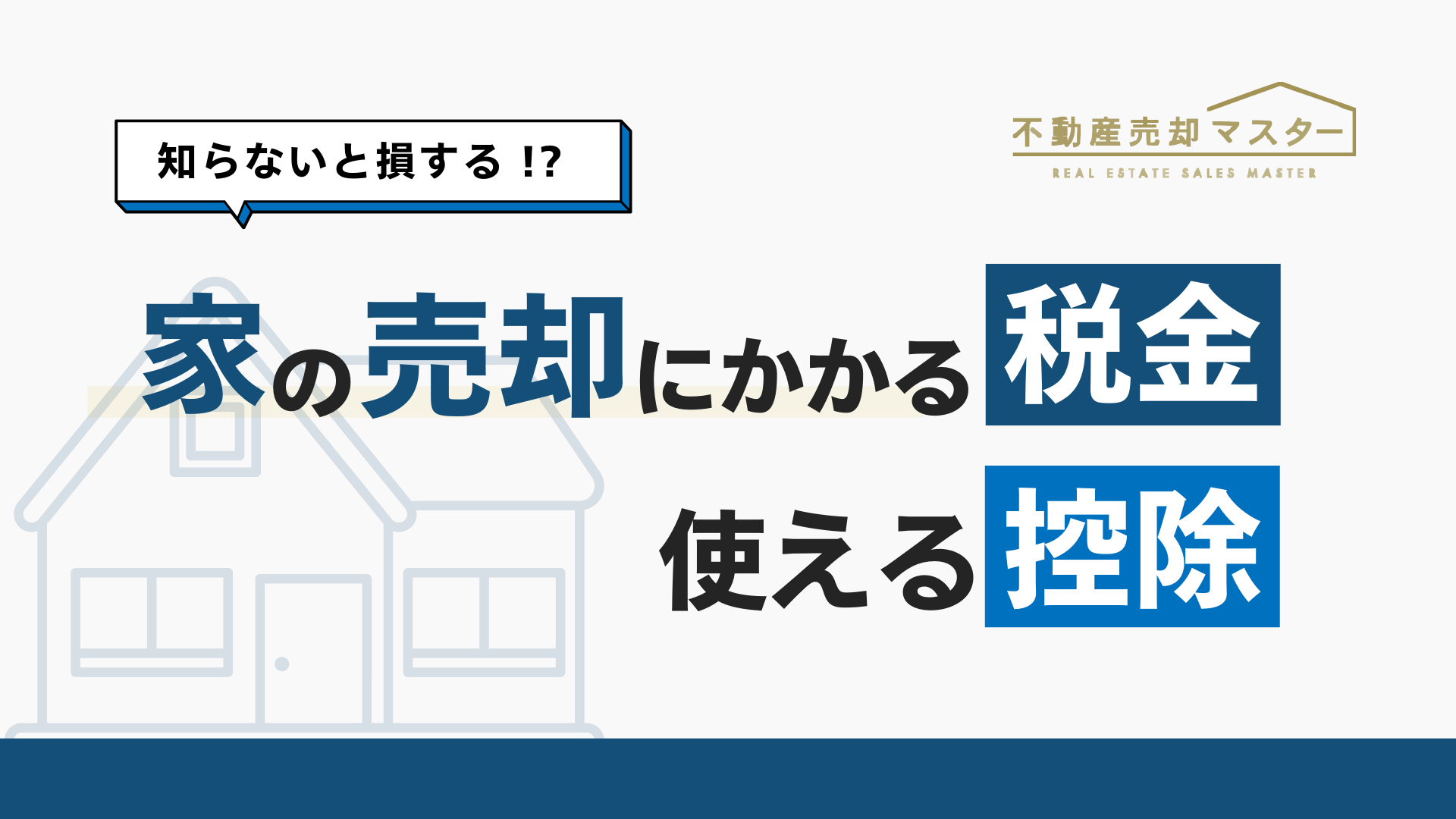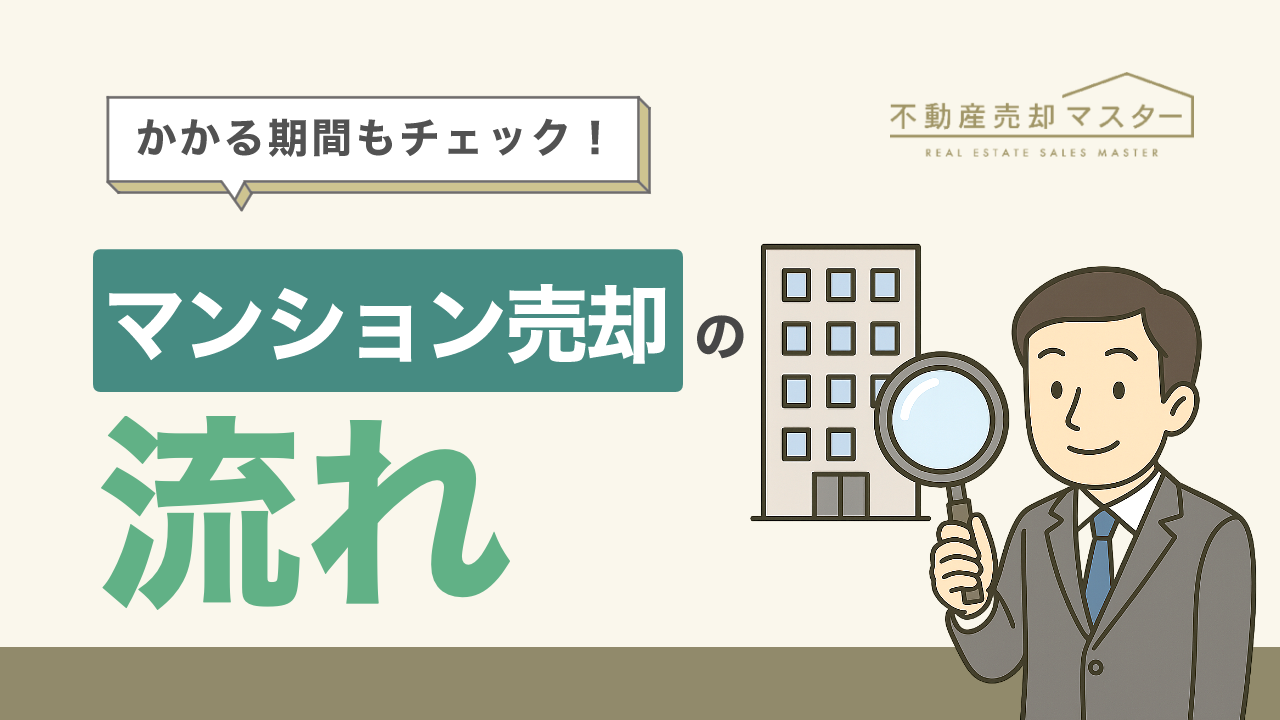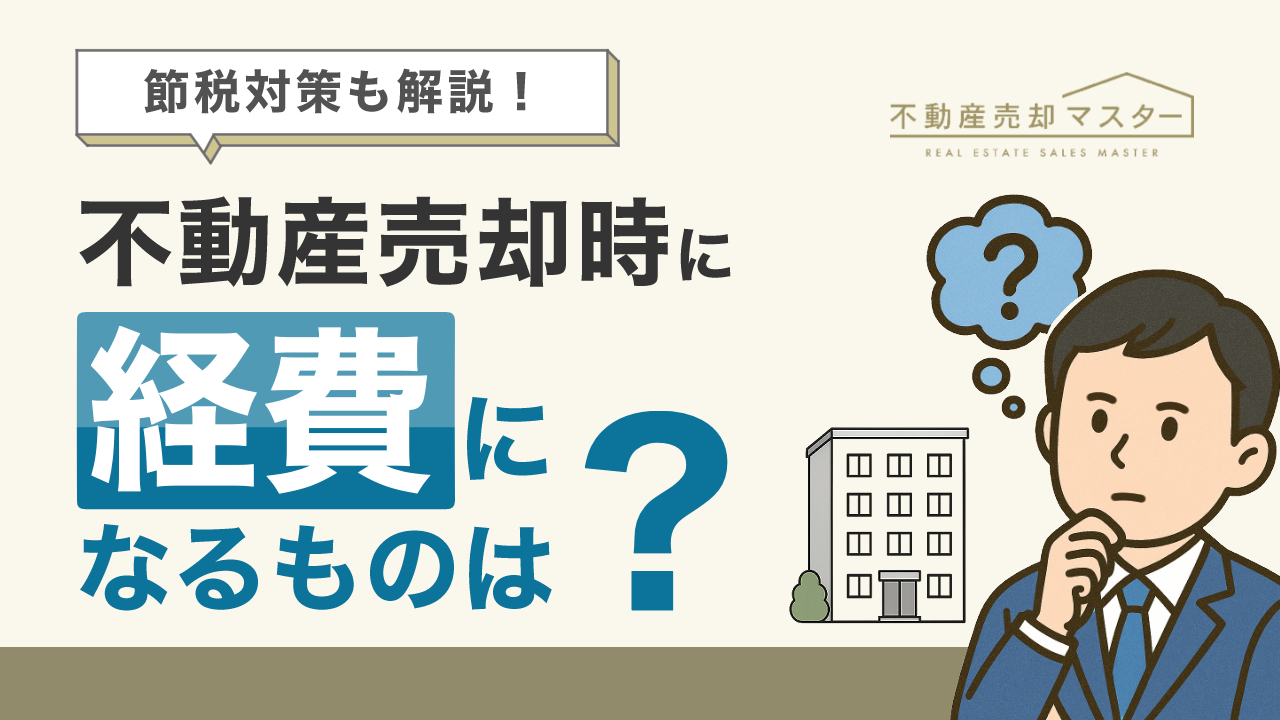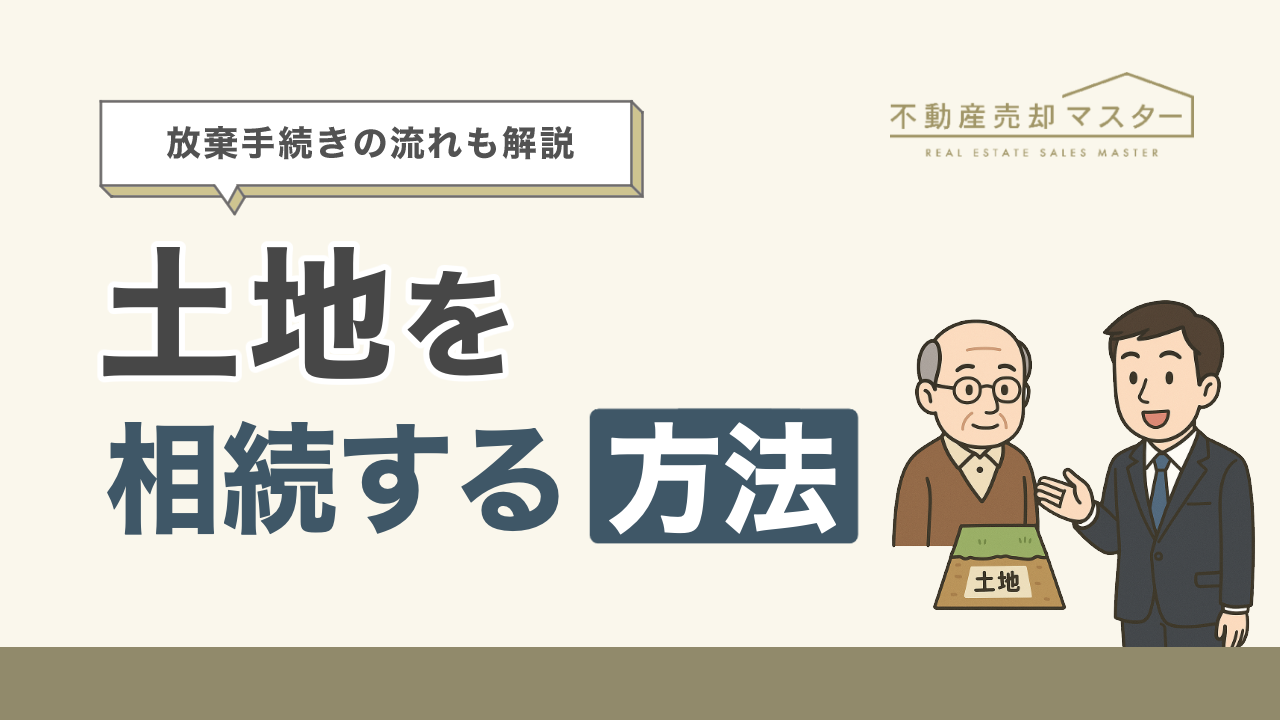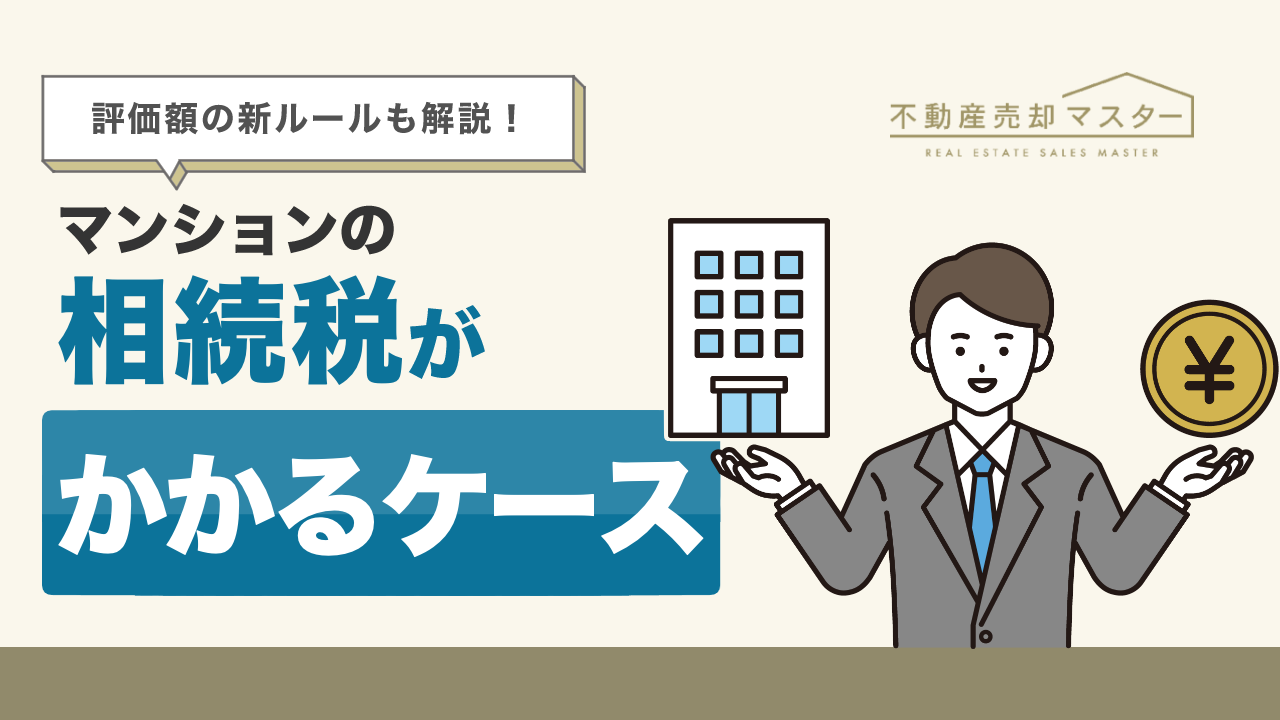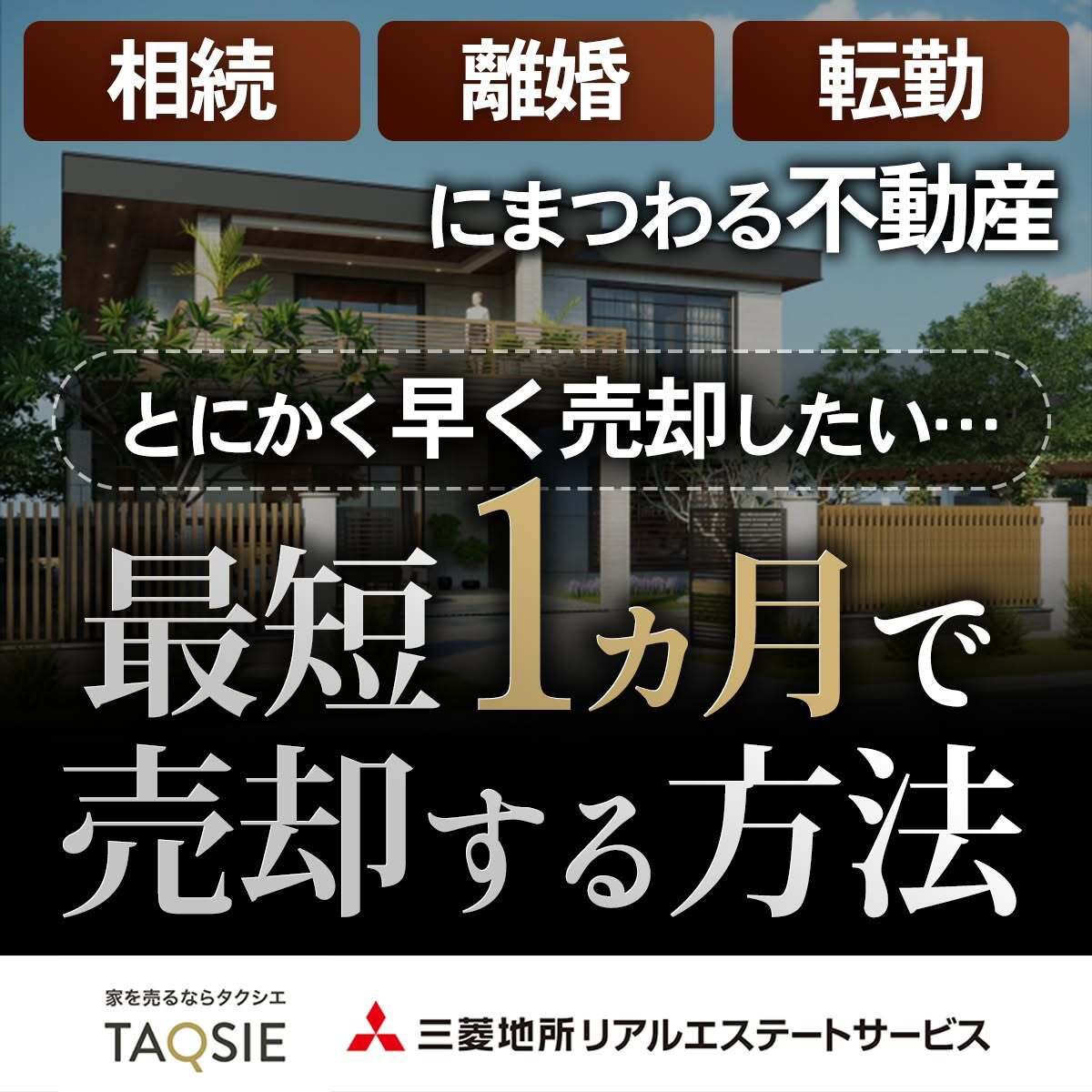家を売る際に発生する税金が気になる方も多いでしょう。
売却利益があっても税金がかかるため、「思っていたよりも手元に残らない」という事態を避けるためには、事前に税金額を把握しておくことが重要です。
本記事では、家の売却に伴う税金の種類や計算方法、節税に役立つ制度などを解説いたします。資金計画を立てる際にお役立てください。
一昔前は、マイホームの売却によって譲渡損失が発生するため、確定申告が不要なケースが多く見受けられましたが、特に昨今の都心部を中心とした不動産価格の高騰により、マイホームの売却によって譲渡所得(利益)が発生し、確定申告が必要となるケースが増加しています。様々な特例や特別控除等もありますが、勘違いしやすい注意点もあるので、ポイントを抑えておきましょう。
- この記事を読むと分かること
-
- 家を売るとかかる税金とその金額
- 税金負担を減らす特例・控除
- 家の売却時に気をつけておきたい税関連の注意点
この記事の監修者
佐藤 雄樹
株式会社Next BRANDING 代表取締役
一般社団法人東京都相続相談センター 理事
一般社団法人不動産流通プロフェッショナル協会 政策委員
[出身校]学習院大学経済学部
[保有資格]
不動産証券化マスター、不動産コンサルティングマスター(相続対策専門士、不動産エバリュエーション専門士)、宅地建物取引士
学習院大学経済学部卒業後、三菱地所リエルエステートサービスで法人営業として6年以上、不良債権処理や不動産コンサルティングに従事。リーマンショック後は会社更生・民事再生・破産案件に対して、事業再生専門の大手法律事務所と一体となり企業再生業務に従事。2011年に株式会社brandsを設立し代表取締役に就任。2013年には東京都相続相談センターの理事に就任。2020年には株式会社Next BRANDINGを設立し、相続コンサルティングに特化。各専門士業から高い支持を得ている。
家を売りたくなったらタクシエ
三菱地所リアルエステートサービスが
あなたのエリアで実績の多い不動産会社をご紹介!
チャットで完結OK!
しつこい営業電話はありません!
家を売却する際にかかる税金の種類

住み替えやライフスタイルの変更などで家を売却して利益が出た場合は「譲渡所得税」「住民税」「復興特別所得税」などの税金がかかります。
| 家を売却するとかかる税金 |
- 譲渡所得税
- 復興特別所得税
- 住民税
- 登録免許税
- 印紙税
- 消費税
|
それぞれの税金で課税される基準や支払いタイミングが異なるため、家を売却する際は「どの税金」が「どのタイミング」で「いくら必要」になるのかをしっかり把握し、シミュレーションをしておく必要があります。
関連記事:
不動産売却で生じる税金は?節税対策や確定申告が必要なケースも解説
マンション売却の税金ガイド|種類、計算方法やシミュレーション、節税対策を徹底解説
家を売る際の手続きにかかる税金
家を売る際の手続きに発生する税金は、「印紙税」「登録免許税」です。
| 税金の種類 |
費用相場 |
支払いのタイミング |
| 印紙税 |
10,000円〜30,000円程度 |
不動産の売買契約書交付時 |
| 登録免許税 |
2,000円程度 |
抵当権抹消登記の申請時 |
以下でそれぞれの税金に関する説明や具体的な金額について説明します。
印紙税
印紙税とは、「課税文書」に対して課税される税金のことです。
課税文書とは、領収書や契約書、借用書や手形、株券、債券などの印紙税法で規定されている文書のことを指します。
家を売る際に交付することが義務付けられている「不動産売買契約書」も課税文書に該当し、収入印紙を貼付する必要があるため、印紙税が発生します。
印紙税は、文書の種類や契約金額によって税額が異なります。不動産売買契約書に記載されている契約金額別の税額については以下のとおりです。
| 記載した契約金額 |
本則税率 |
軽減税率 |
| 10万円を超え50万円以下 |
400円 |
200円 |
| 50万円を超え100万円以下 |
1,000円 |
400円 |
| 100万円を超え500万円以下 |
2,000円 |
1,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下 |
10,000円 |
5,000円 |
| 1,000万円を超え5,000万円以下 |
20,000円 |
10,000円 |
| 5,000万円を超え1億円以下 |
60,000円 |
30,000円 |
| 1億円を超え5億円以下 |
100,000円 |
60,000円 |
| 5億円を超え10億円以下 |
200,000円 |
160,000円 |
| 10億円を超え50億円以下 |
400,000円 |
320,000円 |
出典:不動産売買契約書の印紙税の軽減措置|国税庁
※令和6年4月に施行された「所得税法等の一部を改正する法律」により、不動産売買契約書の印紙税軽減に係る特例措置が延長され、令和9年3月31日までは軽減税率が適用されます。
一般的な家の売却価格は1,000万円〜1億円の範囲内であるケースが多いため、印紙税の相場は1万円〜3万円程度です。
なお、不動産売買契約書を一通のみ作成し、原本を買主に交付し売主は原本のコピーを控えとして保存する場合には、売主に印紙税はかかりません。ただし、後日のトラブル・紛争が生じるおそれがあることを踏まえると、不動産売買契約書は2通作成しておくほうが好ましいです。
登録免許税
登録免許税とは、不動産の権利に関する登記を行う際に発生する税金です。
具体的には、抵当権や所有権の設定、移転、抹消など、登記に関わる手続きを行う際に課せられます。
家を売る際には、抵当権が残っている場合、売却のために抵当権を抹消する必要があり、その際この抹消手続きに対して登録免許税がかかります。例えば、ローンが残っている不動産を売却する場合や、ローン完済後にまだ抵当権抹消手続きをしていない場合は、抵当権抹消登記が必要になり、登録免許税を支払う必要があります。
抵当権抹消登記には、抵当権を抹消する「不動産1個につき1,000円」の登録免許税が課されます。一般的には、土地と建物のそれぞれに抵当権が設定されているケースが多いため、登録免許税は2,000円程度かかると把握しておけば問題ないでしょう。
なお、抵当権がついていない不動産を売却する場合は、抵当権抹消手続きが不要なため、登録免許税もかかりません。
売却益が発生した場合にかかる税金
家を売る際に、売却価格から購入費用や売却にかかった諸費用を差し引いた所得が黒字の場合(売却益が出た場合)には、譲渡所得税や住民税が課せられます。
これらの税金は、所有期間に応じて税率が異なり、所有期間が短いほど税率が高くなっています。具体的な税率は以下のとおりです。
| 区分 |
条件 |
税率 |
| 短期譲渡所得 |
売却した年の1月1日時点で、不動産の所有期間が5年以内 |
所得税:30%(30.63%)
住民税:9% |
| 長期譲渡所得 |
売却した年の1月1日時点で、当該不動産の所有期間が5年を超えている |
所得税:15%(15.315%)
住民税:5% |
出典:土地や建物の譲渡所得に対する税金|国税庁
基本的には、所有期間が5年以内の場合は「短期譲渡所得」として39.63%の税率が適用され、5年を超える場合は「長期譲渡所得」として20.315%の税率が適用されます。所有期間が10年以上のマイホームを売却する場合、軽減税率の特例の適用を受けることができます。
売却益が出た場合の譲渡所得税の納付については、不動産を売却した日が属する年の翌年の確定申告を通じて行います。例えば、2025年1月10日に不動産を売却した場合には、翌年の2026年2月16日から3月16日(※)の期間に譲渡所得の確定申告を行います。
住民税については、譲渡所得の確定申告の内容が住所地の市区町村に共有され、5月〜6月ごろに届く住民税決定通知書をもとに納付します。会社員で特別徴収を選択している場合には、会社の給与から住民税が天引きされるため、特に対応の必要はありません。
(※)基本的に申告期限は毎年3月15日とされていますが、その日が土曜日または日曜日である場合は、その翌日が期限とみなされます。
関連記事:
不動産売却益とは?計算方式や確定申告の必要性をご紹介
土地の売却でかかる税金とは?計算シミュレーションや確定申告が不要なケースも紹介
【早見表】家を売却した時の税金シミュレーション
所有期間8年の場合(譲渡所得税・住民税の税率:20.315%)
実際に家を売却した際にかかる税金は、不動産の所有目的や期間、種類によって大きく変動します。
ここでは、一般的な条件をもとに、購入価格と売却価格に応じた譲渡所得税、住民税をあわせた税金の目安を算出しました。家の所有期間が8年、特例の適用なしの場合の税額の早見表は上記のとおりです。
実際には、控除の特例を活用したり、不動産仲介手数料や印紙税など売却時にかかった費用が売却金額から差し引かれたりするため、この目安よりも税額が少なくなるケースが多いでしょう。
1,000万円の譲渡所得が出ると約203万円もの税金が発生してしまうのですね。
仰る通りです。譲渡所得が発生するということは、譲渡所得税や住民税等の納税が発生してしまいますが、特別控除や、買換特例をはじめ所有期間等に応じて軽減税率等もあり、実際の税負担を抑えることもできます。これらの制度は、細かな要件も多く、併用できない制度もあるなど、専門性が高く、複雑ですので、必ず税理士や管轄の税務署に相談してください。
家を売却するときの節税対策

家を売却する際には、多額の税金が発生する可能性がありますが、いくつかの節税対策を利用することで、負担を軽減することができます。代表的な税負担軽減措置には以下の3つがあります。
以下では、それぞれの特徴やメリット、デメリットを解説します。
居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除の特例
家を売るときに使える1つ目の節税対策が、3000万円の特別控除です。名前からイメージできる通り、売却利益が3,000万円を下回る場合は、譲渡所得税を控除するという制度です。「住まいを5,000万円で購入、8,000万円で売却し、3,000万円が譲渡益」となった場合は、譲渡所得税を支払う必要は一切ありません。
実際には、5,000万円で住宅を購入した場合であっても、取得費の計算上、購入時の土地、建物の各々の価格に基づいて算出します。建物については、購入時の建物価格から建物の構造や用途、経過年数に応じて算出される減価償却相当額を差し引いた未償却残高を取得費とするため、建物の取得費は購入金額以下になることが一般的です。
本特例を適用するための要件は以下のとおりです。
- 実際に居住していた住まいを販売すること
- 家屋部を取り壊している場合は、その土地を居住をやめてから3年目の12月31日までに売却すること
- 売却相手との親族関係や世帯関係がないこと
- 売却の前年から前々年までに他の特例を利用していないこと
適用条件こそあるものの、マイホームを手放す方であれば基本的に活用できると考えていて問題ありません。
また譲渡益が3000万円を超えたとしても、特別控除は利用可能です。3000万円を超えた部分に税率をかける形になるため、要件を満たしている場合には他の特例との兼ね合いも考えた上で活用を検討しましょう。
参考:居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例|国税庁
特定の居住用財産の買換え特例
買換え特例は、不動産を売却して新しい住宅を購入した場合に、売却時の譲渡所得にかかる税金を繰り延べられる制度です。特例を利用するためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 売却する住宅が自己の居住用であり、売却価格が1億円以下であること
- 買い替え先の住宅も自己の居住用であること
- 新しい住宅の購入は、売却する年の前年から翌年までの3年間の間に完了しなければならないこと
- 買い替え先の住宅の取得価格が、売却した住宅の売却価格と同等またはそれ以上であること
新居の取得価格が売却価格よりも低い場合、その差額に対してのみ譲渡所得税が課せられる点も重要です。
この特例は税負担を繰り延べるメリットがありますが、適用されるかどうかは、売却時と購入時の価格やタイミングをしっかりと確認する必要があります。
参考:特定の居住用財産の買換えの特例|国税庁
10年超所有軽減税率の特例
10年超所有軽減税率の特例とは、10年以上所有しているマイホームを売却する場合に、一定金額までの譲渡所得に課税される税率が緩和される特例です。
通常、譲渡所得に対しては20.315%(所得税15.315% + 住民税5%)が課せられますが、軽減税率が適用されることで、課税額は次のように減少します。譲渡所得のうち6,000万円以下の部分に対しては14.21%(所得税10.21% + 住民税4%)の税率が適用され、6,000万円を超える部分には通常の20.315%が適用されます。例えば、売却益が6,000万円の場合、通常だと約1,219万円の税金がかかるところ、軽減税率を利用すると約853万円に抑えることができます。
この特例を利用することで、長期的に所有していた不動産の売却時に大幅な税負担軽減が可能ですが、所有期間や売却額などの条件を満たす必要があるため、事前に確認することが大切です。
軽減税率の特例は、住宅ローン控除や特定の居住用財産の買換え特例との併用はできませんが、居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除の特例との併用は可能です。
参考:軽減税率の特例|国税庁
居住用財産買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
「居住用財産買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」とは、マイホームを売却して損失が出た際に、新たにローンを組んでマイホームを購入した場合に適用できる特例です。
適用要件を満たしている場合、給与所得や事業所得など他の所得との損益通算が可能となり、所得税や住民税の負担を抑えることができます。
また、特例を適用した年だけで赤字をすべて損益通算できなかった場合、残額は売却した年の翌年以後最大3年繰り越すことが可能です。
特例の主な適用要件は以下のとおりです。
- 売却損失が発生している
- 売却した家は居住用として使用していた
- 売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えている
- 売却した家から転居したのは3年前の年の1月2日以後
- 買換後の家は売却した年の前年から翌年までの間に購入し、床面積は50㎡以上
- 売却した年の翌年年末までに新居に居住すること
- 新居はローンで購入し、返済期間は10年以上
- 合計所得金額が3,000万円以内
基本的にマイホームは長期間にわたって居住していることがほとんどなので、売却する際には建物の資産価値の下落を伴っていることから、譲渡損失が発生するケースが多くなっています。
買換えに際して譲渡損失が発生した場合には、確定申告で損益通算をすることで先に納めていた所得税の還付を受けることができます。
参考:マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例|国税庁
特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」とは、住宅ローンのあるマイホームを住宅ローンの残高を下回る代金で売却し、譲渡損失が発生した場合に適用できる特例です。この特例は新たなマイホームを購入しない場合でも適用できるのが特徴です。
損益通算の対象となる金額は、①譲渡損失額、②住宅ローン残高から売却金額を差し引いた金額のうち、いずれか少ない額となります。
また、特例を適用した年で損益通算しきれなかった場合、残額は売却した年の翌年以後最大3年にわたって繰り越せます。
この特例を適用するための主な要件は以下のとおりです。
- 売却損失が発生している
- 売却した家は居住用として使用していた
- 売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えている
- 売却した家から転居したのは3年前の年の1月2日以後
- 売却金額よりもローン残高の方が多い
基本的には、オーバーローンの限度がない「居住用財産買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」の方が控除できる金額は多くなります。そのため、この特例は新たに賃貸物件に移り住む方や「居住用財産買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」の適用要件を満たさなかった場合に利用するのが一般的です。
参考:特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例|国税庁
家を売却するときの注意点
家を売却する際には、いくつかのポイントに注意する必要があります。
特に気を付けておきたいポイントは以下の3つです。
後々の手続きや費用において不利益が生じないようにするためにも、しっかり押さえておきましょう。
取得費が不明な場合の計算方法
不動産を売却した際の譲渡所得を計算するには、「売却による収入額」や「購入時にかかった取得費を示す証拠書類」などの譲渡に関するデータが必要です。しかし、特に「取得費を証明する書類」に関しては、「購入から時間が経ちすぎて記録が残っていない」「証明できる資料が手元にない」といった状況もよく見られます。
取得費が不明な場合、譲渡所得税の計算で取得費として売却価格の5%をみなす「概算取得費」を使用できます。これは、購入時の価格や諸費用の記録が残っていない場合に適用される方法です。
例えば、売却価格が3,000万円の物件の場合、概算取得費は150万円(3,000万円×5%)となります。この方法を利用すると、実際の取得費が高かった場合に比べて、譲渡所得が増加し、結果的に課税額が高くなる可能性があるため注意が必要です。
そのため、家を売る際には物件購入時の契約書や領収書が保管されているか必ず確認するようにしましょう。
売買契約書や領収書等の代わりに購入時の抵当権の設定金額が記載されている登記事項証明書や住宅ローンの契約書などがエビデンスになるという記載を目にすることもありますが、抵当権の設定金額や住宅ローンの借入金額は、購入価格そのものを証明するエビデンスにはなりえないため、税務署から否認される可能性も高い為、ご注意ください。
また、親等から相続したマイホームである場合、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡している場合には、マイホームの相続に伴って納めた相続税相当額を取得費に加算することもでき、この制度は、概算取得費と併用して利用することも可能です。
住宅ローン控除と特例は併用不可
住宅ローン控除は、自宅を購入してローン返済を続けている場合に所得税が控除される制度ですが、譲渡所得税の負担を軽減する一部の特例との併用ができません。
住宅ローン控除を適用するには、先述した以下の3つの特例を過去3年以内に受けていないことであることが求められます。
家の売却時に住み替えを目的として新しく住居を購入した場合、譲渡所得税の申告時に上記のいずれかの特例を適用した場合、新しい住居にかかる住宅ローン控除を受けられなくなるため注意が必要です。
そのため、両方の適用要件を満たしている場合には、事前に売却後にかかる税金についてシミュレーションし、どちらを適用するかを慎重に判断することが重要です。
マイホームの売却にいたっては、建物の築年数の経過に伴い、取得費が低くなるケースや、代々相続した土地等の場合、高度経済成長期より前に取得されていたことにより、土地代が著しく低額であったり、取得費が不明であることを理由に概算取得費を利用するケースが多く見受けます。また、居住用不動産である場合には、3,000万円の特別控除の適用を受ける事によって、納税が発生しないことも少なくありませんが、これらの特別控除等は、あくまで特例に基づく制度であるため、必ず申告する必要があります。尚、譲渡損(損失)となった場合、譲渡所得税の申告は不要となります。居住用不動産の3,000万円特別控除は、買換え後の住宅の住宅ローン控除との併用が認められないため、どちらを選択した方が得か、或いは、一定条件の下に組み合わせることが可能か等を税理士や管轄税務署に相談されることをお薦めします。
なお、他の所得との損益通算が可能な「居住用財産買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」と「住宅ローン控除」は併用することも可能ですが、併用するための要件もあるため、必ず、税理士や管轄税務署に相談しましょう。
また、相続によって取得した土地建物が①被相続人のマイホームで、その建物が②昭和56年5月31日以前に建築された建物(区分登記建物は除く)であり、③被相続人が他界されてから売却に至る迄の期間、継続して空き家であり続けた場合には、「相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」として、相続によって取得された者、一人当たり、譲渡所得の金額から最高3,000万円(注)まで控除することができる特例もあります。
※取得した相続人の数が3人以上である場合は、一人当たりの控除額は、2,000万円までとなります。
確定申告が必要
家を売却した場合、譲渡所得が発生した際には確定申告が必要となります。特に、売却によって利益が出た場合や、3,000万円特別控除などの特例を利用する場合は必ず申告が必要です。一方、譲渡損失が発生した場合でも、損失を翌年以降に繰り越すためには申告が必要です。手続きには以下の書類が必要となります。
- 売買契約書
- 取得費の証明書類
- 譲渡所得税に関する計算書
売却益が出た場合には確定申告が必要となりますが、譲渡損失が出た場合には、原則、確定申告は不要であるため、自分の状況に合わせて必要かどうかを判断し、適切に対応することが重要です。
家を売却するならTAQSIE(タクシエ)がおすすめ!
家の売却では、印紙税や登録免許税、譲渡所得税が発生する場合があり、売却後の資金計画に狂いが生じないか心配なときには、税金がいくらぐらいかかるかをあらかじめ把握しておくと安心です。
家の売却前に売却見込み額を調べたいときには、不動産会社の査定を受ける必要があります。その際、エリアの市場動向やマンション・戸建て売却が得意な仲介担当者を選ぶと、売却に適したタイミングや物件の事情に応じた戦略を立ててもらえます。
三菱地所グループが運営しているTAQSIE(タクシエ)なら、プロフィールを確認したうえで担当者を選べるので効率的です。ぜひご利用を検討してみてください。
あなたのケースにあった
ご成約者の声を見てみる
絞り込む